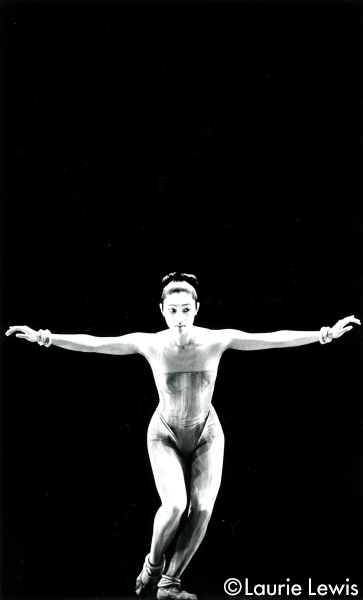振付家・ダンサーとして多彩なジャンルにアクセス
- 新年早々、2月半ばの時点ですでに3つも本番があるというのはすごいですね。ニューイヤー・ガラ『京響クロスオーバー バレエ×オーケストラ』(構成・振付・出演)、新国立劇場バレエ団『火の鳥』(振付)、白井晃演出『出口なし』(振付・出演)。『出口なし』は再演ですが、ほとんどダンス主体だった初演と違い、今回はかなりの量のセリフがある挑戦的な作品でした。
- 発表の時期が重なってしまいましたが、それぞれ分散させて長い準備期間をかけて進めさせてもらいました。昔、キリアンさんが「1日かけて1分間分のクリエイションが進められたら上出来だ」とおっしゃっていたので、私もそんなペースです(笑)。振付以前にやるべきことは山のようにありますから。
- 振付家としても、ダンサーとしても幅広いジャンルにアクセスしていらっしゃいます。クラシック・バレエ、コンテンポラリーダンスはもちろんですが、江口隆哉の振付・伊福部昭の音楽による日本のモダンダンスの歴史的作品『プロメテの火』(1950年初演)のようなアーカイブ作品への出演(2016年)、あるいは能とのコラボレーションなど。しかもすごく研究されていて、高いクオリティの作品にチャレンジされています。
- あまりジャンルでは考えていないんです。そのときに取り組めそうな仕事とうまく巡り会っているという感じです。たとえばちょうど同時期に、日中韓芸術祭2017での『A STONE』(振付)と『SAYUSA─左右左』(出演) (*1) で能の方との仕事をさせていただきました。もともと日本の芸能に憧れると同時に敷居の高さを感じて、勝手に反発していました。というのもヨーロッパで踊っていると、他の人と同じように踊っているのに「まるで能のようだ」「舞踏のようだ」「エキゾチックな花のような」という批評を受けがちで。悔しくて、日本的と思われるような表現をわざと避けていました。でも日本に帰ってくると、やはり魅力を感じてしまう。そんなときに御縁があって梅若実さん(現人間国宝)のお嬢さまである幸子さんとお話させていただく機会があり、能楽堂のあるご自宅にうかがいました。梅若さんはとてもオープンな方で、何かすごくビビッドに繋がる感触がありました。
- その出会いが世阿弥をテーマにして能の囃子を生の音楽として用いた『A STONE』に繋がったのですね。顔合わせに、たまたま僕も同席していましたが、すごく緊迫した空気でした。お付きの方から「これはできません」ということをまず告げられて(笑)。
- (指揮者のいない)能楽囃子方では、即興のような要素をすごく大切にされていて、音を出すリハーサルをしないで、本番にかけるそうです。それでもダンスのリハーサル用に笛の楽譜を声にして渡していただきました。ダンサーの私たちはそれを徹底的に聞き込んで丁寧に振りを付けて、もしも本番で速さが変わってもついていけるよう、自分たちで歌えるくらいにしました。すると感じ入っていただけたのか、「(音を出したリハーサルを)何回でもやりましょう!」と言ってくださった。音楽の揺れに対して、若いダンサーがサーッと吸い付いていくように踊るのを、多分すごく楽しんでいただけたのではないかと思います。むろん本番は一回一回がスリリングな出会いのようでした。私がダンサーとして出演した横浜能楽堂の『左右左』でも、音楽監督の大倉源次郎さん(小鼓)がいろいろな問題意識を提案されて、非常に面白いプロセスでした。
- ご自身について聞かせてください。初めはバレエからですか。
- 私が幼い頃、父がヴァイオリン造りの修行のために、家族を連れてイタリアに移住しました。私に記憶はないのですが、3歳の頃、テレビの天気予報で踊っている身体を見て、母に「私もこういうのをやりたい」と言ったそうです。ただ体操でもないし、リトミックでもないし、何だろうというようなものだったのですが‥‥。
- イタリアの天気予報で踊っている人がいた?
- いたんです(笑)。言葉は理解できないけど、人が動いているのはすごくビビッドに感じた。私は言葉を覚えるのが結構遅くて、やっと日本語で自己表現ができるようになったところでイタリアに移ったので。自分の中で「これ綺麗!」と思っても伝わらないし、人と共有できない。言葉は人と人を繋げるはずなのに、言葉によって断絶されるということを子どもながらに感じ取っていました。そこで言葉を介さないで感情などを直接やりとりできるようなものに、一生従事していきたいと思うようになりました。
- それは子どもとしては切実ですね。世界と自分のつながりをつくり上げる時期ですから。
- そうですね。ただすぐに習わせてはもらえなかったので、家にあったレコードをかけて、ぬいぐるみと踊るというのをしつこく2年間やっていました(笑)。モーツァルトとバッハと、なぜかメンデルスゾーン、それに北欧の音楽も好きでした。ついに5歳の時に母がバレエを習わせてくれました。小学校に上がる前に日本に戻ったのですが、バレエは続けました。でも、身体を動かすのがすごく恥ずかしくて、ストレッチも恥ずかしいし、レオタードに着替えて皆と一緒にやるのがすごく苦手で。教室では何もやらないで椅子にしがみついたままで、家に帰ってから自由に踊っていましたけど(笑)。バレエは18歳まで続けて、1988年ローザンヌ国際バレエコンクールで賞を貰った後に海外へ行きました。
- もともと海外で踊りたいという気持ちがあったのですか。
- 実は母がバレエに反対していて、「国際的に認められない程度ならすぐにやめなさい」と言われたので、自分でも実力を知りたい思いがあったし、コンクールに出ました。そこでプロフェッショナル賞をいただきました。
- 当時はバレエ学校に留学できる賞と、「この人はプロでやっていけるだけの実力がある」というプロフェッショナル賞がありましたよね。プロのバレエ団で十分にやれるという実力を認められたわけで、凄いことだと思います。
- ただどこかのバレエ団に入団を斡旋してくれるわけでもなかったので、とりあえず賞金だけもらって帰国しました。進学校の高校生だったので、周りはみんな受験準備の真っ最中。なのに、私は将来の方向性が何も決まっていなかった。その時ちょうどジューヌ・バレエ・ドゥ・フランスというバレエ団が日本ツアーをしていて、神奈川県民ホールの公演を観に行きました。公演もさることながら同年代のダンサーが踊っている姿に触発されて、朝のレッスンを一緒に受けさせてもらい、すぐに仲良くなりました。するとその夜、「ダンサーの一人が大ケガをした。上演するレパートリーの中に32回のグラン・フェッテが入っているけどできる人がいない。明日からツアーが続くけど、恩恵は32回転できる?」という電話がかかってきた。「はい、できます!」と。それでフェッテをやるためだけに次の日からカンパニーに入りました。ツアー終了後、「フランスまで来られる?」というので「もちろん!」とフランスで踊ることになりました。
- フランスには32回転できる人がそんなにいないのですか。
- 日本では珍しくありませんが、ヨーロッパは教育方法が違うので、意外とできる人が少ないんです。コンテンポラリーまで踊りこなせる身体の綺麗なダンサーだけど8回転ぐらいしかできないとか、多いですよ。だから自分が指導するクラスでは、「グラン・フェッテは武器になるから」と、必ずやらせるようにしています。
- それでそのままGBFのユース・バレエ団に入団することになったのですね。
- そうです。そこで、当時気鋭の振付家マチルド・モニエと現代音楽家メシアンによる『世の終わりのための四重奏曲』の創作に関わることができて、創作にも関心をもつようになりました。ユース・バレエ団は年2回、フランス各地の町を巡ってバレエを見せるツアーをします。体育館や公民館でやることもありますが、寂れた炭鉱の町で、子どもたちが私達の乗ったバスをいつまでも追いかけてきたりして、子どもたちの教育にも目覚めた時期でした。
- しかし、怪我で退団されます。
- 高校の時に球技大会で捻挫をした古傷がありました。日本だと週に2回しか稽古をしてなかったのですが、むこうでは毎日7〜8時間の労働時間ですから、無理がたたったのだと思います。フランスの病院で「あなたの足首は60歳くらい。あと数カ月放置していたら、一生走れなくなる」と言われたので、日本に戻って手術をしました。
- リハビリのためにカンヌ・ロゼラ・ハイタワー・バレエ学校へ行き、その後、アヴィニヨンのオペラ座バレエ団とモナコ公国モンテカルロ・バレエ団と契約されます。
- モナコはカンヌからすごく近くて、オーディションがあると聞いて受けたら契約することができました。でも次のシーズンの夏からだったので、それまでディレクターに誘われて半年ぐらいアヴィニヨンに在籍しました。ディレクターがフランス屈指の技巧派だったので、回転やジャンプのテクニックがすごく向上しました。
- モンテカルロ・バレエ団からネザーランド・ダンス・シアター(NDT)(*2)に移った経緯は?
- 当時のモナコのディレクターだったジャン・イブ・エスケルがNDT出身で、レパートリーにキリアンやノイマイヤー、フォーサイス等の作品が入っていました。私が入団して数カ月後、『浄夜』というキリアン作品のリハーサルを見る機会があり、「これは何!?」と衝撃を受けました。数週間後にNDT2のオーディションがあり、しかもモンテカルロ・バレエ団の休みと重なっていたので、これは受けに行くしかない(笑)と思いました。
- 『浄夜』は月下の男女の語らいを描いたリヒャルト・デーメルの詩をモチーフにしたシェーンベルグの曲に振り付けた作品です。リハーサルしか見ていないのに、そこまで中村さんを駆り立てたキリアン作品の魅力はどんなところだったのですか。
- 終盤で男女が旋回運動をしながら交差していくステップが、遠心力を操りながら展開するのですが、旋回する度に異なる次元に何かが展開していくんです。私はボリショイ・バレエのプリマだったリュドミラ・セメニャカがすごく好きで、彼女が回り終わると前と後で世界観が変わるんです。『浄夜』は作品の力でそれを成し得ていると感じて、自分の中でもっと見てみたい!とピーンときました。オーディションには何百人も受けに来ていて圧倒されましたが、私を含めて4人が新規メンバーに決まりました。
- NDTには1991年から1999年まで在籍されます。どんな9年間でしたか。
- 私がNDTで踊りはじめた頃には、ナチョ・ドゥアトもマッツ・エックもNDTのダンサーから振付家になっていて、カンパニーに作品提供していました。カンパニーは成長の最中で、若くて才能のある振付家に大きな仕事を依頼して育てていこうとしていました。オハッド・ナハリンもバットシェバ舞踊団の芸術監督になる前からNDTに作品を提供しながら大成していった。振付家が振付家として成功していくプロセスにダンサーとして関われたことは、すごくスリリングでした。
- すごい顔ぶれですね。後に現代バレエやコンテンポラリーダンスの先端を担う才能がNDTに集結している、まさに黄金期だったのですね。
-
私がいた頃は、その黄金期がかなり完成されつつある時代でした。ただマッツにしてもオハッドにしても、もちろんキリアンさんにしても、ダンサーの内奥をこじ開けて引っ張り出していく振付家なので……すごく辛い体験でもあるけれど、同時に自分の中から未知のものが引き出されていって、常に新しい何かに触れるような日々でした。
キリアンさんの新作も新しい土地に受け入れられるのか、ブーイングで罵られるのか、次の日の新聞評によってお客さんの入りが変わる胃が痛くなるような時期でした。ニューヨークではBAM(ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック)の次の日はリンカーンセンター、パリではテアトル・ド・ラ・ヴィルからオペラ座へ、という目まぐるしい日々でしたね。 - 中村さん以外に日本人のメンバーはいましたか。
- 私の後に渡辺レイさん、大植真太郎さんなどがNDT2に入りましたが、1と2はツアーや時間割も違うので、接点はほとんどありませんでした。結局、1では当時は私がひとりでした。海外拠点だった20年近く、ほとんど日本語を喋らない生活でした。
- この頃のNDTは来日公演も多かったです。画期的だったのが、彩の国さいたま芸術劇場が企画した「彩の国キリアン・プロジェクト」(00年〜04年。当時、館長だった諸井誠の依頼で、NDT3がレジデンスするほか、02年には日本初のNDT1〜3の全カンパニーの来日公演も行われた)です。
- NDTが日本で上演した『One of a Kind』に出演していた私を見て、諸井さんがキリアンさんに私のソロ作品を彩の国さいたま芸術劇場でやりたいと申し出てくださいました。実は、その提案をいただいた99年度を最後にNDTを辞めてフリーランスになったのですが、諸井さんは変わらずオファーしてくださった。でもキリアンさんは、「女性の自作自演のソロに良い作品はあまりない」と乗り気じゃなかった。で、結局「僕がつくる!」ということになり、松崎えりさんも加わった『ブラックバード』を2001年に上演しました。
- 『ブラックバード』はキリアン・プロジェクトの成果のひとつです。舞台上から細い紗のチューブが下がっていて、中村さんが動き出すと黒い衣装の女が登場してそれを断ち切ります。スピーカーから流れるキリアンのベケットの朗読やつぶやくような語りに合わせて中村さんがダンサーの半生を表現し、バックには中村さんの顔や身体の一部、NDTのダンスパートナーだったケン・オソラさんとのデュオを撮影した映像が映し出される。ラスト、中村さんは全裸で舞台を去っていきますが、身ひとつですべてを受け止めるダンサーの存在が神々しくて、愛おしくて、感動しました。衣装はファッションデザイナーの菱沼良樹でした。クリエイションのプロセスはどのようなものでしたか。
- この頃の私はキリアン作品を世界中のカンパニーに教えに行ったり、自分の作品を踊ったりしていたので、世界中あちこちで少しずつ長い時間をかけてつくっていったという感じです。キリアンさんは長い間新作をつくっていなかったのですが、久しぶりにつくった『Click – pause – silence』に手応えを感じて、『ブラックバード』を少しずつつくり貯めていきました。
- 『ブラックバード』の再演(2002年)のときは妊娠中の中村さんが膨らんだお腹で踊られて、強烈な印象でした。チューブが産道にもヘソの緒にも見えて、ものすごい迫力でした。そういう状況で踊るというのはアーティストとしての判断ですか。
- 初演の時とは構成を変えて踊りました。バレエ団なら代役もあり得るけど、フリーランスで自分の名前で引き受けた以上、床を這ってでもやるという心構えを、この時にすごく勉強しました。確かにそういう覚悟で臨むからこそ伝わるものもあると思うし、その時、自分に与えられている状況を踏まえて何が表現できるのかを考えることが大切。完璧な状況の中での完璧な踊りだけが人の心に届くわけではありませんから。だから私はキャンセルしたことはないです(笑)。
- ちなみに『ブラックバード』の前年、2000年に自作自演のソロ『ドリーム・ウィンドウ』を発表されています。これは中村さんのはじめての創作で、オランダでGolden Theater Prizeを受賞しました。
- 『ドリーム・ウィンドウ』は、京都の苔寺や天竜寺などの庭園をつくった禅僧の夢窓疎石という方のお庭を見た時に想像したことからはじまりました。ひとつの石があって、一人の女性がいて、石に腰掛けたり、石が棺や墓石のように見えたりもする。私は創作する時に自分の中に分身みたいなものが出てくるのですが、この作品の彼女も私の分身のようなもので、その彼女が内面にいるもう一人の自分と出会っていくみたいな作品でした。
- ヨーロッパの第一線で長年活動されてきた中村さんは、2007年に活動拠点を日本に移し、プロジェクト・カンパニー「Dance Sanga」を設立。2014年まで仲間たちとのダンス研究や実験的公演を行います。なぜ日本に拠点を移されたのですか。また、Sangaはどのような活動を目指したのでしょうか。
-
子どもが4歳になって学校教育が始まった時に、やはり読み書きや相手に応じた話し方が日本語でできるようになってほしいという思いが強くて、帰国しました。それが第一の理由です。
Sangaというのは仏陀が入滅した後に、皆が一つの所に集まって共に食事をしながら祈ったという“始まりの場所”のことです。自分自身が素(ニュートラル)の状態に立ち戻れる、しかも一人ではなく集団の中で行う、そういう場を創造したくてDance Sangaをはじめました。はじめてすぐに横浜のBankART NYKのStudio202にレジデンスさせていただきました。私も30代で若かったですが、20代後半から30代初めのダンサーが中心に集まり、一度海外に出て戻ってきた人が多かったです。そこで「削ぎ落としていって、常に自分のニュートラルにアクセスできる」ということをキーワードにメソッドをつくっていきました。 - 日本に拠点を移されてから、ダンサーとしてだけでなく、振付家としてとても意欲的に作品をつくられています。その中のひとつにバレエダンサーの首藤康之さんとの仕事があります。首藤さんが神奈川芸術劇場で2011年からプロデュースしている企画「DEDICATEDシリーズ」など、たくさん協働されています。そもそもの出会いを聞かせてください。
- 私が野間バレエ団に『シンデレラ』(2009年)を振り付けることになり、王子役を探していました。以前、キリアンさんが『パーフェクト・コンセプション』を東京バレエ団に提供していて、その公演で首藤さんが踊っているのを見たことがあり、いいなあと思っていました。それで、どうしてもお願いしたくて、自分で電話しました。私はこれまでの人生で電話というものを数えるほどしかしたことがない人間ですが、それくらい出て欲しかった。この頃、首藤さんは東京バレエ団を退団されていて、いろいろ考えられていた時期でお断りをいただいたのですが、一週間後ぐらいしてまた電話して、「別の企画で、私と一緒に踊りませんか?」と。そうして実現したのがバッハのピアノ曲を使った『The Well-Tempered』(2009)というデュエットです。それを発表する前に、佐藤恵子さんのインスタレーションの中で踊る『時の庭』(神奈川県民ホールギャラリー)をご一緒しました。それがシェイクスピアの詩集を題材にしたデュオ『Shakespeare THE SONNETS』(2011、新国立劇場)に繋がっていきました。
- ともにクリエイションするパートナーとしての首藤さんはどんな方ですか。
- 首藤さんはとてもミステリアスな方で、作品をつくるためいろいろと話し合っているはずなのに、舞台に立つ度に「この人だれ? 初めて見る!」と驚かされます。そういう「いま見る初めての首藤さん」が本当の首藤さんなんだろうなと思います。どんなに作品をご一緒しても、二度と同じような姿で出てくることはありません。それがまた次も一緒に作品をつくりたいと思う一番の要因だと思います。
- 中村さんのクリエイションはどのように進むのですか。たとえば、2016年のDEDICATEDシリーズで死をテーマに中村さんが演出・振付をされた『DEATH「ハムレット」』はどのようなプロセスだったのですか。この作品は『ハムレット』のプロットを用い、首藤さんがハムレット、中村さんがオフィーリアとガートルードの二役、7人の俳優がアンサンブルを務めました。冒頭のシーンは現代の美術館という設定でしたが、稽古がはじまった途端に中村さんが、「ここに絵があります!」と言い始めたと首藤さんがおっしゃっていました。できあがりのイメージがバーンと浮かぶのですか。
- 基本的には既に出来上がった作品の情景が見えている感じです。ただ夢と同じで、辻褄が合わないところも多い。それをどこまで残していくのかが難しいですけれど。曼陀羅がポンと見えるように、つくりたいものが降ってくる感じです。
- それは戯曲ベースのものでも、今年の新国立劇場バレエ団で発表した『火の鳥』(ジェンダーを問うかのようなハイヒールをはいた現代的な火の鳥の造形が話題となった)のように音楽がベースのものでも同じですか。
- 同じですね。そういうものが見えてこない時に綿密な下調べをしてアンテナを広げると、そのとき一番自分に興味があるものがビビッと引っかかったりします。
- 即興音楽家で維新派の音楽監督である内橋和久が音楽を担当し、鈴木ユキオ、平原慎太郎が出演した『ASLEEP TO THE WORLD』(2013年)を取材させていただいたことがあります。このタイトルは、ペルシャ文学史上最大の神秘主義詩人といわれるジャラール・ウッディーン・ルーミーの詩のタイトルから取られたとかで、凄い勢いでルーミーの半覚半睡の詩の話をしていただきました。「人間の魂が覚醒するのは体が眠っているとき」だとか、これがどう踊りになるのかさっぱりわからなかった(笑)。ダンサーには具体的な振り付けとして伝えていく必要があると思いますが、どうされているのですか。
- そうですね(笑)。身体の可動域や力学のこととか、振り付ける技術は本当に沢山あるので伝えることもいろいろあります。ただ、クリエイションをする際に「即興で直感的に何気なくできた動きを、もう一度やろうとしても全然できない」という不思議なことがあるんです。クリエイションの時点では直感が開かれているからできたことでも、振付として他人に渡すときには、ちゃんと動きとして分析して定着させる必要があります。
- 優れた技術の上に訪れる直感、それを分析して定着させることが振付、ということですか。
- もちろん振付には様々な方法がありますし、何をもって振付というかも人によって全然違う。私が長くいたオランダにはコンセルヴァトワール(国立高等音楽舞踊学校)やアカデミーがありますが、それぞれに振付について考え方が違いますし、特色がありました。ハーグのコンセルヴァトワールは古いバレエをキッチリやる、ロッテルダムのダンスアカデミーはカニングハム系統の基礎やテクニックを持っている人がリードしているので作品をつくるとか新しい試みが得意、アムステルダムのアカデミーは「基礎に縛られているからダメなんだ」と「ノンダンス」を掲げるとか。オランダは小さい国なので、学校同士が競い合っていて非常に面白かったですね。ノンダンスの人たちからは、私たちも技術に囚われていると批判されていました。
- NDTですら技術に囚われていると言われたのですか!
-
はい。でも5歳からやってきたバレエを、今さらなかったことになんてできませんよね。とくに私がバレエを習い始めた頃は細部にわたってスタイルへの美学が強いロシアバレエの影響が強かった。だから一度そのスタイルが身体に入ると抜くことが難しくて、応用が利きにくいことはあるかもしれません。私はボリショイ・バレエ団が凄く好きで、そこに向かって身体や骨格、筋肉が全部つくり込まれていますから。自分の身体の中に既に通り道ができてしまっていて、骨格や筋肉のレベルで可能性が限定されているような気がしたこともありました。もちろん古く美しいレパートリー作品を踊るときには、絶対にバレエの技術が必要になってきますが‥‥。オハッド・ナハリンの振付などを踊ると、これまでやってきたことが次の段階に進む足枷になっているように思えたこともありました。
それで、フリーになったばかりの頃は、自分が積み上げてきたものを一度解体して、否定して、そこに頼らない作品制作や舞踊表現というものを目指していたような気がします。ヨーロッパでは「オリエンタルな魅力」と言われないようにしていたのに、日本に帰ったら「日本人離れした魅力」と言われて、もうどうすればいいやら(笑)。でも最近は、そういう「禁じていたもの」と和解して、フラットに付き合えるようになってきました。肩肘を張らず、自分の持っているものから、その作品にとって一番必要なものを謙虚に使うようになりました。 - 「和解」とは面白い表現ですね。
-
大きな転機になったのが、赤レンガ倉庫で通年の教育普及プログラムに取り組んだことでした。その年の最後に集大成としてつくった『Silent Songs』という作品で舞踊の歴史を語る部分があり、色々勉強しました。人間がずっと過去から積み上げてきた舞踊の精神史みたいなものが現代にどう受け継がれているかを伝えていくことも、今の自分にとって大きな使命だなと思うようになりました。
もちろん昔のダンス映像を見ることはできます。でもたとえば、地面を割って積み重なる地層が見えるように、いま目の前で踊っている人の中に舞踊の歴史がしっかりと息づいていることを見せられたら、すごく豊かな体験になるんじゃないか。そこで意地を張って禁じ手にしているなんて馬鹿馬鹿しい。私自身、もっともっと学びたい、知りたい舞踊の世界は山ほどあるわけですから。 - キャリアを重ねてなお、逆に学びたい世界が広がってくるとは……すごいですね。
- いえ、のろまなだけですよ(笑)。
- 中村さんが構成・演出・振付・出演された『トリプレット・イン・スパイラル』(2018)は、近藤良平さん(振付・出演)の他に若手のバレエダンサーが出演していて、若い人のためにつくった作品という印象を受けました。若手の育成に興味をお持ちですか。
-
私は長い間ひたすら自分が踊るだけで、教える立場になったことはありませんでした。NDTにいた27歳の頃、ドイツのブランデンブルクの劇場に作品提供をした時にクラスをつくったのが初めての「教える」という経験だったと思います。29歳ぐらいから彩の国さいたま芸術劇場等でワークショップ的なことをしたり、世界中のバレエ団などにキリアン作品を教えに行ったりもしていました。キリアン作品はバレエに近いようで、けっこう遠い。なので、そこを埋めていく身体の使い方を研究して他者に伝えるための作業が必要です。ですから、最初は人を育てるというより、プロのダンサーとしてのコーチングという感じだったと思います。
転機になったのは、30代の初め頃、ローザンヌ国際バレエコンクールで17〜18歳ぐらいの子のためのコーチングを始めたことです。踊ってもらって、最終的に作品を仕上げ段階にもっていくアドバイスをする。そういう経験を通じて、まだ教育段階にある人たちを教えることに意義を見出すようになりました。日本に帰って来た時も、クリエイションと教育的な取り組み、直感的なものと技術的なものを車の両輪のように進めたいと思っていました。そんな思いが募って、コレオグラフィックセンターをつくりたいと考えました。実は、『トリプレット・イン・スパイラル』がそのスタートの公演になります。ここに出演した加藤美雨はワークショップのオーディションで選びました。こうした新しい才能も見出していければと思っています。 - それは大きな決心をされましたね。何かきっかけがあったのですか。
- 30歳ぐらいの頃に「教育に取り組まない限り、もうなにも起こらない」と言われる夢を何度も見たんです(笑)。
- それは、お告げですか!?
- 自分のキャリアを振り返ると、大海原を小さな舟で旅しているような感じでした。自分の羅針盤が本当に合っているのか、頼りにしている地図が正しいのか、それすらも判らない。嵐が来たり、途中で水がなくなったり、寄る辺ない感じを抱きながら漂っていました。でもいざという時には必ず頼りになる「港」に立ち寄ることができました。それは劇場であったり、振付家であったり、仲間や家族であったり‥‥。いろいろなレベルでいろいろな「港」があると思いますが、そこに寄れば一息つくことができて、新しい情報を手に入れて新鮮な水を貰い、大地の上で寝ることができる。再び旅立つ時には最新の地図と、信頼できる羅針盤を手にできる。私自身もまだ旅の途中だけれど、何か若い人たちの母港となるようなものを創りたいと思いました。
- 具体的にどんな活動が予定されていますか。「望みうる最高の形」でも結構なので今のところのプランを聞かせていただけますか。
-
舞踊家とは孤独な闘いを内面に繰り広げるものですが、大きなことを成し遂げるには「協力していく力」というものが大切です。コレオグラフィックセンターでは、アーティストとプロデューサーが協力関係を築いた上で事業を展開していくことを重視しています。アーティストが伸びやかに自分を磨くこのとのできる安心できる地盤、立ち寄ったら次の出発の拠点となるような整備された港を築きたいと思います。もちろん、メタファーとしての「港」ということです。
具体的には、公演を中心にして、ダンサーの育成とキャリア支援、舞台芸術全般にわたる研究や、舞踊のアーカイブの整備などを行っていきたいと思っています。もうひとつは振付家の育成です。プロの振付家や新しい世代の海外の振付家が作品をつくっていく過程を共有し、ドラマトゥルクとともに作品構成をしていくやり方、観客に見せる前に配慮すべき様々な事などを実践的に学ぶ場にしたいと思っています。アーカイブ的に重要な過去の名作と、まだ評価が定まらない若いアーティストの作品を同時に上演して、若手のチャンスになるような企画もできるといいですね。
昨年は、プレ事業として『トリプレット・イン・スパイラル』の上演、コレオグラフィックセンターの活動として、マーサ・グラハムから直接指導を受けたグラハム・テクニックに詳しい折原美樹さん(ニューヨーク在住)を招きました。動きながらグラハム作品を解説していただいたのですが、とても良かった。グラハム作品から音楽や当時の政治的な問題、舞台の美術や照明などを学ぶ、広く人を惹き付けるような座学ができました。そういう座学は、ダンサーだけではなく、観客の育成にもなります。日本の古典芸能やヒップホップ、アフリカの民族舞踊など、ダンスの裾野の広さそのものを学べる場にできればと思います。 - 中村さん自身がそこで教えるわけですか。
-
はい。そのためにもまずは自分のメソッドについて整理したいと思っています。バレエの基礎があった上でできる動きと、バレエ以外の動きの両方が必要なので。以前、発声法の資料を読んだことがあるのですが、イタリアの古い教育では「地声で歌える声の領域」と「地声だけでは歌えない声の領域」を別々に学んでいたのだそうです。だから後で両者をブレンドできる。でもこれは時間がかかりすぎるので、今でははじめからミックスされたものを学ぶようになった。結果として、その配合の中の声しか出なくて、表現の幅が狭まったと書いてありました。
とても納得がいきました。ダンスも同じで、やはりバレエは純粋にバレエとして毎日取り組まなければいけない要素としてあり、その上でバレエでは届かない表現を学ぶ必要があるのではないか。バレエができることが大前提ですが、加えて、私のベースには若い時にずっと学んでいたリモン・テクニック、オハッド・ナハリンやウィリアム・フォーサイスのメソッド、さらにはヨガや太極拳など、自分にとって必要だと思う要素があり、それをブレンドする独自のメソッドがあります。ただ、まだ系統立てて確立したというとこまではいっていないので、整理しないといけないのですが(笑)。 - それはナハリンのGAGAのように、「どんどんバージョンアップしていくメソッドだ」といえばいいんじゃないですか。
- そうですね。私はバレエの先生ではないですが、ニュートラルな、オーソドックスな基本をまず押さえたい。オーソドックスが一番難しいですから。実際の舞台では全員がトウシューズを履いて群舞を踊ることなどまずありませんが、基本のバレエはやはり重要だと思います。たとえばアレクサンダー・テクニックは別に何かの表現に直接結び付くわけではありませんが、ダンサーはダンサーなりに、演劇の人は演劇なりに、あるいは何の表現をしない人にとっても、生きるということにおいて凄く有効な身体の感じ方を提示しています。フェルデンクライスやGAGAにもそういう側面がある。とすると、必ずしもアウトプットに結び付ける必要はない。そこから豊かにものが育つことができる土壌みたいなテクニックというものも、メソッドとしては重要な要素です。
- クラシック・バレエを踊るためではなく、「よりよく生きるためのテクニック」という考え方はとても刺激的だと思います。コレオグラフィックセンターの拠点はどこになりますか。
-
場所は、THE STUDIO(*3)を拠点にはじめています。パフォーマンスの場所は劇場がすべてではありませんが、大事に丁寧に使える場所を探しておきます。また応援してくれる方を細々でも募っていくつもりです。
現代は情報も入手できますし、針路は自由に選ぶことができそうですが、ダンサーの将来は意外と選択の幅が狭く、コンクールで賞を受けたり、留学することがゴールのようになっています。迷っている若いダンサーも結構いるので、いろいろなキャリアのある方々の点在している経験を丁寧にすり合わせて、コレオグラフィックセンターという「母港」で伝えていきたいと思っています。身体で習得する人も、頭で習得する人もいるでしょうから、こちらが揃えておいた素材を、各自で取捨選択できるようにするつもりです。小さいけど、そういう思いのこもった場所をつくっていこうと思っています。 - 素晴らしいですね。本当は国がやるべきことですが…。
- でも、できる人がやりたい時に小さい規模で始めるのもいいのではないでしょうか。自由だからこそできることもありますし、大きいストラクチャーの中ではできないこともたくさんあると思うので。自分たちができることをコツコツとやっていきます。