- まずご自身について聞かせてください。演劇に興味を持ったきっかけは何だったのですか。
-
最初に演劇に興味を持ったのは13歳、中等学校での英文学の授業を通じてでした。本当に楽しかったです。1年生の時には一般の学校では教材として3冊の本が指定されていたのですが、私の学校はちょっと特殊で、補助教材としてさらに8冊を読んで感想文を書くことになっていました。年に11冊というのは、その年頃の生徒にとってはかなりの分量です。でもそのおかげで私は異なる文化の人々について書かれた物語を読むことに興味を覚えました。大学入学前も、入学後もその興味が薄れることはありませんでした。
シンガポール国立大学(NUS)に入学した時には、まだ演劇学専攻は開設されていませんでしたが、私は作品を上演してみたいといつも考えていました。でも自信がなかったのです。2年生になって演劇コンクールが開かれると聞いた時、友人が「卒業する前に1回やってみよう。この機会を逃したらもうできないかもしれないから」と。その通りだと思いました。私たちはウッディ・アレンの戯曲『神』を選び、舞台をシンガポールに移して完全に翻案した作品を作ることにしました。観客は最初から最後まで笑いっぱなし。私たちは優秀作品賞を受賞しました。
でも、終わってみると欲求不満を感じる部分もありました。外国戯曲の翻案、特にウディ・アレン作品のようにニューヨーク特有の神経症的なメンタリティが重要な作品の翻案では、私たちの文化的なルーツが表現できないと感じたのです。もっと深い翻案はできないだろうか、いやむしろオリジナルの新作を作ることができないだろうかと考えるようになりました。 - それで自分の劇団「ネセサリー・ステージ」を始めたのですね。
-
はい。コンクールの後、みんなに劇団を作りたいと提案しました。コンクールに参加していた他のグループにも声をかけました。たぶん、私は卒業後の自分の居場所を作りたかったのだと思います。
新しい劇団の名前を考えなくてはなりませんでした。誰かが「ネセサリー・シアターはどう?」と言い、私もいいなと思いました。別のメンバーがネセサリー・ステージ(The Necessary Stage:TNS)という名前を提案して、もっと深みのある名前だと思いましたし、みんな気に入ったのでそれを新しい劇団の名前にしました。
実際に何をするのかを決める必要がありましたが、自分たちのイメージやメタファーを駆使したシンガポール独自の作品を作ろうというのはみんな同意見でした。私は西洋文学を専攻する中で、外国の状況をうらやましく思っていました。私たちには自分たちの声というものがないと感じていたのです。ただ、劇団を旗揚げした1987年当時、オリジナル作品を上演するには多くの障害がありました。作品を練り上げていく方法論が確立していなかったので、評価の定まった海外戯曲を上演するほうがはるかに無難だったのです。当初は劇団員の役割も決まってなかったので、演出家、劇作家、俳優を全員で分担し、即興で作品を作っていきました。ですから、TNSではコラボレーションの感覚が当初からごく当たり前のものとして存在していました
さらに1987年に「マルクス主義的陰謀」事件 (*1) が起こったため、事態は少々複雑になりました。劇団を正式に登録するにあたって、政府から山のような質問を浴びせられました。なぜシンガポールの作品をやりたいのかについても尋ねられました。私たちが反政府的な政治劇をやるのではないかと恐れていたのです。執行委員が全員カソリックなのはなぜかということも尋ねられました。「マルクス主義的陰謀」事件に教会関係者が含まれていたことから、カソリックについても政府は神経を尖らせていたのです。正直、指摘されるまでそのことにはまったく気づいていませんでした。なぜなら理由は単純で、私たちは皆カソリック系のジュニアカレッジの出身だったというだけなのですから。 - TNSの立ち上がりがそのような政治的な目で見られていたというのは興味深いですね。その後、劇団はどのように成長していったのですか。
-
当時、「シンガポール・ランチタイム・パフォーマンス」という企画がありました。シェルやシンガポール開発銀行といった民間企業が、自分たちが持っていた小さな劇場でランチタイムに劇を上演していたのです。NUSにもそうした企画があり、私たちを含め、さまざまなアマチュア劇団がそういったところでで公演を行っていました。ギャラはほんの少しでしたが、若い演劇人にとってはまたとない成長の場になっていました。
その頃はシンガポールには劇団が数えるほどしかなかったので、新聞も私たちのことを取り上げてくれましたし、多くの人が見に来てくれました。私たちはアマチュアの学生劇団としてスタートしましたが、次第にセミプロ、プロの劇団へと成長していきました。
その過程で、私たちはコラボレーションと集団創作を柱とする独自の方法論を確立していきました。現在「M1シンガポール・フリンジフェスティバル」の共同芸術監督を務めているハーレシュ・シャルマが座付作家になったのもこの頃です。オリジナル作品を作っていく際、私たちは俳優たちにプロセスに深く関わることを求め、台本を元にしてワークショップを重ねます。ハーレシュの作劇法は伝統的な机の上での作業ではなく、稽古場で劇全体を作り上げていく過程と一体化したものになっています。
初期のもっとも成功した作品の一つ、『灯籠は消えない』(1989年)は、当初ランチタイム・パフォーマンスのために制作されたものですが、6回にわたって再演され、国家レベルの芸術祭である シンガポール・アーツフェスティバル にも招待されました。上演を繰り返し、ワークショップを行い、観客からのフィードバックを聞き、作品を改善する。このサイクルはTNSの確固たる方法論となっています。
この時期はシンガポールの演劇界がプロ化を経験している時期でもありました。1991年にはナショナル・アーツカウンシル(NAC)がコミュニティ開発省から独立し、政府が長期的視野に立って芸術支援を開始しました。私たちもそれまで携わっていた仕事を辞め、フルタイムで演劇に取り組むようになりました。当時、NACはシンガポールの芸術の育成を目的に、自国の作品を上演する劇団を優遇する政策をとっていました。例えば劇場の賃借料を無料にする「シアター・イン・レジデンス」プログラムの採択要件は、年に4本の作品を上演し、そのうち最低2本は自国作品とすることでした。これは劇団にとっては大変魅力的なプログラムですから、多くの演劇人が自国作品に取り組むようになりました。これは大きな変化でした。アートシーンは活性化し、TNSもその中で成長していったのです。 - 過去26年間でTNSにとって最も大きな問題は何でしたか。
-
検閲ではないでしょうか。私たちは、この国の問題、気質、状況といったものをテーマにして社会的な作品を作っています。私たちの作品は娯楽作品ではありませんし、純粋に個人的・精神的な物語でもありません。常に社会的な切り口があります。1980年代にはこの種の演劇は厳しく批判されました。他のアーティストの目には芸術性の低い対政府プロパガンダと映っていましたし、政府はさまざまな社会的な問題が作品でどう扱われるか、神経を尖らせていました。
問題を深く掘り下げていけばいくほど、さまざまな社会問題に触れざるを得なくなっていくことが問題をさらに難しくしていました。例えば、『オフ・センター』(1993年)は精神障害についての物語ですが、社会復帰を望む患者を受け入れることができない不寛容な社会についても語らざるを得ませんでした。当時、生産性を上げることだけに汲々としていたシンガポール人を作り出してしまった根本的な原因に目を背けることはできなかったのです。でも、そのせいで私たちの作品は賛否両論を呼ぶことになってしまいました。
政府は芸術を奨励し始めていましたが、社会や政府を批判するような作品を受け入れる準備はまだできていなかったのです。『オフ・センター』では主人公が軍隊で精神的失調に陥るのですが、それが不興を買いました。当初、この作品は保健省からの委託で制作されていたのですが、彼らは他の省庁、つまり防衛省を批判するような作品に資金提供するわけにはいかないと言いだしたのです。
私たちは台本を変更したくなかったので、保健省に資金を引き揚げてもらい、私たちが独自に作品制作を続けることを提案しました。最終的に保健省も合意しました。俳優たちはすでに9カ月もの間リサーチと稽古を続けてきていましたが、ギャラの減額に応じてくれたので制作を続けることができました。でも、政府は外国の機関から資金提供を受けているのではないかと疑心暗鬼になり、調査までされました。シンガポールに根ざした作品を作り続けるなら、常にこうした問題がつきまとうのだと覚悟せざるを得ませんでした。 - シンガポールに根ざした作品とともに、現在ではインターカルチュラルな国際共同制作がTNSの作品の柱になっています。芸術的ビジョンの中で、これはどのように位置づけられるのでしょうか。
-
1990年代になると、私たちはシンガポールの多文化・多言語・多宗教という側面に目を向けるようになりました。さまざまな民族のバックグラウンドを持つ俳優とともに、それぞれの違いを肯定的に捉えていったのです。同時に、社会の周辺に追いやられているマイノリティにも関心を向けていきました。こうしたプロジェクトを通じて育てていったのは「他者」──私たちとは違う人々、そして多くの場合には恵まれない環境にある人々──との関係でした。彼らをどう表現するかが、私たちにとっての課題になりました。
1998年、私たちはパディー・チューと一緒に『コンプリートリー・ウィズ/アウト・キャラクター』という作品を作りました。パディーはシンガポールで初めてHIVの感染を公表した人物で、HIV問題の象徴となっていました。1年にわたる共同制作プロセスを経て、彼が自分自身を題材にして舞台に立つという特別な作品になりました。観客は彼が演じるのを目撃します。でも、幕が下りても彼は病魔から逃れることはできません。彼は語るべき物語をすでに持っていたので、共同制作の過程ではそれを整理し、演劇として成立させることが目的となりました。彼の物語を補助するために、ごくシンプルなマルチメディア映像を使いました。
こうした経験を通して、私たちは他者にどう向き合い、彼らをどう表現し、アーティスティックなプロセスに彼らをどう巻き込んでいくかを学びました。私たちは俳優、観客、環境といったすべてのものを「他者化」し続けました。プロセスの中で他者性が知覚される時、物事の問題は顕在化し、そして複雑になっていきます。そうした違いの中に見いだされる「複雑性」こそ、グローバル化する今日の世界で我々が取り組むべき課題になってきているのではないでしょうか。多文化が共存する自分の国でこうした複雑性に向き合うことで、私たちが海外のアーティストと仕事をする準備ができていったように思います。
また、NACの政策が私たちに影響を与えたことも事実です。当時NACでシンガポール・アーツフェスティバルのディレクターを務めていた ゴー・チンリー のイニシアチブのもと、2000年代に入るとNACは国際共同制作のための助成スキームを整えます。シンガポールのアーティストが海外のアーティストと共同で作品を制作するのを奨励するのが目的でした。私たちのように国際プロジェクトに関心を持つアーティストが出てきて、NACがそうしたニーズに応えたとも言えますが、私たちには大きな助けになりました。 - 2005年にTNSは「M1シンガポール・フリンジフェスティバル」をスタートさせました。これはどのように始まったのですか。
-
シンガポールの電話会社「M1」は、長きにわたって私たちを支援し続けてくれています。この関係は、かつてシェルに勤務していたチュア・スィーキァットという男性がM1に移った時に始まりました。ある日、彼から「予算があるのでフェスティバルをやる気はないか?」とメールが届きました。彼は私たちがシェルの劇場で上演したランチタイム・パフォーマンスを見てくれていて、TNSならば信頼してまかせることができると思ってくれたのです。
もちろん私たちの返事は「イエス!」でした。NACが財政難から彼らの「ヤングピープルズ・シアター」プログラムを打ち切りにした直後だったので、ちょうど若者向けのフェスティバルをやりたいと思っていたところでした。1998年に始まったフェスティバルは「M1ユース・コネクション」と名付けられました。でも、しばらくするとヤングアダルト層の観客を集めるのに苦労するようになり、主な観客が子どもたちになってしまいました。「ユース(青年)」という言葉がよくなかったのです。そこで、2004年に名称を「M1シアター・コネクト」と改めました。
その年、私たちは突然状況が変わったことに気づきました。急激な国際化が起こっていたのです。あらゆるものが国際色を帯びるようになり、NACの綱領にも「シンガポールをグローバル・シティーとして発展させる」という使命が加えられました。そこで、私たちはM1に対して再度名称を「M1シンガポール・フリンジフェスティバル」に変更することを提案しました。名称変更したばかりだったので、彼らはいい顔をしませんでしたが、なんとか説得しました。フェスティバルは国際的になり、メディアもより真剣に取りあげてくれるようになったので、いい決断だったと思っています。 - フリンジなのに、フェスティバルでは毎年テーマが設定されています。どういう考えからこのポリシーが導入されたのですか。
-
私たちは、このフェスティバルがTNSと同じように社会との関わりを持つものにしたいと思いました。人々の心に刻み込まれるような作品に出会える場にしたいと思ったのです。テーマを決めることにしたのはそのためです。このような方法が従来のフリンジのあり方に反するものであることはわかっていました。キュレーターによって選ばれた作品が上演されるエディンバラ・フェスティバルへの反発から、人々はエディンバラ・フリンジに集まるのですから。「あなたたちはフリンジ、非主流と言っているが、それは何に対してなんだ?なぜキュレーションなどするんだ?そんなものがフリンジと呼べるのか?」という質問を最初はよく受けました。
シンガポール最大の劇場、 エスプラネード・シアターズ・オン・ザ・ベイ (以下、エスプラネード)をはじめとする有力な組織とパートナーシップを組むことに批判的なアーティストもいました。2005年までにはエスプラネードは国際的に知られるようになっていましたし、そこで上演したいために応募してきたアーティストもたくさんいました。ある意味では、私たちはエスプラネードの名前を利用したと言えます。批評家たちは「フリンジがこんな立派な会場で開催されるとはどういうことだ?」と書き立てました。
それに対する私たちの回答はこうです。
「シンガポールにはきわめて強固な主流文化が存在する。従って、我々アーティストは常にそうした主流文化に対する非主流としてふるまわざるを得ない。しかし、シンガポール・アーツフェスティバルがすでに確立されたものだからと言って、それに対して『フリンジ』になる必要はないし、エスプラネードに対して距離を置く必要もない。むしろ、彼らを巻き込むべきなのだ。エスプラネードの劇場にはフリンジのプログラムを入れられる容量がある。隠れてこそこそする必要はない。これは我々のフェスティバルであって、我々が西洋的なフリンジの概念にとらわれる必要はない。我々は『フリンジ』という考え方自体に反抗しているのだ」
私たちはフリンジは一種類だけであるべきではないと思っています。アヴァンギャルド・フリンジ、社会的な作品だけのフリンジ、コミュニティ・ワークしかやらないフリンジ──そんなものではなくて、フリンジは多様であり得ることを示したいと思っています。そのためにキュレーションし、ちょうどいいバランスを探っているのです。 - 2014年のフェスティバルは1月8日〜19日に開催され、テーマは「アート&ピープル」です。これは10周年という節目のフェスティバルでもありますが、何か特徴がありますか。
-
作品のインタラクティブ性ではないでしょうか。プログラムの文章を引用すると、「アートと人々との関係を見直すことで、私たちはアートと創造的プロセスの新しい可能性を開くことができる」ということを探求するため、人々をさまざまな形で巻き込んでいく作品を選びました。
例えば、シンガポールのアート・オブ・ストレンジャーズの『マウンテン』は、温暖化をテーマとしたストーリーテリングとロールプレイを組み合わせた作品で、15人のパフォーマーが登場します。それに対して観客数も15人に限定されているので、観客はとても密度の濃い演劇的体験をすることになるでしょう。また、日本の村川拓也の『ツァイトゲーバー』もパフォーマーと観客との密接な交流にフォーカスした作品です。この作品では、各回ごとに観客の一人が重度身体障害者を演じ、介護者と目の動きだけでコミュニケーションをとる体験をします。
ニューヨークを拠点に活動する現代美術家の砂入博史『マジュラー・シンガプラ:ツリー・プロジェクト』は、また別の形でシンガポール人の参加を促します。砂入のツリー・プロジェクトでは、すでに「被爆樹」として知られる広島の原爆を生き延びた木の種を人々に配り、それを育てる取り組みが行われています。今回の展覧会では、こうして育てられた苗木とともに、これまで世界中で実施されてきたツリー・プロジェクトの写真やインタビュービデオが展示されることになっています。 - 海外と国内の作品のバランスはどのように取っていますか。
-
フェスティバルが高いステータスを得られるようになったのは、国際的なフェスティバルになったからです。そのステータスを利用して、私たちは国内のアーティストの作品制作に資金を提供しています。海外のアーティストは、通常、すでに発表されている評価の定まった作品を持ってきます。もちろん私たちは大きなフェスティバルでは見られないような海外作品も紹介したいとは思っていますが、前者については大使館や助成財団などから資金援助を受けることはそれほど難しくありません。
しかし、国内のアーティストにスポンサーを見つけるのはより困難なので、私たちが資金提供をしています。それは若いアーティストだけに限らず、経験豊富なアーティストにも実験的な作品のための機会を提供しています。私たちはシンガポールの豊かな側、例えばエスプラネードから資金を調達して、国内のアーティストの創造活動を支援しているのです。 - フェスティバルの立ち上げ時には7つあったカテゴリーが2014年には3つになるなど、プログラミングが大きく変化しているように思います。 (*2)
-
昔は本当にたくさんのプログラムがありました。確か、2年目は全部で52のイベントを行ったはずです。直前にルーマニアの
シビウ国際演劇祭(ARTマニア・フェスティバル)
に参加したのですが、300ものイベントが行われ、人々は劇場から劇場へと文字通り走り回っていました。素晴らしい活気で、そういう雰囲気をシンガポールでも作り出してみたいとトライしました。
しかし、この試みは、シンガポールでは全く通用しませんでした。人々は、どれに行けばいいかさっぱりわからなくなってしまったのです。シビウでは、フェスティバルは町の一大イベントで、近隣の国の人たちもこのフェスティバルを楽しみに待っています。しかし、シンガポールでは年がら年中フェスティバルをやっています。多くの人々は「今年のプログラムは多すぎてよくわからないからスキップしよう」と考えたのです。そうしたところで、すぐに別のフェスティバルが控えているのですから。
それで、構成を徐々にシンプルにしていきました。他のフィルムフェスティバルが人気を集めるようになると、映画部門は廃止しました。共同芸術監督のハーレシュが以前言っていたように、私たちはフェスティバルを拡大するのではなく、深化させることを目指しました。10周年記念で規模を拡大するのかという質問をよく受けましたが、私たちが欲しいのはクオリティで、すべての作品が実験的・先鋭的な価値を持っていることが重要なのです。そうすれば作品は人々に衝撃を与え、人々は作品を記憶するでしょう。 - 作品の難易度の指標として「バージン/ベテラン」というラベルをつけるシステムが導入されたこともありました。数年で廃止されましたが、これも実験だったのですか。
-
このシステムを導入した理由は、作品についてきちんと情報を提供しなければ観客が自分に合っていないものを選んでしまい、結果としてフリンジ作品全体への興味を失ってしまうのではと恐れたからです。カレーの辛さ表示のようなものですね。
でも、しばらくすると「フェスティバルの観客は見るものを責任を持って選べる段階に到達しているのではないか」という批評家たちの声が聞こえてきました。「こんなことをするのは過保護だ」と言った批評家もいました。彼には、これがフリンジの精神そのものに反している行為に思えたのです。人々はリスクを負うべきだし、私たちは観客の柔軟性をもっと信じるべきだというのが彼の主張でした。私たちは同意し、ラベル付けを廃止することにしました。 - フェスティバルと政府との間に緊張関係が生じたことはありましたか。その際にはどう対処したのですか。
-
ええ、もちろん緊張関係はありますし、常に検閲の問題がありました。TNSとしても、デリケートな問題を扱う作品をフリンジで取り上げていますし。そこで、私たちは検閲を担当するメディア開発庁(MDA)との間に、ある種のコミュニケーションの回路を開くことにしました。彼らのほうでもすべての作品を一から十までチェックすることはしたくなかったので、どの作品は「安全」で、どれが議論を呼ぶ可能性が高いかを私たちの側から知らせてほしいと考えていました。それは合理的な判断でしたし、余分な労力を省きたいという点では私たちも同感でしたので、同意しました。
MDAが作品をどう捉えていいのか判断できないケースもありました。その場合は、MDAのスタッフに私たちの事務所に来てもらって一緒にストーリーをおさらいすることもしました。私たちは彼らを見下すことも、からかうことも、あるいは恩着せがましくすることもありません。スタッフは事務所に戻って上司に報告することになりますが、ストーリーや私たちの意図を明確に理解していれば、庁内で私たちを代弁し、助けてくれるからです。検閲制度に対して異なる態度を取るアーティストがいることは承知していますが、私たちはある種の協力関係を結ぶという選択をしました。彼らが受け入れられる範囲でアーティストの利益を考慮してくれることを信じようと考えているのです。
今回のフリンジフェスティバルで上演される作品に、検閲についておもしろいアプローチをしているものがあります。ポルトガルのムンド・ペルフェイトの『膝のうしろの三本の指』ですが、これは独裁政権時代に検閲に引っかかった作品を組み合わせて1本の演劇にしたものです。アーティストが主張したかったのは、このプロジェクトの劇作家は検閲官なのだということです。用いられているテクストはすべてポルトガルのもので、シンガポールのものではないので検閲のハードルは低くなります。しかし、この作品を見る時、世界中で行われている検閲、その背後にある考え方、そして検閲が芸術の創作に与える影響について、ごく自然に思いをめぐらすことになります。 - 2008年のフェスティバル・ハイライトのひとつになった「不平の合唱団プロジェクト」はフィンランドのアーティストがシンガポール人の不平不満を集めてコーラス作品に仕立てるというものでした。これはテクストがシンガポールのものなので、警察とトラブルになったと聞きました。
-
「不平の合唱団プロジェクト」では、公園やショッピングセンターなど、さまざまな場所で屋外公演を予定していました。このプロジェクトはそれまでも他の国で実施されていて、アジアではシンガポールが初めてでした。一般対象のオーディションを行い、ワークショップし、不平不満のテクストを集め、リハーサルを行いました。実に楽しい経験でした。
予想されたことではあったのですが、1行か2行、シンガポールの中央積立基金(CPF)制度 (*3) について触れた部分がありました。これが警察との間で問題になりました。彼らはコーラス隊に参加している外国人にこの歌詞を歌わせたくなかったのです。ミーティングの後、私はコーラス隊(メンバーはシンガポール人、永住権取得者、外国人で構成されていました)のところに戻って状況を説明しました。誰もが、特にシンガポール人が「みんなと一緒にやりたい」と言いました。彼らはすでに2週間にわたって共に作品を作ってきていたのですから。もちろん、オーガナイザーとして、私もそうしたいと思いました。当時、シンガポールは礼儀正しい社会を作ろうという標語を掲げていたのに、「外国人はコーラス隊から出て行って」というのですから皮肉です。
実は、この件に関してMDAのスタッフが私たちを弁護してくれたのです。最後の最後まで警察と話をしてくれました。私たちはコーラスのメンバーと共に、プロジェクトを実施するために何ができるか必死に考えました。ついにプロジェクトのメイン会場だったアーツハウスが、「ここでやっていいから他の会場はキャンセルしなさい」と言ってくれました。そして、私たちからも招待者だけのプライベート・イベントとして実施することを提案しました。招待した観客は、入口で登録するようにしました。これは二重の安全策でした。私はそれをMDAに連絡し、MDAが警察に連絡し、それですべてが決着しました。
誰も知らなかったのですが、実はこの時、プロジェクトのドキュメンタリーを作るために何人かの撮影班が同行していました。彼らはこのプライベート公演を撮影し、翌日、フェスティバルが終了してからYouTubeで公開しました (*4) 。国際的な反響を呼びましたが、政府からは何のお咎めもありませんでした。私たちは法律に違反しないよう警察から指示されたことを、その通りに寸分違わずやったのですから。
この出来事の後、多くのレポーターやジャーナリストが電話をかけてきましたが、私たちはノーコメントを貫きました。私たちはやるべきことをやったのであり、オーガナイザーという立場で作品を守る発言をすべきではないと考えたからです。もし私たちが不平を言い出したら、すべての人たちの努力を台無しにすることになってしまいます。それよりも、他の人に作品を守ってほしいと思いました。実際、新聞で報道されると、多くの海外在住のシンガポール人から警察の措置への非難の声が寄せられました。 - 民間の劇団にとって、このような大規模な国際フェスティバルを毎年開催するのは重荷ではありませんか。
-
年間を通じて活動している強力な運営チームと実施テンプレートがすでに出来上がっていますので、そんなに重荷ではありません。それと、作品を共同で上演している会場からのサポートが大きな助けになっています。こうしたサポートは拡大し続けています。例えば、2015年に開館予定の新しい国立美術館からはすでに「フリンジのために提供できる会場がある」と言っていただいています。そうしたサポートの申し出があるぐらい、人々はこのフェスティバルを求めています。
実は、ある時点でフェスティバルを終わりにしようと思ったことがありました。でも、多くの人から「やめないで!」という声が寄せられて、思いとどまりました。代わりにフェスティバルの芸術監督を持ち回りにすることを現在検討しています。ハーレシュと私は、おそらく2015年に芸術監督の座を退き、その後は2年ごとに新しい芸術監督を迎えることになるでしょう。すでに何人かの候補者をリストアップしていますが、多彩な顔ぶれでとても興味深いリストになっています。これは、必ずしもすべてを変えてしまうということではなく、新しい芸術監督には、私たちのテンプレートの特徴は部分的にでも尊重してもらいたいと思っていますし、運営チームはそのまま継続されます。
現在、シンガポールではキュレーターのニーズが高まっていると感じています。シンガポール・アーツフェスティバルは民営化され、劇団シアターワークスの芸術監督であるオン・ケンセンが初代のディレクターになりました。でも、その次は誰ができるでしょう。そのためにも、フェスティバルのキュレーターの育成が求められているのです。フリンジフェスティバルはその手助けができるかもしれません。 - 終わりに、将来の計画についてお話しいただけますか。
-
私たちは、もう何年も地元の劇団と共同制作をしていないことに気づきました。シンガポールの劇団は、今、袋小路に入ってしまっているように思います。自分たちの俳優とだけ仕事をし、いつもの観客にいつもの場所で芝居を見せる。そのほうが楽だからです。ハーレシュと私はそうした壁を壊したいと考えています。シンガポールの演劇人と共にインターカルチュラルな作品を作りたいのです。多文化が共存するシンガポールならそれは可能です。これが私たちの現在の関心事です。永遠にそうであるとは限りませんが、少なくとも今後3〜4年はこれが私たちの仕事の中心になると思います。
そのための舞台が、フリンジと併催される「ラボ」という新しいスキームです。まだきちんとしたテンプレートは出来ていないのですが、人々が集まって即興で何かをする場にしたいというのが現時点での考えです。ハレーシュと私にはある種のジャム・セッションの経験があります。クロアチアの劇団と仕事をしていた時、相手がシンガポールに来ることができなくなり、代わりにシンガポール側のクリエイティブ・チーム──マルチメディア・アーティスト、音楽家、それに私たち二人──が集まって、映像や音楽、その他の要素を使ったいくつもの実験を行いました。最後に作品にするというプレッシャーなしに作業し、自分たちがやりたいと思ったことを実験したので、本当に新鮮でした。
私たちはもう一度それをやってみたいと思いました。しばらくしたらある段階に到達して、「OK、このプロセスを作品に仕上げてみよう」ということになるかもしれません。そうなることも、ならないこともあるでしょう。どこにも行き着かなかった場合には、そのグループは解散して別の形でやればいいのです。将来のフリンジフェスティバルの芸術監督にはこのようなラボ作品のためのセクションを設けてもらうようにお願いしたいと思っています。
ラボはTNSだけで実施するものではありません。他にも演劇的な実験のためのプログラムを持っている劇団があるので、彼らを招き、「ラボ・レポート」という全体タイトルのもとで3〜4本のワーク・イン・プログレスを上演できれば、フリンジフェスティバルの新しいに柱になると考えています。そこで上演されるものは、作品としてまとまっている必要はなく、ニューヨークのウースター・グループがやっていることに近いものになるでしょう。彼らの『へアリー・エイプ』について語る時、観客は「どっちのバージョンについて話しているの?春のバージョン?それとも秋?」と尋ねるでしょう。観客は、作品が成長していくのを見るためにお金を払います。これと同じことが私たちに起こるのはいつになるかわかりませんが、参加し、フィードバックし、作品の成長にアクティブに参加していく観客が生まれてほしいと思います。ラボ・レポートを通じて、フリンジフェスティバルがそのための踏み台になれればと思っています。2015年に最初のラボ・レポートを実施するための準備を始めています。ラボ・レポートは、金銭的な考慮や評価などのプレッシャーを受けることなく、ただ遊ぶための「遊び場」なのです! - 長時間、どうもありがとうございました。
アルビン・タン
10周年を迎える
M1シンガポール・フリンジフェスティバル
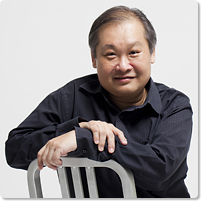
(C) The Necessary Stage
アルビン・タンAlvin Tan
ネセサリー・ステージ 創設者
M1シンガポール・フリンジフェスティバル 共同芸術監督
シンガポールを代表する劇団のひとつ、ネセサリー・ステージが2005年に立ち上げたM1シンガポール・フリンジフェスティバルが今回で10周年を迎える(2014年1月8日〜)。
聞き手:滝口 健
*1
1987年の5月と6月にシンガポール政府が秘密裏に治安警察活動を行い、22名が逮捕され、裁判を受けぬままに拘禁された事件。彼らにかけられた嫌疑は、シンガポールの現社会体制を転覆させることを目的としたマルクス主義的陰謀への荷担であった。逮捕者の中には、カソリック教会の関係者(事件の中心メンバーと目されていた)や劇団「サードステージ」の演劇人たちが含まれていた。サードステージはオリジナルの風刺劇で人気を集めており、政府の不人気な政策を批判することも多かった。
*2
2005年のフリンジフェスティバルの7つのカテゴリーは以下のとおり。
1.ライブフリンジ:演劇、ダンス、音楽などのライブパフォーマンス
2.セルロイドフリンジ:映画
3.フリンジギャラリー:展覧会
4.フリンジデモンストレーション:インタラクティブな一般向けフリーイベント
5.フリンジスピーク:トーク、討論会、ワークショップ
6.フリンジコンジャンクション:他の団体と協力して実施されるアウトリーチプログラム
7.インダストリーフリンジ:アーティストたちの交流の場。
一方、2014年の3つのカテゴリーは以下のとおり。
1.フリンジハイライト
2.ライブフリンジ
3.フリンジギャラリー
*3
シンガポール人および永住権取得者の労働者のための義務的貯蓄制度。給与月額の一定割合が自動的に控除され、特別口座に積み立てられる。積立金は年金、医療、住宅といった限られた目的にしか使用できない。シンガポールが「過保護国家」と呼ばれる一因でもある。
*4
この映像には以下のURLからアクセスが可能。
https://www.youtube.com/watch?v=3S0mEJ-aajM
劇団ネセサリー・ステージ
The Necessary Stage
https://www.necessary.org/
M1シンガポール・フリンジフェスティバル
M1 Singapore Fringe Festival
https://www.singaporefringe.com

ネセサリー・ステージ
『コンプリートリー・ウィズ/アウト・キャラクター』
Completely With/Out Character
(C) The Necessary Stage

アート・オブ・ストレンジャーズ『マウンテン』
The Mountain
(C) Phorid

村川拓也『ツァイトゲーバー』
Zeitgeber
(C) Ryouhei Tomita

砂入博史『マジュラー・シンガプラ:ツリー・プロジェクト』
Majurah Singapura_Tree Project
この記事に関連するタグ

