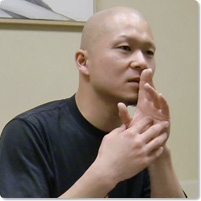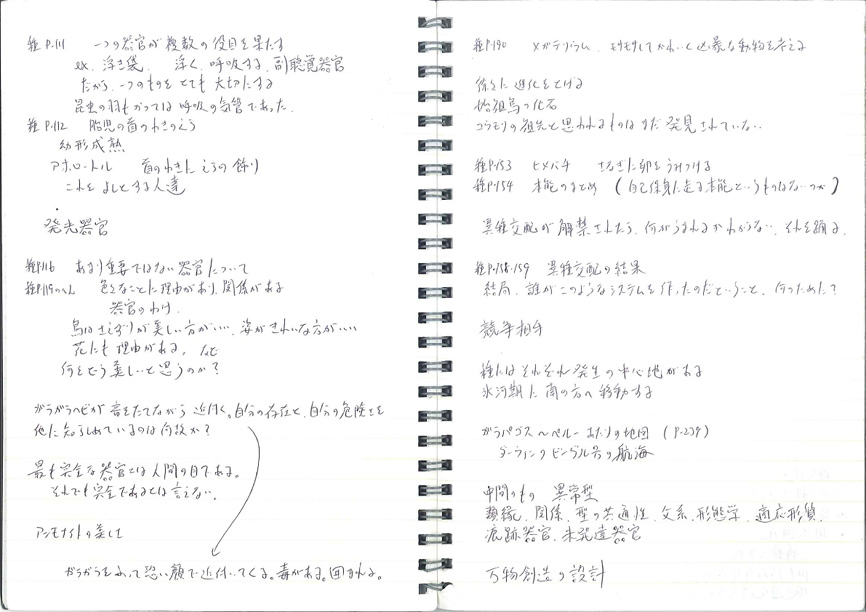身体感覚に直結するイメージを使ったワークショップ
- ビルの地下にある50席ほどの壺中天で行われる公演には独特の雰囲気があり、熱いファンを獲得しています。公演を見に行ったときに前の方に騒がしい一団がいるなと思ったら、シルク・ドゥ・ソレイユの出演者たちでした。彼らにワークショップを行っているそうですが、内容について伺えますか。
-
『コルテオ』のメンバーですね(笑)。『ドラリオン』に出演していたクラウンの方と友人だったのをきっかけに、2008年からメンバーとワークショップをしています。超一流のパフォーマーである彼らも、自分たちが知らなかった舞踏の身体の動かし方にものすごく興味をもってくれたみたいです。例えば、彼らに「動物っぽい動きをしてみて」と言うと、どうしても見た目の形や動きを真似るものになりがちです。しかし僕らの舞踏では、形から入るのではなく、四つ足の獣としての身体の仕組みや動きを踏まえて、イメージを使いながら動物になってしまいます。
あくまでもサンプルですが、「四足歩行の動物の動き」を実際にやってみると……まず四つん這いになり、「お尻の穴から玉を入れて、体を通って頭のてっぺんから出す」というイメージで背中を波打つように柔らかく動かします。次に前に進むとき、手足を前に出すことで身体を運ぶのではなく、背中につくった波の力を使って身体が前に出るようにするんです。これができると、今度は「右のお尻に入った玉を左の肩に出します」、その逆もやって、対角線上にあるおしりと肩をクロスするようにつくった波を使って歩いて行く……。
このあたりはまだまだ体操の類ですが、これができるようになると、次は本格的にイメージを身体に入れて表現してもらうわけです。例えば、「動物である自分はいまジャングルにいて、土の上で、身体の大きさはこれくらいで、蹄があって、毛が生えていて、尻尾があって牙があって、闇に潜んで歩いている……というイメージを入れてみましょう」と言うと、見た目の形を真似していたときからは思いもつかないような面白い動きがどんどん生まれてきて、「体操」が「踊り」に変わっていくんです。
師匠である 麿赤兒 は、「そもそも『踊り』は『振り』であり、振りとは子どもが動物のフリをする、その振りだ」と言うんです。だから僕たちもこういう動物の振りがちゃんとやれるように稽古します。ワークショップの時も、作品をつくる時も、こういうイメージを使って何かの「フリ」から入るという方法はよく使います。
海外公演のときなどでもワークショップを頼まれることがよくありますが、通常は、野口体操(*1)をベースとした麿メソッド(らくだ体操)から始めて、「重力に逆らわず力を抜いた方が身体は柔らかくなり効率的に動く」といったことを体験してもらって、そこから大駱駝艦の舞踏の動きに入っていきます。外国人の方にとって、野口体操はよほど興味深いらしく、翻訳したいから本を送ってくれ、と言われたこともあります。 - 大駱駝艦の舞踏の動きについて説明していただけますか。
-
麿赤兒が大駱駝艦の三本柱と呼んでいるのが、「身振りの採集(Choosing daily behavior)」「鋳態(Mold Body)」「宙体(Space Body)」です。
「身振りの採集」とは、日常の行為の下には、行為にならない、名付けられない“身振り”が存在していて、それが踊りを引き出すという考え方です。
「鋳態」とは、いわば“形”です。例えば、水をこぼしてしまった瞬間に身体が固まる、そういうフリーズされた日常の仕草のなかから踊りの形が決まっていくのではないかという考え方です。その形を決める要素は、環境や病気、職業などたくさんあります。お百姓さんであれば“腰をかがめている職業としての形”があり、老人には“腰が曲がった姿勢”とか“病気で足を引きずっている姿勢”がある。そういう日常の姿を「鋳型」に切り抜いて踊るという考え方です。「鋳型」はそもそも形があるものだけに存在するのではなく、嬉しいとか悲しいという感情にも形があります。そういう感情の形を鋳型にするために、感情のテンションを持続させて、感情を壊さないように運ぶという稽古もあります。
「宙体」は、本来実態と考えられているものを空虚なものと考え、何もない空間の方を実態として意識するという考え方です。僕達が日常的に使う「おかげさま」という言葉がありますが、その「おかげさま」で、つまり他者によって自分が踊らされる、と考えるとどうなるかということです。例えば「右手を上げる」にしても、自分の意志や力で手を挙げるのではなく、糸で右手が吊られて上がるのか、手の下にある空気が膨張して上がるのか、空気ではなくて水かあるいはゼリーが膨張しているか、それは暖かいのか冷たいのか、気持ちいいのか痛いのか……。そういう様々な要素を感じた結果として「動かされていく」ことで、踊りが生まれていく、という考え方です。鍛えた身体が中心にあって踊るのではなく、むしろ自分とは「世界の中にポッカリ空いた身体の形をした空白」であり、それが周囲の変化によって動かされている……それが「宙体」という考え方です。
ただそういうイメージを頭で理解して、わかった気になってもできない。実際に身体で、自分は何も考えないで動かされる、いわば思考停止状態で追求しないとダメなんです。だから大駱駝艦には、例えば「悲しさを伝える表現方法」というものはありません。その代わり、悲しさそのものの密度をとことん高めていく。すべてはそこから生まれてくるものであって、形だけなぞっても仕方がないんです。
舞踏との出会いと麿赤兒の存在
- そもそもどうして田村さんは舞踏を始めたのですか。
-
父が英米文学の研究者で、母も芝居好きだったため、子どもの頃からシェイクスピア劇や、夢の遊眠社などの芝居をよく見せられていて、舞台は面白いなと思っていました。中学3年のときくらいからは、一人でも劇場に足を運ぶようになりました。
そんな高校生の頃、NHK-BSで大駱駝艦の『雨月〜昇天する地獄』という公演の放送を見ました。オープニングで鎖に繋がれた男女がガンゴンガンゴンやっている姿はまさに地獄のようでしたし、セリフなんか使わないすごい世界があるなって思いました。それと前後して、美術の先生の後輩が教育実習のための模擬授業というので、偶然様々な舞踏のビデオや寺山修司の映像などを見せてくれたんです。その辺から急激に肉体に興味を持ち始めて、大野一雄さんや大駱駝艦の公演を見に行くようになりました。俳優の身体より舞踏家の身体を見ているほうが圧倒的に面白い。初めて生で麿さんを見たのは鴻上尚史さん演出の『ゴドーを待ちながら』(94年)でしたが、麿さんの存在はとてつもなく強烈でした。
大駱駝艦の若手男性だけの作品をタイニイアリスという小劇場の狭い場所で見た時に、「ああ、ここだ! なんでオレはここで踊ってないんだ!?」と思った。もう高校2年か3年の頃にはどうしても大駱駝艦に入りたいと思うようになっていましたね。僕が通っていたのは進学校だったんですが、進路相談のときに「僕、大駱駝艦という所に入りたいんです。身体を白く塗って踊るところなんですけど……」って言ったらさすがに担任の先生はキョトンとしてました(笑)。
肉体と同じくらい言葉にも興味があって詩も学びたかったし、大学には行った方がいいということになって、中村文昭先生が教えている日本大学芸術学部の文芸学科に入りました。それで大学2年の頃(97年)から大駱駝艦に出入りし始めて、3年生(98年)の時には正式に入艦して公演に出させてもらっていました。 - 踊りの経験は全くなかったわけですが、どうやって舞踏を学んでいったのですか。
-
初舞台は『死者の書』の台湾公演だったのですが、再演だったので、まず先輩から振りを教えてもらって麿さんがチェックする、という感じでした。もっこを担いでずーっと歩くシーンがなかなか上手くいかなくて、4時間ぐらい歩かされた。そのとき麿さんに、「日差しを浴びて疲れた労働者の“陰”になってみるといいんだ」とか、色んな言葉をいただきました。それでも中々上手くいかなくて僕が一人でずーっと歩いていると、先輩がスッと入ってきて僕の前を歩いてくれたりして、嬉しいながらも必死に、ひたすら歩いていたのを覚えています。
ツアーでは大部屋に7〜8人で雑魚寝するのですが、そういう集団行動には慣れなくて、しばらく「僕はここでいいです」って、押し入れで寝ていました。でも話に加わらないのもイヤなんで、顔だけは出して(笑)。
大駱駝艦は、毎年夏に白馬で合宿をしていて、参加者は35人ぐらいなのですが、半分は世界10カ国ぐらいから集まる外国人です。8泊9日で、朝から晩まで稽古漬け。そこで聞ける麿さんの話が面白くて、個人的につくっている「麿さん講義ノート」が毎年1冊出来るほど。1日目はダンスの話はほとんどしません。生け贄の話から始まったり、「舞」の語源から始まったり、「そういうところから私にとっての踊りは……」と大駱駝艦の方法論に入っていきます。麿さんはいつも新しいところにいて、変化し続けていることが凄いと思います。
とにかく皆で長い時間、一緒にご飯をつくって、稽古をやります。踊りのダメ出しをしているのかと思ったら「お前のこの味付けはなあ……」とメシの話だったり(笑)。そういう時間がすごく濃密だと思います。
かといって「家族っぽい」というのとは全然違う。家族は一番甘えられる場所ですが、大駱駝艦は一番甘えられない。つらい顔はできないし、ギックリ腰になっても舞台に立たなければいけない。そういう緊張感もありながら、すごく良い関係でいられる。それは結局、様々な人間がそれぞれの人生を歩みながらも、麿さんのもとに集まり、命懸けで踊るのだという強固な共通意識を持っているという大前提があるからだと思います。
大駱駝艦の舞台は僕にとってのはじめての衝動だったし、これが一生続くんだろうな、ということを何の疑いもなく信じていられる。僕の人生の中で、麿赤兒とは、どっしりとそこにある、山のような存在ですね。
田村一行の世界
- 今年10周年を迎える壺中天公演では、これまで18名の舞踏手が38作品を発表しています。近年は2カ月に1回ぐらいのペースで、しかもたいてい1週間以上の長期公演を行い、若いお客さんが集まっています。田村さん自身もこれまで舞踊批評家協会賞新人賞を受賞した『雑踏のリベルタン』、海外にも招聘された『血』(08年)、『オママゴト』の3作品を発表しています。
-
僕が入艦してすぐ若手が交代で作品を発表する「戯族シリーズ」が始まり、2001年から本格的な「壺中天公演」を行うようになりました。舞踏手によってスタイルはそれぞれで、「身体があればそれでいい」という人もいますが、僕は古本屋などを回っていろいろな資料を集めてから緻密につくるのが好きですね。「頭でっかちになるな」と言われますけど、資料に埋もれてあーだこーだ考えているときはとても幸せな時間です。
例えば今年3月に福岡で再演される『血』は、自分のルーツに挑みたいと思ってつくった作品ですが、ダーウィンの進化論から遺伝子関係の本までとりあえず揃えて、ガラパゴスの分厚い写真集を見たりしながら考えました。その結果、舞台上に生命系統樹まで出てきた(笑)。
当然のことではありますが、作品を創るということは、振付や演出、出演だけでなく、美術、衣裳、音楽に至る細部まで考えねばなりません。要はすべてにおいて引き算足し算の加減が重要で、その按配を探ることが、創作の苦しみでもあり楽しみなのだと思います。例えば衣裳を考えるにしても、大駱駝艦の場合、「白塗り・裸」が最強の衣裳となりますので、そこに何かを着せると余分な説明になる恐れがある。でも、「じゃあ全員裸!」となると安易すぎる。作品や踊りにとって何が必要なものか、何を削いでゆくのか、そこをいつも試行錯誤しています。音楽はここ2作品、和太鼓奏者の林英哲さんやピアニストの谷川賢作さんと一緒に活動されている尺八奏者の土井啓輔さんにつくっていただいています。「一行さんの作品は全部曲を書きます」と言ってくださっていて、お願いしています。コンピュータでつくる曲の一音一音にも魂を吹き込むように作曲なさっていて、僕が作品のイメージを伝えると、その世界観を的確に掴んで曲をつくってくださいます。今後も、2人だからこそつくれる世界を、もっと模索することができそうです。
僕は詩も書きますが、ダンサーには作品のイメージを詩に書いて伝えることもあります。舞踏は、いわゆるダンスのような「振付家が振りをつくって、それを写す」というのとは根本的につくり方が違うと思います。例えば僕は、言葉や絵で振りを記録する「振り帳」というものをつくっていますが、「立っていて、揺れて、しゃがむ」だけのシーンに3頁ぐらい使います。それは、単なる動きの記録ではなくて、立っている時・揺れている時に自分の中で何が起きていたか、どういう感覚だったか、をメモしておくものです。動きではなく、そのときの感覚を再現するための手掛かりとして、言葉で残す感じです。みんなそれぞれの方法で、このようなノートをつくっています。
僕の場合は、日頃から気になることを書き留めています。例えば「ニワトリの卵は4日目に弱る」とか(笑)。何でもいいんです。すぐには役立たなくても、のちに「卵の中」の振りをつくる時、何かおかしいなと思ってノートを見ると、「あ、ここで弱ってないからおかしいんだ」と気付いたりする。また胎児が成長していくといった振りのときも「あれ、上手くいきすぎてるな」と疑問を持ったときにこの言葉を思い出せば、「1回弱らせた方がいいのかな」というヒントになったりします。
振り帳は、振付家が演出ノート的につくったものと、舞踏手が自分の身体を動かすために記録したものとでは違ってくることもありますが、それぞれの身体にとってリアリティのある言葉ならば、別に違っていてもいいと思います。欧米のダンサーから見ると「それでダンス作品が成立するのか?」と驚きますけどね(笑)。
ただ大駱駝艦の舞踏手同士には、練習や合宿などの共同生活を通して、身体的な共通言語があります。例えば「ぐにゃんで4つ」って言ったらそれだけでこういう感じ、と通じちゃいます。そうするとあとはその時々の「間」の話になってきます。「間」で身体が決まってくる。例えばビンタをされて、1秒で振り向くと「なんだよ!」となりますが、4秒かけて振り向くと「え?」という感情になるかもしれない。しかしそれは「1、2、3」というカウントを取るだけではダメで、ほしいのは「パンと張られて生まれる感情」なわけです。単なるカウントではなく、その「間」に何を飼うか、何が潜んでいるのか、何が動くのかということを追求しなければいけなく、僕らの中にはその部分での共通の認識が、かなりあると思います。だから新人は、まずそのあたりの感覚を掴むことが必要になりますね。
作品を創作するときに、構成や人への振付は順調に進んでも、自分のソロ・パートには常に苦労してしまいます。麿さんは「人を振り付けるみたいに自分も振り付ければいいじゃないか」と言うんですけど、それがなかなかうまくいかない。自分を他者として扱うことは、何事に置いても難しいことです。
麿さんにはだいたい本番1週間〜10日前に、通し稽古の状態で初めて見てもらいますが、非常に緊張します。壺中天で作品をつくった人は皆、稽古場に向かう道で「あのトラックがオレを轢いてくれたら稽古場に行かなくてすむのに」(笑)って思うみたいですね。そのくらいの精神状態にまで追い込まれても、それでもやっぱり作品をつくりたいんですから、因果です。
ジョセフ・ナジとの出会い
- 田村さんは壺中天のメンバー3人と共に2006年のアヴィニヨン・フェスティバルのオープニングを飾った日仏共同制作公演、ジョセフ・ナジ振付・演出による『遊*ASOBU』に出演しました。また2008年に文化庁新進芸術家海外留学制度により3カ月間フランス留学した際にもナジのカンパニーが引受先でした。彼との出会いは、どのようなものでしたか?
-
『遊*ASOBU』の時、ナジのワークショップにオーディションを兼ねているとは知らず、勉強のつもりで気軽に参加したら、ナジが選んでくれたんです。アヴィニョン・フェスティバルで初演してずいぶんツアーもしました。
彼は決して僕に「舞踏をやれ」とは言わなかった。『遊*ASOBU』のとき、ナジはアンリ・ミショーを元にして「象が溶けて蟻になる」とか、けっこうムチャクチャな題を出して「じゃあどうぞやってみて」という。僕は「オレは耳をやるからお前は鼻をやれ」「それがこういうふうにグニャんと溶けて蟻になろう」と、わりとそのままやりました。頭で考えるのではなく、言葉をダイレクトに身体に移した。彼はそういうのが大好きだったみたいで、すっかり意気投合しました。
例えば僕らがそこで「日本人」や「舞踏」というのを表現したらダメだったと思います。僕らの身体に染みついている日本の文化や風習というのは幾らでもあって、それは放っておいても自ずと出て来くるものです。だから自分たちの持っているリアリティをそのまま突き詰めていけば、それがオリジナリティになっていくんだと思います。ナジが欲しかったものは“舞踏的”な何かではなく、“田村一行的”な何かだったわけだと思います。
ヨーロッパでは、ナジ自身が舞踏っぽいと言われているようなのですが、それは何故かということは随分考えました。何故なら僕自身もそう感じたからです。だからこそ、ナジが持つ舞踏的要素を追及することは、自分自身の舞踏を見つめることにも通じると思ったんです。まずはナジの故郷の存在はとても大きいと思いました。僕は東京生まれの東京育ちで、麿赤兒の奈良であったり、土方巽の秋田のような原風景はありません。今では自分の原風景は東京だと言えるようになりましたが、ある時期、それで舞踏ができるのか、みたいな妙なコンプレックスがありました。そういうこともあって、どうしてもナジの原風景を見たいと思い、お願いして彼の故郷に連れて行ってももらいました。
ナジの故郷はハンガリーとセルビアの国境付近にあるカニージャという美しい村ですが、世界でも一、二を争うくらい自殺者の多い場所だそうです。しかも自殺の方法が壮絶で、「尖がった木の枝に飛び込んで自分の喉を貫く」とか、まるで死に方を競い合っているようです。
実際にカニージャに行って、その雰囲気や空気感を感じて、土地の匂いを嗅いで、地元の人達と接した後でナジの作品を見ると、すごくそれが伝わってきた。例えばカニージャで自殺した、ナジの友達の詩人へのオマージュとしてつくったソロがあるのですが、雨がしとしとと降っていて、その隅でナジがずっと踊っているわけです。本当に遊ぶものがなくて、彼はそうやって遊んでいたんだなというのが伝わってくる。その詩人はドアノブで首を吊って亡くなったそうですが、あるシーンでナジは何度もそういう動きを繰り返し始める。その作品の中で、ナジもその友人と同じ絶望や、死の決意を体験し、でもその上でナジは死ではなく生へ向かう。憤りや苦しみを乗り越え、友の死を浄化させようというナジの悲しくも強い思いがひしひしと伝わってくるんです。……そういうふうに人間の生き様をさらけだすところや、故郷の原風景と一生付き合おうとするところも、確かに舞踏と共通しているのかなと思いました。
研修の時、「オレはナジから舞踏を学ぶためにフランスに来たんだ」と言ったら、みんな驚いていました。向こうの人がバレエをやっているように、向こうの人は日本人のダンサーはみな幼少期から舞踏をやっていると思っていますから、ナジから舞踏を学ぶといっても何のことだかわからなかったみたいです(笑)。でも、じゃあ逆に舞踏って何ですか?って感じですよね。ナジは作品によって表現方法が全然異なっているし、そもそもこれはダンスだとかあれは彫刻だとかの表現の境界にこだわっていない。僕も“舞踏”をやろうとしているわけではない。自分がやっているのが何だったかは見た人が決めればいい。かつて自分のやった仕事をなぞるのではなく、常にその時の自分のリアリティを追及すれば、それこそがオリジナリティになる。そしてその自分へと向けられた扉は、他者への普遍的な扉へと繋がる。ナジにはそういう意味で共感しました。彼は間違いなく僕の人生に影響を与えたひとりです。
舞踏的なるもの
- 大駱駝艦そして壺中天は、白塗り・裸体の創生期の舞踏的なスタイルを強固に受け継いでいます。しかも先達の功績を安易に享受するのではなく、若い舞踏手がそれぞれの世界を追求し、何より観客を魅了する身体性を持ち続けています。これは驚異的なことですが、その秘密はなんでしょうか。
-
今ここにある自分の身体は、少なからず現代の様々なことに侵されているとは思います。しかし“舞踏”とはもっと精神的なもの、普遍的なものだと思います。先ほど言った「原風景に戻らないと舞踏ではないのか」とか「土方が死んで舞踏は終わった」とか「外国人がやるものは舞踏じゃない」ということは絶対にありません。絶えず「太古より連綿と引き継がれてきた、今ある自分の身体で何を踊るのか」ということの連続が舞踏であり、それがこれからも自分が追求していくことなのだと思っています。
だからといって「これが舞踏ですよ」と押し売りをするつもりは全くないし、例えば僕のことを面白がって起用してくださる演出家も誰一人として「舞踏をやってください」とは言わないです。僕の中に染みついている踊りのボキャブラリーは舞踏流ですし、大駱駝艦風味ですから自ずとそういうものは染み出てきてしまうものです。だから「田村にこういう場所と役を与えるとどうなるか」というのを面白がってもらっているように思います。
舞踏は、舞踏をやろうとした瞬間に舞踏じゃなくなる、と思うんです。だからこそ、常にどうやってそこに存在し続けるかを問われ続ける。なので「自分がここでバーンと立っているだけで、周りで汗だくで動いている連中よりも強く存在してみせる」という意識の張りを常に持ってやっています。
麿さんも言葉を使い分けていて、“舞踏”という言葉を使う時と使わない時があります。僕は「舞踏を引き継ぐ」というよりも、麿赤兒の追い求めているものを追いかけ続けたい、というのが素直な気持ちです。だからといって麿赤兒をなぞっても、それは亜流にしかならない。壺中天の若手がどんな試みをやっても、麿さんはその世界を超越してしまう。その発想の根幹を盗むというよりは、その生き様を楽しみながら体験してゆきたいです。麿さんには常に驚きと納得を繰り返す。だからこそ飽きないし目が離せないのでしょう。実際に、「あの時に麿さんが言っていたのはこういうことだったのか」と数年後に納得する瞬間に出会うことが多々あります。それがこの10何年か常に繰り返し起きているので、ああ絶対に辞められないなあ(笑)、と思うわけです。
以前、先輩がつくった作品では、本番直前に麿さんの指示で白塗りをやめたこともあります。その作品にとっては白塗りが余分だ、と判断したわけです。あるときは電車の中で麿さんが「なんでお前眉を剃ってるんだ?」と(笑)。「えっ?みんなだって剃っているじゃないですか」というと、「オレは生えてるじゃねえか」と言う。自由というか、答えがない(笑)。格好を付けているわけじゃなくて、本当にそういうところに行ってるんですよね。
そもそも舞踏は既成の価値観に対するアンチみたいなところから始まり、次に舞踏に対するアンチが生まれて……というのを繰り返す歴史があったと思います。だから今の世代、僕はあえて「いのち懸けで芸術やっています」って言ってるんです。これが芸術じゃなくて何なんだと。時代ごとに流行りすたりはあるでしょうけど、そんなことには関係なく、「人類が初めて火を見た時の驚き」を踊りにするような、人間の本質や普遍的なところを突き詰めて、これからも踊っていきたいと思います。