- 2001年から大駱駝艦の若手が作品をつくってアトリエで発表する「壺中天」シリーズがスタートしました。若手の育成についてはどのように考えているのですか。
- あまり深く考えてないけど(笑)。いつも僕の振付けでやっていると、彼らなりに思うところもあるだろうし、蓄積しているものもあるだろうから、まあ、何かやってみろと。マンガばっかり読んでるのかと思ったら、そうでもなかったりして、僕とはズレがあるけどそれが逆に新鮮ですね。ただ、壷中天をやっているのは、5年、10年経験のある連中です。
- 麿さんの振付けとどういうところが違いますか?
-
うちの舞台様式みたいなものはある程度踏襲しつつ、内容というのは本当に全部まかせている。振付け、美術、照明、音楽とかいろいろひとりでやるので、それをどうセレクトするかでもの凄くセンスが問われますね。僕の焼き直しみたいなことをすると不機嫌になるから(笑)、かなりプレッシャーがかかっていると思いますよ。
僕にとっても「こういうことを考えているのか」と大変勉強になる。それと、20代、30代の若い奴と話すのに、作品を話題にすれば対話が成り立つみたいなこともありますし。僕の振付けは抑圧だから、忸怩たる思いでやっているのが彼らの中でどう醗酵しているか、それが出るのは面白いですよ。稽古の途中は見ないようにしていて、彼らが自分でそれなりに仕上げて、本番1週間ぐらい前にちょっといじくる。ただ僕の感性のみで「ここが面白い」「ここは面白くねえ」「削れ!」というわけにもいかない。その辺はせめぎ合いですね。 - スタイルからあまりはずれると駱駝艦ではなくなると思いますが、その辺の境界線はどこにあるのですか?
- そこが難しいですね(笑)。僕なりの許容範囲があるというか、こちらも相当「デタラメ」をやっているから、それほど驚くことはないですけど。「デタラメ」というのがどういう意味かを語ることはできますよ。
- 「デタラメ」の説明がつくのですか?
- つきますよ。「デタラメ」というのは僕の基本的な方法論ですから。ある日、何気なくマッチ棒を投げたら、確率的に「立っちゃった」みたいな、そういう瞬間みたいなところで楽しめるか、生獲りにできるか、というのが僕の言う「デタラメ」。そういう「デタラメ」は、どれだけ心身(こういう言い方をすると言葉が違ってくるけど)がそれを掴まえているかということで見えてくるものなんです。「ふざけてんじゃねえよ」って言うほど見えてくる(笑)。ふざけててももの凄い。そういうものさえ見えてくれば、これは相当面白いと思います。
- 大駱駝艦として、ある種のスタイルというか文体というか方法というか、それを共有しているとして、大野一雄さんや山海塾にも独自のスタイルがあるとすると、じゃあ舞踏って何なのでしょう。
- 結局「舞踏は舞踏の中にない」ということになってくる。あやふやながら僕には僕のスタイルというのがあって、山海塾とも笠井叡とも違う。山海塾とは多少共通点があったにしても個々に違うし、そういうスタイルは邪魔になるのでみんな何とかそれを振り払って違うところに行きたいけど、一歩踏み出しては迂回して戻ってくるみたいな、常にそういう分岐点に立っている。とはいってもそこから抜けてしまおうとかいうのではなく、包含しながら進み、密教的に増殖していく。その時間なり場所を司るというか、つまりは自分自身をどう司るのかということが舞踏にはあるけど、だからといって舞踏の定義となるとそういうのでもないから、難しい。
- とは言っても、観ている方は舞踏として何らかの受け取り方をしてしまう。
- 復元能力に関わるところについてということですよね。そこにはそれなりの自負はあって、言葉にしろ、身体の動きにしろ同じ感覚が司っていて、それは何か?というと何でしょうねえ(笑)。言葉の言霊だとか、ある種の始源の強さだとか言うと、民族学みたいな話になるし。まあ、そういう面もあるとは思いますが、身体の置き方、立ち方によってあらゆる疑問が解消するというか、そういう存在の仕方というのがあるんじゃねえかってことですよね。
- それは、東京でも、アメリカやソウルでも変わらないだろうと?
- そう、それはありますね。だって、海外の出し物を観ても、文学を読んでもそれなりにわかるでしょ。細かいところは判りませんよ。でもビックリしているとか、泣いているのは悲しいんだろうとか、情念的なものは判ります。まあ、人間なら一応情緒はあるだろうというのが前提ですけど。持ってないヤツもたまにいるから(笑)。
- 情念的、情緒的なものが、麿さんの一番根っこにあると考えていいのですか?
-
かなりあります。「あっ!」って驚く時は、世界共通で同じ顔をするだろう、とかね。そういうところで、まず共通認識が生まれると思うんです。それから、「その悲しみについてどう思う?」とか、「その悲惨さについてどう思う?」とか、こっちの問題として返ってくる。
まあ、僕の場合はかなり虚無的になってくるんだけど、ある人にとっては「一緒に泣こう」とか、「平和のために行こう」となるかもしれない。そこにまた踊り手の立ち方がどうかということが出てきて、「世界を救おうと思ってやってるわけじゃねえしな!」となったり(笑)。
そこでの我々の立ち方は、カッコ良く言えば、何物かの「容れ物」であり、つまりは生け贄(サクリファイス)として存在している。舞踏人種というのは、芸術とかっていうことではなく、生け贄(サクリファイス)としての肉体の存在を証明するものでして、「他に我々は何も言うことはありません」っていう方向にいくのが、僕の癖なんですけどね。
- なるほど。じゃあ情緒や情念がどっかにあったとして、それと身体がうまく繋がらないといけないですよね。その繋がり方を学ぶメソッドとして野口体操があるのでしょうか。
-
身体をひとつの流動体、原始生命体として捉える野口体操というのは、ある程度のところまで方法論としてあって、大駱駝艦の合宿でもはじめに野口体操とはこういうものだという説明をしてやらせるけど、それだけではちょっと違うような気がする。野口さんのような身体論は理想論としてはあるけど、そこに異物をどう放り込むか、ということが私にはあります。
我々は排気ガスを吸ったり、たばこを吸ったり、そういうとんでもないものを自然に受容しているわけですよ。そういういろいろ入り込んできてしまっているということからは逃れられない。
こういう風に話していくと、舞踏というもののある種の姿がブワーっと出てきそうな気はするんだけど。舞踏という定義はもともとそんなになくて、たとえば異教徒をうまく巻き込んで、その儀式をちょっと入れちゃったりとかしてるうちに、いつの間にかミックスして、それで形づくっていくような。そういう異教徒的なもののリアリティもまたこっちに欲しいというところがあるんですよね。肉体というのを仕事にしちゃってるから、それだけどん欲になっている面もあるとは思いますが。
- そういった、感じ方でも考え方でもいいですが、それこそ舞踏が始まった50年代、60年代と現在では、変わってきていると思われますか?
-
身体をいじくっていると、多かれ少なかれどっかで(過去と現在は)オーバーラップしていますから。
- そういう意味では、時代など関係なくて、「肉体という限界」と言ってもいいのかもしれないけど、それが共通のものとしてずっとあると?
-
そうそう。そういうある種の認識の上に立っているものであれば、舞踏と言えるんじゃないかとか。まあ、若い人には、「そんなこと関係ねえよ、俺は元気だ!」みたいなことが一方ではありますけどね(笑)。
- そういう身体が、50年代とか60年代にわざわざ発見されたのはなぜですか?
-
それは出るべくして出たということだと思います。それ以前にそういうことは意識されないものとしていっぱいあったけど、ある時期、そういうことを忘れるような状況があって「何かおかしい」と。それがたまたま60年代だったということ。まあ、あんまりその辺を言っちゃうとね(笑)。
- 高度成長とか言っちゃうと単純になりすぎる(笑)。
-
それもひとつにはあると思いますよ。戦後イケイケってやってきて、ある種の疲れもあったかもしれない。ふと気が付くというか、「嫌だ」「後ろ向く!」となった。それまで後ろを向くということは国賊だったから(笑)。その辺は、僕らより土方(巽)さんや大野(一雄)先生の方がヒシヒシと感じていたんじゃないですか。「何ものにも入ってやらない!」「どこにも属さねえ」「輪っかの外にいなければ信用できねえ」みたいな、強い意志があったと思います。
大野先生の方が意識的、論理的で、土方さんはもっと無意識的でかつ強い直感力で「輪っかになんか入れねえ」っていう、疎外感みたいなものを感受性として一番もっていたように思います。「嫌だったら嫌だ!」みたいな女性的なところがあって、「これは強いぞ」とよく言っていましたから。女に、「嫌だったら嫌だ」と言われたら何度説明してもダメだ、とりつく島がねえ、みたいな(笑)。 - 土方さん、大野先生もそうですが、天児さんも麿さんも、みんな言葉というものをとても上手く使っていると思います。実際に舞踏の振付けの場でもたくさんの言葉を投入してイメージをつくっていく。その辺りのことをお伺いしたいのですが。
-
基本的に僕が使う言葉というのは“方便”ですよ。身体なんか鋳型みたいなもんだからそれだけでは動かない。ひとつの方便として言葉、インチキな言葉でも何でもいいんだけど、それを使うことによって身体ってものが反応するんです。僕の場合、身体が動くためにはどんな言葉を使ってもいい。だからといってできあがったものがその言葉であるということは全くなくて、もっと違うものであるところに意味がある。
そういう言葉を身体が飲み込んで、そんな言葉なんていうのは一切消えて、そこには身体のあり方、動きも含めて、あり方みたいなことだけが存在する。
- そういう言葉のあり方のようなものは、若い人にも継承されているのですか?
-
いや、なかなか(笑)。言葉が方便にならなくて、平板な意味としてとってしまう。「やわらかく!」「かたく!」「その連続!」とかって言うと、こうやれっていうのとか、じゃあグニャグニャなのか、そうでもないのか、説明してるのか、違うのかって話になりますわな。だから言葉によって逆に身体が変なところに行ってしまうことになる。
- 麿さんたちが使っている言葉は、指示というかインストラクションじゃないんですよね。
-
方便なんですが、若い人には、まだやっぱり言葉に対する信用があるというか…。「行け!」って言ったら行ったりしちゃうんですよ。
- それって小説を読まないからじゃないですかねえ(笑)。ところで、先ほどからの話を積み重ねていくと、まさに身体というものは変わらないというのは事実としてあるけれど、言葉についての認識にはかなりのズレが生じていることを踏まえて、麿さんが若い世代について考えていることってありますか?
-
踊りとして面白いというところに納まればそれはそれでいいんじゃないかと。僕の手助けがなくても、そういうふうなところにタッタッタッタッと行ける、ある種の手練れになってくれればいいとは思っています。
我々の仕事として身体の置きっぷりというのがあって。何もしないで板間に立っている意味みたいなことなんだけど。何もしなくても、それこそ言霊ならぬ“体霊(タイダマ)”がウワーンとあって、止まっていてもその波長が変えられる。要するに、身体の一種の多面性(多様性)が、見てる方にいろいろな方向性をもって伝えられるようになってくれれば。「なんじゃこりゃ」「見たことねえぞ」っていうところが最初だとは思うんですが。
- 野口体操的なものからはじめて、「見たことねえぞ」っていうところにいくにはどのように進めていくのですか。
-
野口体操というのは肉体概念みたいなもので、僕自身は最初に教わった時にとてもショックを受けた。体操はカチッとしたものじゃなくてグニャッとしたもの、身体というのもグニャッとしたものという、自分が身体についてもっていたそれまでのイメージの全く反対のベクトルを触発された。
でもじゃあただグニャグニャしてればいいとかという、そうじゃない。袋という身体の器が固ければどうなる?という疑問がでてくる。どんぶりのようなカチカチの器で中味が揺れてるとどうなる?とか、凍っちゃたらどうなんだ?とか、いろいろと投げかけて身体を動かしていく・・・。
- 先ほど、言葉は方便であると言われていましたが、言葉のイマジネーションがなければ踊ることができない、身体をつくることもできない、ということですか?
-
そうですね、できませんね。重心を低くするというのでも、色々な例を出します。剣道でも柔道でも、腰が抜けていると攻撃もできないし防御も弱い。そういう武道の立ち方の例とか。
そしてそのイメージから飛び出る。我々は武道じゃないし、勝ち負けでやっているわけじゃないですから(笑)。そこで今度はヤクザのケンカの仕方っていうのが出てきてね。型にはまった動作だと、どっちが強いかわかるけど、ギャーってわけのわかんない暴力ででてきたらわからない。ウワーとか変な踊りでもされたらそっちが勝っちゃうかもしれないみたいな(笑)。
でもまあ、そういうことを言っていてもそれも方便ですから。そういうことを言っても、なおかつ、言葉は我々の身体にとってはどんどん消えていってしまうものなんです。同じようなことをさせるのに、他の例えをだしたっていいわけでしょ。例えはいくらでもあるんだから。
- ということは、最初に身体についての考え方をある程度変えたら、あとは実際に色々な言葉やイメージでエチュードをやる。
-
言葉とイメージだけでいいのか?という判断もあるんですよ。だんだん宮本武蔵とか、塚原卜伝みたいな話になってきた(笑)。剣豪が自然体でいても隙がないみたいな、それも一つの形だとか言う話し。僕がよく言うのは、「存在感があるというのもひとつの技術だぜ」ってこと。ただいればいいってものじゃなくて、グニャーっとしてても何かがあるというか。そこに行けるための技術論というのはあると思います。
- 舞踏の作品には一定の時間の流れが必要です。それはどうやって決まっていくのですか?
-
面白ければどんどん続けてやるんです。とは言っても、面白い、面白くないをどこで決めるのかが問題ですが、具体的にやっていくと、1シーン大体10分か15分の単位になります。
今は、やっている方より見る人のスピードの方が速くて、パッと見たら判っちうみたいなことがある。別に駆け引きでやっているわけじゃないから、そういうのに対処する必要があるかどうかは別問題ですけど。
ただ、時間を持続するためには、それはそれで駆け引きの手だてというのはあると思う。僕の中では一種の「間」ということになるんですが。静止でなくてもいいけど、静止画をつくる、間をつくるみたいなことがあります。音楽の言葉で言うと、シンコペーションがけっこう好きなんですけど、そういうある種のショック、ウッとなるという西洋的な間。ウッといくかと思ったらクッとなるみたいな、不連続な連続が持続のポイントだったりします。ピアニッシモの中にも「クッ」とか「バーッ」とかあって。むしろゼロにできるだけ近いところでゼロから1にいく方が、100から101にいくより客をグーッともっていけるみたいなところがありますね。
- 音楽についての考え方は?
- 微妙ですよね。「良い音さえあればい」ということになるんだけど、情緒的な音は特定の感情を彷彿とさせるからよくなくて、だからなかなか邦楽は使えない。野外でやるときは音楽としての音があると面白くないけど、劇場では完ぺきに音がないと僕でさえ不安になってくる。なかなか「沈黙も音である」という境地にはいけないですね。
麿赤兒
代表作「海印の馬」で韓国公演
麿赤兒が語る舞踏の今

麿赤兒Akaji Maro
1943年奈良県生まれ。早稲田大学文学部演劇科を中退。劇団「ぶどうの会」を経て、1964年に土方巽に師事するのと平行して、唐十郎とともにアングラ劇団、状況劇場を設立。デモーニッシュな俳優として活躍。1972年、演劇と舞踏の新たな融合を目指して「大駱駝艦」を旗揚げ。以来、社会的な規範からはみ出した肉体や情念も人間の本性として肯定的に捉え、舞台上で「もののけ」として甦らせる、スペクタクルでユーモラスで物悲しい作品を「天賦典式」と名付けて発表。また、俳優としても活躍し、多数の映画に出演。1982年にアメリカン・ダンス・フェスティバルで海外デビューして以来、海外公演多数。
■大駱駝艦 公式サイト
http://www.dairakudakan.com/
1959年に発表された「禁色」によって、土方巽が日本の文化に根ざした表現主義的なダンスの試み(後に暗黒舞踏と称する)に船出してから、40年余り。白塗り、がに股、剃髪、不連続な身振りに象徴される日本の舞踏は「BUTOH」として国際的な市民権を得たが、解散したカンパニーも多く、また、若いアーティストたちはコンテンポラリーダンスに新しい身体表現の可能性を見いだすなど、舞踏を取り巻く環境は大きく変わってきた。
そんな中、結成から30年を越えて、40名近いメンバーを抱え、なお第一線で創作活動を続けている麿赤兒と大駱駝艦。カンパニーに所属する若手が振付・演出・美術・音楽までひとりで行なうアトリエ公演を2001年から連続企画するなど、新世代の舞踏の誕生も予感させる。
日韓友情年を記念して、6月25日から7月14日までソウルで開催されるダンス交流フェスティバルに招待され、代表作『海印の馬』で初めて大規模な韓国公演を行なう麿赤兒に、舞踏的なるものについて話を聞いた。
聞き手:小沼純一
壺中天
2001年5月からスタートした、壺中天公演は振付・演出する舞踏手がすべてを決め約1カ月で作品を創作し、必ず振付をする舞踏手のソロ部分を入れることが決め事となっている。2005年6月現在までに若林淳、村松卓矢、向雲太郎、石川正虎、田村一行、八重樫玲子、兼沢英子、小林裕子、今井敦子等によって20作品を発表し、6作品の海外公演を行い高い評価を受けている。
野口体操
体育教師だった野口三千三が、1960年代に体操による人間改革を目指して創始した実技。「生きている人間のからだは、皮膚という生きた袋の中に、液体的なものがいっぱい入っていて、その中に骨も内臓も浮かんでいる」という独自の人間観に基づいて提唱された「野口体操」は、体操界では異端視されたが、演劇、美術、音楽など芸術の世界に多大な影響を与えた。

『海印の馬』
Kaiin no Uma
撮影:山崎博人
1982年に初演。アトリエ豊玉伽藍(1985閉鎖)で1980年に月替わりで行われた連続公演『十二の光』のハイライトシーンで構成。幻の馬を求めて彷徨う麿がさまざまなもののけと出会うというスペクタクルな作品で、大駱駝艦の舞踏の醍醐味を堪能できる代表作。




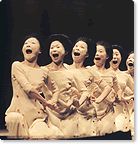
この記事に関連するタグ

