フッツクレイ・コミュニティ・アーツ Footscray Community Arts
https://footscrayarts.com/

フッツクレイ・コミュニティ・アーツ外観

円形劇場(Amphitheatre)

Roslyn Smorgon Gallery

スタジオ
先住民や移民のコミュニティとの対話を促進する
フッツクレイ・コミュニティ・アーツ
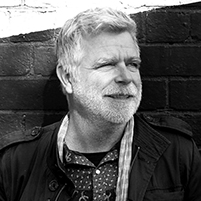
(C) Footscray Community Arts
フッツクレイ・コミュニティ・アーツ チーフプロデューサー
メルボルン郊外にあるフッツクレイ・コミュニティ・アーツ(1974年開館)では、先住民アドバイザーを設けるなどの取り組みにより、アートを媒介にして先住民や移民コミュニティとの対話を促進してきた。
フッツクレイ・コミュニティ・アーツ Footscray Community Arts
https://footscrayarts.com/

フッツクレイ・コミュニティ・アーツ外観

円形劇場(Amphitheatre)

Roslyn Smorgon Gallery

スタジオ
*1 オーストラリアでは、先住民社会との協調にむけた活動の一環として、公の場で発言をする際などには、その活動を行う土地の先住民族たちとその祖先たちに敬意の言葉を述べることから始めることが推奨されている。
*2 白豪主義は、オーストラリアにおける非白人入植を制限しようとする政策。その一つとして、1901年12月23日に「移民制限法」が施行された。この法律は、新しく設立された連邦議会に提出された最初の法律の一つで、オーストラリアへの非英国人の移住を制限することを目的としていた。この法律が制定されたことで、白豪主義が正式に確立された。この政策は1966年に廃止された。
*3 ゴフ・ウィットラム(1916―2014)はオーストラリアの政治家、第21代首相(1972-75)、労働党。フェア・ゴー(fair go)はウィットラムが選挙活動で掲げた「Give Gough a fair go」というスローガンがもとになっており、平等主義の精神を表す言葉として浸透した。
*4 Reconciliation Action Planは、オーストラリアの各地方行政が設置する先住民社会との和解・協調に向けた活動計画。企業や組織、個人などさまざまな規模で実践できる行動指針が示されている。冒頭でダンさんが述べた祖先や土地への感謝の言葉もその一つ。
*5 ソングラインとは、アボリジナルの先祖がたどってきた軌跡を示す道すじ。大地または空に架かる道として、歌や物語、ダンスやペインティングによって語られる。
*6 ウミンジカ・フェスティバルは2022年10月22日、3年ぶりに開催された。ウェルカムセレモニーでは、新しいフクロネズミの皮で作ったマントを「エルダーズ・イン・レジデンス」であるラリー・ウォルシュおじさんとナーウィート・キャロリン・ブリッグスおばさんに贈る重要な儀式が行われた。300人ほどの参加者は1日を通じて、アボリジナルのアートやクラフトマーケット、ライブパフォーマンス、DJ、食べ物を楽しんだ。イベントはアボリジナルのコミュニティにも歓迎され、フッツクレイ・コミュニティ・アーツの掲げる「ファーストネーション・ファースト」ポリシーへの熱意を、実践を通じて示す結果となった。
*7 美術・舞台・映像・文学・放送などのアーティストおよびそこで働く人を対象にしたリーダーシップの育成プログラム。
*8 2016年に創設され、隔年で実施されているヴィジュアルアートを対象にした賞。18歳以上のオーストラリアのアーティストを対象にしたメインのフッツクレイ・アート賞(大賞、西部のアーティストを対象にしたローカル賞、フッツクレイ・コミュニティ・アーツでの滞在創作・展示ができるレジデントアーティスト賞)、メルボルン西部の小・中学生を対象にしたヤングアーティスト賞があり、受賞作とヤングアーティスト部門の応募作全てを展示する展覧会を開催。
*9 ドリームタイムとは、世界の創造を表す言葉。アボリジナル独特の時間・歴史・記憶の感覚を伴う。
*10 アボリジナルの人々には読み書きするための文字がなく、点を多用した模様などの絵によってさまざまな情報を伝えていた。1971年にイギリス人の美術教師であるジェフリー・バードン(Geoffrey Bardon)の指導によりキャンバス地にアクリル絵の具で絵を描きはじめたのがアボリジナル・アートのはじまりとされる。その特徴的な画法がドット・ペインティング(点描画)と動物の骨格などが透けたように描くエックスレイ・ペインティング(レントゲン画法)。
*11 シチュアシオニスト(状況派)は1950年代からフランスをはじめヨーロッパ諸国で勃興した文化的・政治的運動。大量消費が示すような社会・政治・文化・芸術・生活といった既存の体制に反発し、それに支配されない解放された生の瞬間を生み出す「状況の構築」を目指して表現活動を行った。パリの五月革命(1968年)における若者の活動や70年代のイギリスのパンクなどの活動にも影響を及ぼした。
*12 ダンさんのアボリジナルの曽祖父には二つの家族があり、一つはアボリジナルの妻との家族(ブラック)、もう一つはイギリス人妻との家族(ブラウン)だった。ブラックの家族が体験したトラウマは、植民地時代のアボリジナルの人々を対象にした「盗まれた時代」を作り出した差別的法律(アボリジナルの子どもを両親から引き離す政策、文化や言語の統制、土地権利の没収、移住の強要など)によるもので、ブラウンの家族が体験したトラウマは、アボリジナルとしてのアイデンティティを隠し、否定し、主流の文化に同化して差別を避けて生きのびることを選択したことによるものだった。
この記事に関連するタグ