
『F/BRIDGE』
ロンドン・コロネット劇場「Electric Japan 2022」公演(2022年5月)
「モノと身体」の関係から生まれるダンスで
社会を照射する田村興一郎
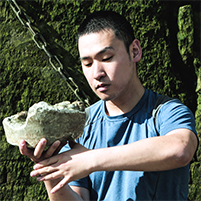
2016年、18年と横浜ダンスコレクションで連続受賞し、注目を集める田村興一郎(1992年生まれ)。Noismが拠点を置く新潟に生まれ、高校ダンス部を経て、ジャンルを越えた交流が活発な京都を出発点としてアーティスト活動を開始。汚れたジーパン、Tシャツ姿の男たちが背中にコンクリートブロックを乗せて歩く代表作『F/BRIDGE』、車のタイヤを使ったデュオ作品『goes』など、「モノと身体」の関係から生まれる作品を発表。

『F/BRIDGE』
ロンドン・コロネット劇場「Electric Japan 2022」公演(2022年5月)

『Yard』
横浜ダンスコレクション2017 アジアセレクション 最優秀新人賞受賞者公演
(2017年2月/横浜赤レンガ倉庫1号館)
出演:山本梨乃、田村興一郎
Photo: bozzo
https://youtu.be/lMT1d7089QU
『F/BRIDGE』
(2020年7月/城崎国際アートセンター)

『goes』
横浜ダンスコレクション2021「振付家のための構成力養成講座」
(2021年2月/横浜赤レンガ倉庫1号館)
Photo: Yulia Skogoreva

『STUMP PUMP』初演(2019年2月/ArtTheater dB Kobe)
『STUMP PUMP TOKYO』
(2022年3月/吉祥寺シアター)
Photo: 石田満理佳

『窪地』
韓国「Contemporary Ballet of Asia 2022」公演
(2022年11月/ソウル江東アートセンター)
Photo: Rachel Na
*1 全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)(AJDF)
AJDFは、1988年に日本女子体育連盟、神戸市、神戸市教育委員会が創設。高等学校、大学および短期大学に在籍する生徒、学生を対象にした日本ではじめての全国規模の創作ダンス競技会。毎年8月に開催され、5人以上30人未満のチームによる未発表の創作ダンスを対象にした「創作コンクール部門」とさまざまなダンスで参加できる「参加発表部門」の2部門があり、出場経験者にはプロで活躍するダンサー、振付家も多い。
*2 ケビン・カーターがスーダン内戦で撮った写真
カーターはこれでピュリッツァー賞を受賞したが、「少女を助けるべきだった」と非難を受け1カ月後に自殺。後にハゲワシはたまたま寄ってきた瞬間を撮影しただけですぐに飛び去ったという証言も出て物議を醸した。
この記事に関連するタグ