- 阿佐ヶ谷スパイダースを、プロデュース・ユニットという形で始めたのはなぜですか?
-
劇団でやったこともあるのですが、限界を感じました。映画ではその作品に合った俳優を呼んでくるんだから、お芝居もそうあっていいんじゃないかと思い、プロデュースという形で始めました。
僕の作品は、僕の脚本を基にして、現場でディスカッションしながらつくっていきますが、彼ら2人(俳優の中山、伊達)がいることによって外からカンパニーに入ってきた客演の人たちに「こういう風にやっていいんだ」ということを示せる。僕が説明しなくても、僕の芝居を、俳優としてどういう風にやればいいかというのを彼らが見せることができるので、現場がうまく動いていくんです。彼らも客演の人たちから刺激を受けられるし。ユニットの人数が5人、6人になるとそうはうまくいかないと思いますが、3人だとちょうどいいバランスがとれる。まあ僕らはかなり縛り合わないようにするんですけど、その良さもありますね。だけどそこに常に外部の人を呼んできてやる方がことで、お客さんの興味としてもいいし、僕ら3人も刺激を受けられると思います。だから、阿佐ヶ谷スパイダースは、3人でいなければ続けてこられなかったんじゃないか、と思います。 - 以前、劇団でやったこともあるのですか?
- ええ。でも、それは駄目になっちゃったんです。自分がお山の大将になって「僕が一番」になってやっちゃったから、なかなか刺激を受けられなかった。今はいろんな人から刺激を受けながらやっています。
- 作・演出のほかに俳優として出演もされていますが、そもそもの志望は?
-
僕はもともと俳優志望だったので、自分にいい役が欲しくて書き始めました(笑)。大学に入った頃に、神楽坂ディープラッツという小さな小屋を借りて、高校の同級生でスポーツをやっていた人を集めて、僕が書いたお芝居をやった。その作品が想像以上に受けたんです。お客さんが笑ってくれることに喜びを感じて、「これは書くのも面白いかもしれない!」と。それで大学の劇団に入ろうかとも思ったんですが、どうも違うような気がして、自分でやった方が手っ取り早いと、劇団を旗揚げしました。
演出に関して言えば、演出が楽しくなってきたのは最近です。誰かに託した方がいいんじゃないかとも思いましたが、5、6年前から、やっと演出することが楽しくなってきましたね。 - 他の人が書いた作品を演出したのは『ウィー・トーマス』が初めていうことですが、自分の作品を演出するのとどう違いましたか?
-
自分が書いた作品は、こうしたい、ああしたいという思いがいっぱいある。でも、他の人の作品だと、『ウィー・トーマス』でも『ピローマン』でもそうですが、一本の芯というか、この作品のこの部分を見せたい、というのをまず念頭に置くわけです。『ウィー・トーマス』の場合は、「登場人物たちは不器用ゆえにひどいことになった」「家族のような温かい場所が欲しかった」という風に僕が思った、まずはその大枠を信じて作ることにしました。
アイルランド問題はもちろん飛ばさずに入れましたが、でも日本人がそれをすべて理解することは難しい。マーティン・マクドナーがユーモアや皮肉に変えて描いていることの、たぶん全部は伝わらない。だったら、日本でやる分には、わからないジョークは変えていってもいいだろうと。そして、最終的に“温かいもの”を持ってくるためには血みどろにしなきゃいけないと思って、予算の多くを血と火薬と死体に使った。多分、それは正しかったと思います。そうして、とにかく真摯につくる。ジョークじゃなくつくる。コメディをコメディとして面白そうにつくってはいけない。マクドナーの本にも僕の本にも共通しているのは、面白くつくってあるんだけど、そこを敢えて真面目に、俳優たちは死ぬほど真剣につくらないとつまらなくなるということです。コメディの基本だけど「やっている本人たちはクソ真面目」だってところを守ってやりました。 - 『ウィー・トーマス』では、過激派のテロや殺し合いといった暴力表現が、賛否両論を巻き起こしました。暴力表現についてはどう思っていますか?
-
僕が高校のときに見た芝居って、それなりに当時の人の心の痛みを表現しているんですが、それがどうも嘘っぽく見えて、「そんなもんか?」と思ってしまったんです。人間を描くのに、こぎれいに描いてしまうと、生きている僕たちの方が生々しいから、退屈に見えてしまう。人間ってもっと生々しいものだと思うんです。例えば、いやな気持ちになったときに、僕は、「とりあえずダンスミュージックを聞いて陽気になろう」とは思わない。そういう時には悲しい曲を聞くべきだって。悲しい曲の中に“光”を感じられた方がいいと僕は思っている。悲しい音色だからといって、僕は(観客を)救わないつもりはない。是非とも救いたい。そこに光を感じることで救われると僕は信じているんです。陽気な、表側だけ見るのは嫌だ、裏側が見たい。それが必ず暴力表現に繋がるとは限らないけど、そういうものを抜きにしてもいけない。
『ウィー・トーマス』に関しては、わけのわからない世界に連れていかれて「なにかが起こっている」という感じを体感する――劇場の中で火薬がバーンと爆発して、失敗するかもしれないし、何が起こるかわからない、という感じが、僕は好きでしたね。非常に緻密なつくりだし、楽しいエンターテインメントでもあると思う。 - 劇作家として、自分とマクドナーに共通するものを感じますか?
- マクドナーの戯曲を最初に読んだとき、日本の小劇場の芝居とすごく共通するものがあって驚いた。僕らが上演するにはもってこいだと思いました。レールに乗っかりさえすれば話が転がっていくという作品は面白くない。この作品には予測の付かない展開で息をつかせない、自分たちと共通の匂いがあると思いました。人間がリアル(生々しく)に、それでいて演劇的に描かれている。僕は日常会話をなぞったようなお芝居よりも、劇場に足を運ぶからには、何か「演劇的にリアル」な人物を見せたい。だから、『ウィー・トーマス』では、アイルランド解放は、日本と状況が違うのでわからない、と最初は思っても、アイルランド解放と言っている若者たちを人間として見たときに、いつの間にか感情移入して入り込める──そういう風に演出したいと思いました。
- 『ピローマン』に関してはどうでしたか?
-
作家の話ということで、非常に苦痛を伴って書いたのではないかと思いました。彼の中にある苦痛や喜び、そういうものがいっぱい詰まっているから面白い。マクドナーが劇作家として次の段階にいっている、と思った。それは僕にとってすごく大きな刺激になりました。
ロンドンでの上演を見たときに、見終わって思ったことは、「ひどい話なのに、やっぱり僕は救われた」ということです。緑の少女が出てきたときとか、原稿を焼かなかったとき、すごく救われて、あれだけ生々しいのに僕にはまるでファンタジーのように見えた。それがすごく印象に残っています。暗く、重く、しんどい芝居になるかもしれないけど、最後にびっくりするぐらい心が軽くなる。それが何なのかはそのあと探ればいいや、と。マクドナーは冷酷なだけの人間をつくらないで、人物にちゃんと表も裏もつくって、その人の暗い面をうまく表現している。そこが僕の好きなところだったし、舞台でちゃんとやりたいと思ったところでした。一筋の光が最後に見えれば成功だと思って演出しました。『ピローマン』のときには、『ウィー・トーマス』のときよりずっとクリアに(演出していく上での)ラインが見えましたね。
マクドナー作品を演出した後に自分の芝居を書くのは本当に疲れます。自分で「これは、マクドナーが読んだら笑っちゃうだろうな」と書き直したりして。同じ世代ですからね。「彼があれだけの本を書いたのに、これじゃあ駄目でしょ」とか、これでいいのか、これでちゃんと書けているのか、と自分に問いかけることがものすごく多くなった。マクドナーをやったあと、作品をつくったり、人物を造形したりする上で一段上に上がろうとするようになり、それはすごく僕にとって大きなことでした。 - 最新作の『悪魔の唄』は第二次世界大戦のことを扱っています。長塚さんが戦争についてどういう風に感じていたか教えてください。
-
僕は、小学生の頃に原爆に関する資料映像を学校で見せられ、それが恐ろしくて、トラウマ的な体験になってしまった。それから、中学生のときには、学校の先生たちがいわゆる「左」で、授業が終わったあとに、「教科書に載ってないこともある」と言って、731部隊では中国の人を人体実験に使っていたというような話をするんです。そういう「左翼教育」で、日本に対して否定的になっていった。そんな中で、大学生の頃、日本のスポーツ選手が海外で活躍しはじめると、日本人が日の丸を振って応援している姿が目につくようになり、「こんな国だったかな?」と。なんだこれは、っていう答えの出ないいろんな疑問がわいてきて、今の世界の構造が、第二次大戦の勝者と敗者という構造でできあがっているとか、じゃあ第二次世界大戦が起こらなければアジアはどうなっていたんだろうかとか、そういうことを考えはじめた。
いろんなことを複雑に思いながら、沖縄に行って、戦争の資料を見て回りました。で、僕が思ったのは、彼らがなんのために戦ったのかということ。国のため、というのもあっただろうけど、彼らにも普通に家族がいたり恋人がいたりして、その人たちのためにも戦っていたんだ、と。当時の国が巻き込んだ市民――僕らも戦争が起これば巻き込まれるわけだけど――そういう人たちが一杯いて、そういう人たちまで否定してはいけない、日本の犯した罪は罪で認め反省しつつも彼らに対する敬意は忘れてはいけない、と思いました。 - イラク戦争が起こり、日本も岐路に立つこういう時期だから、戦争というテーマを扱おうと思ったんですか?
- 今この時期だからというのではなくて(戦後60年だからということではなくて)、ただ、今、僕が思ったから。27、28歳あたりからだんだん戦争を扱わなきゃいけないという感覚がクリアになってきた。それはもちろん、いろんな事柄の影響を受けているのかもしれないけど、(こういう芝居をやることによって)今の人間が当時のことを思い、今の自分が生きていることを「どうなんだろう」と思うことが一瞬でもあればいいと思っています。「日本が好きか」と聞かれれば、みんな答えを考えると思うんです。
- 今回の作品では、戦争というものを、歴史やイデオロギーとしてではなく、人間心理としてとらえようとしてますよね?
-
そう、その人たちを描くことしか僕はしたくなかった。初めて行った沖縄で、資料館ばっかり回って、3泊4日戦争漬けの旅でしたが、そのときに行った喜屋武(きゃん)岬――アメリカ兵に追い詰められた島民が、投降しないで身投げしたところですが、ここが死ぬほど美しい。ありえない美しさの中で人が死んでいく、それが戦争なんだと。景色とか関係ないという考えが変わって、僕は立ち尽くした。けっこうショックでした。きつかったです。
思ったことを主義主張として問題提起していく――そういうことではなくて、感情のままにやっていけば自ずとそうなっていくかもしれない。そういうやり方もあるんじゃないかと思っています。…去年『Live Forever リヴ・フォーエバー』というブリットポップの映画を見ましたが、イギリスの政権がサッチャーからメージャーになって、ブレアに変わっていく中で、ヒットチャートを飾るロックミュージシャンたちが、すごく国のことを考えていたのがわかった。自国の政治と向き合い、イギリスという国と対峙していた彼らの姿勢にすごい刺激を受けました。音楽として楽しんでいたものに、非常に(政治的な)意味があった。彼らもそういうこととしっかり対峙していた、ということがショックでした。僕自身も時にはそういうものと向き合っていきたい、それは作品もつくる上で必要なことなんだ、と今は感じています。 - これから国際的な場に自分の芝居を出していきたいと考えていますか?
- 日本の小劇場でやられている演劇が、海外でどういう風に見られるかということにはすごく興味があります。別にこういう、戦争を題材にしたものじゃなくても、今までに僕がやってきた家族ものでもいいし、そういうものがどういう風に受けとられるのかということに興味がある。もしチャンスがあれば――日本人の俳優でやるのか、向こうの俳優さんを使ってやるのか、どういう形でやるのかはわからないけど――やってみたいです。
- 長塚さんより下の世代の人たちはゲームばかりやっているように見えますが、そういうデジタル世代が、生身の人間がやる演劇を見に劇場に足を運んでくれるのか、演劇というものを継承してくれるのか、という未来への危惧は感じませんか?
- すごく感じますけど、もしかすると一面的に見てしまっている可能性もあると思う。そうじゃない子たちは確実に育っていて、その人たちに期待するべきだと思います。要するに、マスコミは「ゲームでバカになる」とか決めつけるのが大好きなわけです。でも、ゲームを通じてコミュニケーションをとっている子もいるだろうし、そこで初めて何かしらの創造を志向する、そういう人もいるから、一概には言えない。「彼らが大人になったら不安だ」とだけ言うのはどうかと思います。
- この先、こういうことをやってみたいなというのはありますか?
- 機会があれば、映像をつくりたいという気持ちはあります。あと、ストレートプレイは、それはそれでやりたいけど、一方で「もっと何が起こるのかわからない」、体験する場所としての演劇のようなものをつくってみたい。どこかの都市のどこかの劇場で、あそこにいくとあれやってるらしいぞってみんなが見に来るような、サーカスみたいな、オフブロードウェーの『デ・ラ・ガルダde la guarda』(観客が立ちっぱなしでアクロバットやダンスを見るショー)や『TUBES』(全身真っ青に塗った3人のブルー・マンによるパフォーマンス)みたいな。規模は小さくてもいいから、そういうことがいつかできないかな、と思っています。
長塚圭史
生々しい人間の裏面にファンタジーを見る
現代演劇のニュージェネレーション、長塚圭史

長塚圭史Keishi Nagatsuka
早稲田大学在学中の1994年に「劇団笑うバラ」を旗揚げ。解散後、96年、劇団の形態にとらわれず、少数で行う芝居をやりたいと、新たにプロデュース集団「阿佐ヶ谷スパイダース」を結成し、作・演出・出演の三役をこなす。テレビドラマの脚本執筆や映画への出演など活躍が広がっているが、商業演劇でアイルランドの現代戯曲を演出するなど、新進演出家としての期待も大きい。阿佐ケ谷スパイダースでは、自作以外の作品も取り上げ、小劇場演劇の実力ある俳優を集めたプロダクションを実現している。長塚作品の特徴は、親子関係や恋愛感情などの人間関係を現実と虚構の中間の感覚で描くところ。2004年の『はたらくおとこ』は9都市で公演を行い、1万4,800人を動員している。
(インタビュー・構成:目黒条)

『ウィー・トーマス』 The Lieutenant of Inishmore
撮影:関村良
2001年にロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのジ・アザー・プレイスで初演、ウエストエンドでもロングランした。2003年度ローレンス・オリヴィエ賞ベストコメディ賞受賞。日本では、2003年8月に長塚圭史演出でパルコ劇場にて上演された。アイルランドのイニシュモア島を舞台に、アイルランド解放軍過激派の若者たちが一匹の猫をめぐる騒動から互いに殺しあう暴力的なコメディとして、話題を巻き起こした。
マーティン・マクドナー Martin McDonagh
1971年ロンドン生まれ。劇作家。両親の出身地であるアイルランドのリナーン地方を舞台にした『ビューティー・クイーン・オブ・リナーンThe Beauty Queen of Leenane』で96年デビュー。同作品はイブニング・スタンダード紙賞新人作家賞のほか、ニューヨークプロダクションが98年にトニー賞4部門を受賞するなど大ヒットした。続いて『スカル・イン・コネマラA Skull in Connemara』『ロンサム・ウエスト The Lonesome West』の「リナーン三部作」を完成させた。さらに、アラン島三部作として『The Cripple of Inishmaan』(邦題『夢の島イニシュマン』で文学座が上演、邦題『ビリーとヘレン』でメジャーリーグも上演)『ウィー・トーマス(原題:The Lieutenant of Inishmore)』を発表。2003年に『ピローマンThe Pillowman』を発表。

『ピローマン』 The Pillowman
撮影:関村良
2003年11月から2004年4月、ロンドンのナショナル・シアターでレパートリー上演された。2004年度ローレンス・オリヴィエ賞最優秀新作賞を受賞。ある全体主義国家で、一人の作家が逮捕され、彼の書く残酷な童話のとおりの手法で子供が次々と殺される事件の容疑をかけられる――その取調室での刑事とのやりとりが恐ろしい事実を次々と暴き出していく、スリリングなブラックコメディ。マクドナーが、初めてアイルランド以外の場所を舞台にした作品として、劇作家としてのさらなる挑戦が高く評価された。日本では、2004年11月に長塚圭史演出でパルコ劇場にて上演され、各賞を受賞するなど絶賛を受けた。

『悪魔の唄』

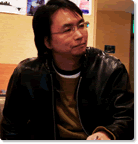
この記事に関連するタグ

