- ダンスというものとの、そもそもの出会いについてお話しいただけますか?
- 奈良の桜井という田舎に生まれ、引っ込み思案で取り柄のないおとなしい女の子でした。麿赤児さんと同郷なのですが、体だけは柔らかくて、テレビを観ながら楽しそうに踊っているのを見た母親が「この子は踊りをやったらいいんじゃないか」と思ったようで、書道やそろばんといったお稽古事の一つとして10歳からモダンバレエを習い始めました。おとなしい子だったから黙ってずっと続けていたんですが、そこでの踊りも楽しくて。それで、大阪で活動されていた巻田貞之助・京子芸術舞踊研究所というところで踊り始めました。
- 巻田貞之助・京子芸術舞踊研究所ではいつ頃まで踊っていたのですか?
- お稽古事の意識としては高校生くらいまで。コンクールに出ることになった時、先生に「自分で作品をつくってみないか?」と言われて、そこから自分の表現というものが始まったように思います。その時に自分が何をやりたいかということを初めて考えた。それまでは先生の振り付けで、先生がつくった世界で踊っていたわけだけど、何か違うなという気持ちもあって。
- バンドでいえば、コピー曲ではなくオリジナルをやろうと。
- そうそう、オリジナルをやりたくなった。「この音楽で踊りたい!」というのがアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンだったりして(笑)。それで服を裂いたり、口をガーッと開けて叫ぶようにしてみたり。高校3年生の頃ですね。発表会でノイズ/インダストリアル音楽を使って、これまでの先生の世界とは真逆のものをやった。そこで、先生がそういうものをやらせてくれたというのが良かったんでしょうね。「そんなの駄目。もっときれいな踊りをしなさい」ではなく、「いいじゃない、祥子ちゃん!」って(笑)。それを伸び伸びとやらせてもらえたのが、今の自分に至る最初のきっかけだったかなと思います。そして、自分を表現したものがコンクールに入賞したっていうことが、「これでも認めてもらえるんだ」という、自分の中での確信になった。元々、映画でも音楽でも美術でも退廃的な世界観をもったものが好きだったんですが、そういったものを踊りで形にできた。それが今も自分が続けてやっていることの原点になっています。自分が頑張ってつくり出したという面白さ。狭い自分の部屋で壁に手が当たったりしながらね。
- 72年生まれの東野さんにとって、その当時、ノイバウテンは既に新しい音楽ではなかったのではないですか?
- はい。その時代の一番新しいものはマドンナとかマイケル・ジャクソンとかで、そういうのも先生は使ったりして、私もそれで踊ってた(笑)。でも「どうなんかな?」って自分では思っていました。
- 奈良の田舎に住む女子高生がノイバウテンのような音楽を知ることとなったきっかけは?
- 私は奈良の天理高校という、全国から生徒が集まり、その半分が寮生という学校に通っていました。私は実家から通っていたし、天理教の信者でもなかったんですが、その中にバンドをやっている子たちがいて影響を受けました。一緒にライブを見に行ったり、出来たばっかりのクラブに行ったり。
- その後、高校を卒業してすぐに大阪へ?
-
しばらくは奈良にいました。今まで奈良で習っていた先生は大阪にも教室をもっていたので、大阪の短大に通いながら子どものクラスで先生の助手をやったり、代稽古をしたり、自分の稽古を見てもらったりということを毎晩やっていました。短大を卒業した後も助手を続けていたんですが、自分でももうちょっとダンスを掘り下げてつくっていきたいなという気持ちもあって、別の先生にも習い始めたり……。
そういう枠の中にいてわかってくると、どうしても出て行きたくなるというか、自分で表現したくなってくる。それで、一度自分でやってみようと思い、2人のDJと「ERROR SYSTEM」というユニットを組んで大阪でパフォーマンスを始めました。私はその頃、ソロでもディジェリドゥ奏者と一緒にライブをやったりしていたんですが、お寺でパフォーマンスをした時に、今、BABY-Qで音楽を担当している豊田奈千甫という女の子と出会い、現在のBABY-Qの母体をつくりました。 - その当時、ERROR SYSTEMが出演していたイベントはどのような内容だったのですか?
- 私は大阪のコンテンポラリーダンスのシーンに近寄りたくなかった。所謂、ダンス業界的なものが。そこに入ってしまえば簡単に公演をしたり、色々なところと繋がりができたのでしょうが、向こうも私がやっていることを気にもかけていなかったし。それで自分たちはクラブや、ステージとサウンドシステムしかないような野外でやっていました。
- 90年代の終わりは、国内でもレイブのような野外の音楽イベントが定着し始めた頃でしたね。
-
そうですね、そういった場所に行ってパフォーマンスしたり、自分たちで企画してお寺でやったり。大阪造形センターの上に「カラビンカ」という小さい劇場があって、そこで自主公演をやったり。それと並行して、
維新派
(大阪の前衛劇団)から派生した「プリティーヘイトマシーン」という野外劇団に女優兼ダンサーとして出たりしていました。
あの頃は、やれる場所も状況もなかった。受け皿もシステムも。あと、ダンスに関しては観客もいなかった。今までダンスを観てきた人たちっていうのではなく、もっと自分の表現を同じレベルで感じてくれる人たちが、もっとダンスに近づいてほしいという気持ちがあった。それは今でも変わっていません。観客自体を、私たちの表現を面白いと思ってくれる人を探していました。アウェイというか、踊りに来ている人たちの前でいきなりパフォーマンスしたら「何?」って反応されるような場所で、後で「良かったよ」って言われるように、考えながらやっていましたね。 - その頃の大阪のダンスミュージックのシーンで、所謂ダンサーが踊るということは珍しかったのでは?
- レゲエ、テクノ、ハウスといった音楽から出て来たダンスではなくて、コンテンポラリーのような「よくわからないダンス」っていうのは、特異な存在ではあったと思います。ERROR SYSTEMは3〜4年やりましたね。
- ERROR SYSTEMという名前の由来は?
- 間違ったシステムを作っていこうと3人で決めた。そもそも受け皿やシステムと言ったものが本来間違っているということを言いたかったというのもあって。ERROR SYSTEMでダンス業界がやっているフェスティバルに応募したこともあります。その頃はやる場所が本当になかったから。でも後々、その頃にERROR SYSTEMの存在を知ってずっと探してくれていた子が、今やっと辿り着いてBABY-Qにいたりするんです。出演情報は殆ど表には出ていませんでしたからね。
- ERROR SYSTEMの活動とBABY-Qの立ち上げは、時期的に重なっているのですか?
-
一人でダンスをやることに限界を感じ始めたんです。言えることが限られてきますから。色んな面白い人たちを出演させ、キャラクターなりイメージを使って、そういう世界をつくってみたい、演出したいと思い始めていた頃、豊田奈千甫と池端美紀と3人でBABY-Qを始めました。2000年に島之内教会で行った公演がBABY-Qの旗揚げです。キリスト教の教会でやったのはプリティーヘイトマシーンや維新派の影響があったと思う。どちらも自分たちで世界をつくっていくというDIYで(笑)。野外の掘っ建て小屋に1カ月泊まり込み、舞台設備から全部つくっていくというハングリーな感じに影響を受けて「自分でもやってみよう」と思った。
その時の公演(『E-DEN – electronic garden』)の参加メンバーには、元維新派の女優であったり、ミュージシャンであったり、ストリップダンサーであったり、役者であったり、ダンスを習っていたという人は一人もいませんでした。演劇とまではいかないけど、最初の頃のBABY-Qには具体的なキャラクターやストーリーがありましたね。かなり無茶苦茶なテンションでやっていました。キリスト教の教会でストリップダンサーがシスターの格好で逆十字でオナニーしたり、最後にダンサーがデストロイド・ロボットをぐちゃぐちゃに壊してしまうとか、そういうことを「教会のステージでやっちゃった」みたいな。神父さんが「早く帰ってくれますように」ってお祈りするみたいな(笑)。 - BABY-Qというカンパニー名の由来は?
-
“バビロン・クエスト”という意味なんです。悪徳と美徳が同居するバビロニア王国の首都バビロンに住む人間は美しい部分とドロドロした部分をもっており、そういったものを同じ感覚で舞台に上げて、自分たちの表現の中で人間自体を掘り下げていって、何が心に響くのかを探していこうというイメージです。パッと見、かわいらしい子供服ブランドみたいな名前ですけど(笑)。名前を付けた時は「良い名前だ!」って思っていたのに、東京に来たら「名前変えたら?」と散々言われました(笑)。「海外じゃぜったいウケないよ」って(笑)。
- BABY-Qの作品づくりに関わる人々はダンサーではない人が多いですよね。
-
ダンサーはあまり使いたくないと思っています。変にダンスが上手い人って個性がないから逆に面白くなかったりするでしょ。器用で、言ったことを忠実にやってくれるけど味がないというか、薄いというか。私自身の感覚だと、ダンスそのものよりも人自身がもっている魅力というものを、作品のイメージの中で舞台上にそのままもっていきたい。ダンスだけを観たい人には「BABY-Qって東野さん以外は踊れないんだよね?」ってよく言われますが、そうじゃない面白さを私は求めていました。最初の頃は特に。最近になって踊りの部分が増えてきて徐々に変わってきていますが、それにしてもやはりキャラクターの面白い人たちの方が絶対、踊りは面白い。はみ出てもらった方が面白い。
- そのような発想は、ダンス業界への反発からくるものなのですか?
-
いや、自分がやりたいことがそうだっただけです。だから、受け皿を自分でつくっていくしかなかった。もちろん反発はしていたし、既存のシーンの中で安泰して公演をやっていくということに重きを置いていなかったから、できる場所を自分たちで探していこうという気持ちでした。教会でやった後、伊丹アイホールに「貸してください!」っていきなり直談判しに行ったこともあります。ほかには、「ロクソドンタ」という天王寺にある小さなハコだったり、「MUKOGAWA DANCE ON THE BANKS」という川沿いの気持ちのいい芝生の上でやる音楽とダンスのイベントなどでやっていました。
- 現在は活動の拠点を東京・高円寺に移したBABY-Qですが、大阪時代の活動についてもう少し詳しくお聞きしたく思います。その頃のBABY-Qはどういう人たちと関わっていたのでしょうか?
-
最初、BABY-Qを3人でやり始めた時に「デストロイド・ロボット」と一緒に作品の制作をしました。プリティーヘイトマシーンで知り合ったんですが、もうちょっと、ダンス寄りの作品でもやってみないかと誘いました。ダンサーには私が女優とか役者さんをスカウトしてお願いしました。「BusRatch」をやっているタカヒロ君やシロー・ザ・グッドマンに音楽で参加してもらったり、映像では「BetaLand」というVJチームとか。言ってしまえば、クラブで遊んでた人たちですね。そういう所で出会った面白い人たちを集めました。「やってみない?」って声を掛けたら、みんな面白がってくれて、凄い頑張ってくれた。まだ、ダンス表現でごちゃごちゃしたものがなかったから頃でしたから。
- 参加した人たちひとりひとりがアイデアを出して来るのですか?
-
そうですね、「白塗りでやってみていいかしら?」とか。「ポールダンスできるから」と言われてそういうシーンができたりとか。「女優だからこそ、ここでこういう風にしてみよう思う」とか。人のキャラクターでシーンができていく。今でも私のつくり方にはそういうところがあります。振り付けをするというよりも、「自分を出して」と言う方が多いですね。
大阪は狭いから違うジャンルの人が繋がりやすいんです。東京のように音楽、演劇、ダンスとか色んな風に分かれていないしクロスしているから、ジャンル同士が近い。クラブが社交場のようになっていて、面白いことをやっている人たちはみんなそこに遊びに来ていました。
そうこうしているうちに、自分たちの稽古場が欲しくなってきて、タイミングよく友達が「味園」という廃墟ビルを見つけてくれたんです。友達が1階にクラブをつくるというので、その上にあった鏡張りでバーカウンターのある、夜逃げするまでは水商売が営まれていたであろうという雰囲気の部屋を、ただ鏡張りだったという理由だけで借りた。鏡があるんで、後は天井抜いて、床にリノリウム貼って、それだけでスタジオにしました。DIYです(笑)。
- 初めてもつことができた自分たちの場所ですよね。
-
そう。しかも私たちがスタジオを使い出してから、レコード屋さんが出来たり、友達がバーやマッサージ屋さんをやり始め、味園というビル自体が盛り上がってきたんです。友達に「カフェやろう」と誘われて、レッスンが終わってから夜に「CafeQ」というお店をやり始めました。そこで色々な人にライブをやってもらっていたのが2003年頃ですね。
- 遊び場で知り合った人たちが、自分たちの集まりやすい場所をつくってしまった。
-
セッションもよくやっていました。即興音楽と一緒にやったり。「新世界BRIDGE」というライブスペースがあったのですが、そこでやっていたアーティストたちやDJたちが来てくれたりして。「じゃあ次一緒にやってみない」という感じで面白い人との出会いがあった。見たことないもの、聴いたことのない音楽が日常的に溢れていた。大阪が面白かった時代です。
そういう風に二足の草蛙をやっていたんですが、次第にダンスが忙しくなってきて、もっとダンスをやりたいという方向に気持ちが向いてきた。味園っていう遊び場もある程度つくり上げたという感じだったから、「私が抜けてももう大丈夫かな」と思って。ちょうど東京へ行こうかなと思っていた時に「トヨタコレオグラフィーアワードに出してみないか」というお話をもらった。小さい時のコンクール以来、初めてアワードというものに出してみようと思いました。そうしたら、ガガガっと「ビデオ審査受かった」「え、東京に行かないと」という展開になり、みんなで舞い上がってしまって。でも頑張って行ったらアワードをいただいてしまって、それに後押しされて東京に拠点を移しました。
- どうして大阪から東京に出ようと考えていたのですか?
-
「大阪は狭いな」という感覚になっていたというのはあった。ある程度やってしまった感があって、劇場にしてもそうだし、人にしてもある程度知り合えてしまったかな、と。セッションしたいミュージシャンともやり尽くしてしまった、という。今も大阪に住んでいたとしても色々できるとは思うんですが、私自身「踊りたい」という衝動がすごく強い。ダンスというものは生で観てもらわないと伝わらないものですし、東京も一つの通過点かもしれませんが、新天地を求めていたんだと思います。
大阪でやり続けて「BABY-Q?うんうん、良かったよ」って言われるのは嬉しいですが、批判もちゃんとされたいですし、知らない世界をもっと知りたいという欲望があった。刺激中毒なのかもしれないけど(笑)。石橋を叩いて渡るじゃなくて、着地点もないのに飛んでしまうというか(笑)。だから東京で何をするのか決めていないしスタジオもないのに住む家だけは決めて、口で言うより先に体が勝手に動いてしまった。東京に来た最初の頃は途方に暮れていたんですけどね。それが2005年の春のことです。
- 場所を高円寺に選んだのはなぜ?
- 友達がいっぱいいたからというのもあったし、やっぱり中央線=出発点みたいな感じがありました(笑)。東京ってシュッとしてないとだめな場所だと思っていたんですが、高円寺は大阪に似ていて行きたい所がどこも近く、気張らなくてもいいし、住みやすい。最初は、バレエスタジオの空き時間を借りようかと思ったんですが高くて、それなら自分たちでつくろうと。スタジオつくるのは、床貼って、鏡貼るだけなので簡単ですから。隣のビルの部屋を借りて、維新派時代の人にも来てもらって、またDIYでつくりました(笑)。
- そういった、自分たちの場所は自分たちでつくっていこうとする意識は、BABY-Qの作品の中でも其処彼処に見受けられますね。では、参加メンバーが一丸となってつくり上げる作品の中で、東野さんがもつ世界観やアイデアはどのように現れてくるのでしょうか? 東野さんの作品の世界観やその制作過程についてお伺いしたいと思います。BABY-Qや東野さんのソロ作品の中には、舞台上に人形や機械といった無機物が、まるで役割を与えられた役者のように出演していますが、ここから全ての作品中に通底する美意識が感じることができます。意図するものは何なのでしょう?
-
どうしても舞台に上げてしまう。鉄、硬質なもの、生きていないもの、しかもちょっと壊れていたり朽ちていたり、しかもそれらは必ず擬人化されていたりする。当初は無意識で選んでいましたが、なぜ美術として人間ではないものを選ぶのかということについて作品をつくっている時に考えたことがあるのですが、自分の影響を受けたものの中に寺山修司さんであったり、「人間機械論」というシュルレアリスムの中の一つの理論で「人は機械にもなれるし、機械は人間になれる」といったものがあるからなのだと思います。
私は人間ですが、自分自身の踊りの中には機械的なイメージや動きがある。言ってしまえば、振り付けされる身体というのはマシーンだったりするわけです。よく出来た精巧な、ちょっとした角度でもつくることができるマシーン。それで人に見立てた機械に心の通じ合えるものとして舞台上にいてほしいというか。それと踊りで交流できるということに惹かれているんじゃないかと思います。そこからは鉄が錆びていった時間の経過も見て取れるし、朽ちていく儚さも感じられる。ある意味グロテスクなビジュアルで優雅なものではないんですが、そこにある美意識を見せていきたい。それを私自身も探しているし、本能的に自分の踊りの中で表現の一部にしてしまう。これが自分のやりたい世界観なのかな、と気付いた作品が『←Z←・ Z 滑稽な独身者機械』。マルセル・デュシャンの作品に「独身者機械」というのがありますが、機械に関してはその感覚に凄く影響を受けている。愛おしくなっちゃう。
- 21世紀の現在において、シュルレアリスムは美術史の中である意味クラシックな概念ですよね。そういった方法論に強く惹かれるというご自身の意識の働きについては、突き詰めて考えたことはありますか?
-
出て来た時代は古くっても、それをなぞっているつもりは全然ない。私は今を生きているし、そこに捕われているわけではないけど、自分の中にその感覚が絶対にある。機械のようなものと生っぽい「性」。私が女であるという理由であったり、流れ出る血であったり、そういった女が持っているものと対比させているのかもしれない……。自分の中にある血なまぐさい物が、ある意味母性であったり、子どもが生まれてくるといったところに繋がってはいると思います。
- 生産性のある機械と女性性を対比させることで見えてくる世界があるということでしょうか?ソロ新作『VACUUM ZONE』にはそういった女性性が強く打ち出されているように感じました。何も無くなった真空状態の中で東野祥子という一女性に何が出来るか、といった覚悟を垣間みました。
-
私の作品の中で女性性というのは、別にエロスという意味で武器として使っているわけではなくて、必然というか、「隠さないといけないもの」ではないと思っているということ。逆にそれを露見させることで、日本の社会の酷さというか、女性性が欲望の対象でしかないというか、そういうことを考えてもらえたりすると嬉しいなと思う。だから、ダンサーに裸に近い格好をしてもらったり、実際裸になってもらったり、そういうものはやっぱり出て来てしまう。欲望がないと生きていけないから。自分が女であるということが、いつもは無意識だけど、作品をつくっていく中で勝手に出て来てしまう。計算してやっているわけではないんですが。
- BABY-Qの作品は、多様な個性をもつ参加メンバーたちの意見を聞いて、東野さんがアレンジャーに徹しながらつくられているという印象を受けます。その、制作の方法と過程についてお聞かせいただけますか?
-
1999年にピナ・バウシュの作品『ビクトール』を観て衝撃を受けました。“人”なんですよね。「あの人好き」という風にダンサーの顔を覚えてしまう。1回観ただけで人の顔を覚えられるなんてあまりないのだけれど、それぞれのキャラクターを好きになれてしまう感覚が面白いなと思えた。一人でバスに乗って東京まで来て観たんですが、感動して泣いて、泣いて……。人自身がもつ力を掘り下げたものだったのだと思います。単純なことしかやっていないんだけれども、それが意図されたもので、そこに意味があるということに気付くと凄く面白い。寺山修司の「書を捨てよ、町へ出よう」からの影響もあったと思いますが、これを観たことでBABY-Qをつくってみようという気持ちの動きに繋がっていった。
私の作品はいちいち主題が大きいというか、大きな世界観を言いたい派?(笑) だから、最初に作品をつくろうと思ったら、タイトルを最初に考える。一番言いたいことを伝えるために、後で味をつけられるような、キーワードを必死に探す。
例えばBABY-Qの作品『GEEEEEK』は東京でつくった最初の作品ですが、「GEEK」という奇形やオタクを意味する言葉にEを3つ足して「ギィーク!」と叫んでいるような、なんとかしてそこを抜け出したいと思っている感じにしました。「GEEEEEK!」という言葉から、自分たちの環境、感覚、経験したこと、メディアの情報というものを発想させたかった。
その前の作品『ALARM!』は警告という意味ですが、「もう危険だよ。もう鳴り響いているからどうしよう。あなたたちはどうする?」というイメージです。『VACUUM ZONE』は、世の中はほとんどゴミで、それが全部吸い込まれてしまった後に何か大事なものが残るんじゃないか、それを探してみたいというイメージ。そういったイメージがまずできて、それから音、映像、美術、フライヤーのビジュアルなどを同時進行させていく。だから振り付けが先にあるわけでは絶対ない。それが一番最後なんです。
誰とこの世界をつくりたいかと考える時に、自分がやってみたい人や同じ世界観を共有している人に、映像だったらROKAPENISに相談しに行く。「こういうタイトルにするんだけど、何かイメージある?」と。「私はこういう風に踊るシーンをつくりたいんだけど、何かアイデアある?」と、まず世界を提示し、帰って来たものをまた私が加工するというやりとりを結構します。ガチガチに「こうやってして欲しい」というのはあまりなくて、信用している人と一緒にやっている感じです。
それはダンサーにしてもそうで、振り付けをする部分はもちろんあるけど、シーンが出てくるのはダンサー自体からというのが多い。普段から即興のワークショップでダンサーを鍛えているんですが、色んな方法を使って自分の中に何があるのか掘り下げさせ、そこから踊りがどのように出てくるのかを体験させる作業をしている。それをよく見ているとダンサー自体の資質がわかってきて、やはり上手い子は同じような動きばっかりしてしまい面白くない。下手糞だけど、頑張って何かを出してくる子の方が面白い。
そういう風にあんまり君主的ではないつくり方をしています。最終的には私が全部決めるんですが、共同作業という感じです。音に関しても「こういうシーンつくりたいんだけど」と言葉でまず提示し、帰って来た音に対してさらにオーダーをして加工してもらう。映像に関しても同様のやり取りをしていく中で一本の作品となり、最終的に自分の踊りが出来ていく。一番自分が最後までほったらかしというか(笑)。いつもゲネ直前のギリギリまでああだこうだ言っています。
私は外側を固めてしまいたい人なんでしょうね。やいのやいの言いたい人。踊っているだけだと満足しない。演出するという意味では、照明にしても音量にしても細かいことが凄く大事だと思う。周りが固まってからやっと成り立たせることで、自分に関しては振り付けに縛られることなく自由でいられる。
- 『VACUUM ZONE』に限っていえば、BABY-Qの作品にも通底する寓意的な美術装置が舞台に並べられていて、それらが穴の中に吸い込まれて消えて、東野祥子という一個人が残る。その演出方法が本当にすごいなと思いました。
-
そう思ってもらえたらすごく嬉しいです。一人残ることの怖さという感覚があって、でも自分自身でいられるということが大事というか、そうでないと自分は何処にもいないわけだから。それまでは自分自身を色んなもので飾っているんですが、それらがはぎ取られた後の何もない状況で私が踊れるということ。いるということ。生きているということ。ソロ作品をつくるのは本当に大変で、悩みながらたくさんの振り付けを考え、でも全部やめるという試行錯誤を繰り返しました。
構想自体は1年前からあって、よく似た状況でやったことが一度ありました。大阪の地下鉄の工事現場でやった作品なのですが、ダンス以外は全て即興で、ほとんどノリ打ちでやったような公演でした。上からどんどんゴミや粉塵が降ってくる工事現場の穴の中で、モワモワした中で人間たちが蠢いているという内容だったのですが、イメージはそこから来ています。あの世界をもう一度ちゃんと掘り下げてみたいな、と。 - 作品のテーマ選びについてもう少し突っ込んでお聞きしたく思います。2008年のBABY-Qの作品『MATAR O NO MATAR』は時期的に秋葉原での大量殺傷事件を想起させるタイトルでしたが、実際に起きてしまった社会事件が作品作りに影響を受けるということはあるのでしょうか?
-
やっぱり生きている以上、そういう感覚はあるっていうか、どんどん凶暴になっちゃう(笑)。敢えて過剰に表現するという部分が元々あって。そんなものがなくても踊りだけでいいと思うんですが、自分がそれを選ぶということは、自分が生きているという中で感じているからだし、やはり心が動くときというのはショックを受けたときだったりしますから。
『MATAR O NO MATAR』って「やるかやられるか/生きるか死ぬか」という意味なんですが、生きるか死ぬかって、本当にわからないなって。由来はあるCDのタイトルから。秋葉原の事件に関していうと、知り合いの後輩が殺されているんです。ただバイトでティッシュを配っていたら事件に巻き込まれてた、その身近さ。新聞見たら毎日そんな記事ばかりで、テレビをつけたらバンバン人が死んでいて、それが当たり前になっているという感じ。心がどんどん荒んでいくような状況を私たちが感じて、舞台でやってみたらどう思われるんだろうみたいな感覚はありました。
『MATAR O NO MATAR』は、ミュージシャンが日替わりで出演する『E/G』という私のソロ作品の延長線上で、BABY-Qでやったらどうなるだろうという企画です。これまでにワーク・イン・プログレスでつくり込んできた作品を、全然タイプの違うミュージシャンと日替わりでやったら、どのように違う作品として見えるのだろうという興味がありました。こういった企画を作品と呼んでいいと思うんですが、本当に音楽にやられて、私たちが負けてしまうかもしれなかった。信頼できるミュージシャンに頼んでいるからそれは絶対ないんですが、一か八かみたいなところがありました。
- 秋葉原事件の犯人の青年は、所謂“同族殺し”としても大きくフォーカスされましたよね。情報の整備だけがどんどん進んでいく中で、テレビをつけたらショックな事件が見たくも無いのに目に入ってくるけれども、本当に知りたいことこそが手に入りにくく、大切なことこそ情報網に絡まって手元に届かない。こういった社会の状況において、ダンスという身一つを使った表現にはとても可能性があると思います。もっと人と接していればああいう事件は起こらなかったんじゃないでしょうか。『E/G』も『MATAR O NO MATAR』も、セッションというある種とてもわかりやすい他者とのぶつかり合いが、当たり前のコミュニケーションの形として提示されていたといえます。
-
そう、メールですら届かないように、今はコミュニケーションが成り立たない。舞台は生だから、それはいつも考えながらやっています。その現場に来てもらって生で感じてもらうということが一番大切。いくら映像で見て良かったといっても、それは絶対に違う。生で感じて心震わせ、そこで息を飲みながら観ている自分というものが大事だと思います。
- 大阪時代に話を少し戻しますが、アイホールでの「take a chance projects」に参加された3年間について聞かせて頂けますか?
-
2001年にアイホールに直談判しに行ったのは自分の企画だったんですが、その作品を観たアイホールのディレクターをされていた志賀玲子さんに声を掛けていただき、Aアイホールが立ち上げた「take a chance projects/一か八かプロジェクト」という、若手に3年間劇場を開放し、予算もつけるので好きなことをやってみなさいという企画に参加することになりました。それが私にとってすごく大きかった。自分の土俵がなかった分頑張ろうとしていたところに、そうやって会場と資金を提供してもらって、つくりたいものを作ることができた。
最初の1年目というのはやはり模索状態でした。BABY-Qは当初3人で構成していたのでそれぞれのイメージが喧嘩してしまったり。1回目は『REMroom』という作品をやったのですが、それをやった後に私以外の2人が「ちょっと休憩したい」と。「BABY-Q、解散の危機か!?」という自体になったのですが、それを志賀さんに相談したら「それは東野さん自身が演出家として、一度やってみなさい」と言われ、続けてやることになりました。その時に自分の表現したいことをよく考えたんです、「何故、機械なのか」とか。それで出来たのが『←Z←・ Z 滑稽な独身者機械』。そして3年目につくったのが『ALARM!』でした。
この3年間は修行のようなものでしたが、こういった環境が私やBABY-Qを育ててくれたと思います。『ALARM!』は、最初は15分の作品だったのが1時間になり、アワードのために25分につくり直し、アイホールで最終的な作品にして初演しました。2004年から2005年にかけてのことですね。『REMroom』『独身者機械』『ALARM!』の3作品は私の成長過程そのものというか、模索していたものが確信に変わっていった時期でもあります。
- その頃に模索していたスタイルというのは、3年間でどのように変化していきましたか?
-
最初は自分が何をどういいたいかというのがはっきりしていなかった。踊りというものはずっと長い間続けていたので、踊れる自信はあるんですが、どのように踊っていいかわからない時代だったというか。ただ単に踊るだけでは駄目な時期になってきていて、それをどう自分で表現したいのかということを必死で探しました。
BABY-Qを始めた時から「人の面白み」をどうやって演出していくかという部分で作品を成立させようとしていたんですが、最初の頃は荒くれだった感じで。やりたいイメージを無理矢理なんとかしてしまうような、空回って足踏みしているような、その場所でずっと全速力で走っているような感じがありました。いつも半年がかりで作品をつくっていたんですが、3作品目の『ALARM!』からワーク・イン・プログレスという方法を取り入れて、1年半くらいの感覚で徐々につくっていった。シーンがどんどん入れ替わり立ち替わり色んなイメージをつくっていくのですが、作品のコアな部分は変えたくないと思っていたら、やはり変わらなかった。それどころか自分の作品のテーマがもつ世界観というものが明確になっていった。それで、その世界観は間違っていないという確信が生まれた。「この作品はこう踊りたい」という、最初に降って来た感覚が一番大事ということに気付いて、それを煮込んだり省いたりという作業をずっとしていても、大事なシーンはこれだなというのがわかるようになってきたんです。
自分は間違っていないという思い込みでもあるんですが、格好良く言えば確信。思い込むということは大事なんだなと思いました。人がどう思おうが、どう感じようが、「私はこうなんです!」と、今は作家として言えるというか、3年間の中で強くなったという感じです。
- 作品を作る時はビデオに撮ったり舞踊譜を書いたりするのですか?
-
ビデオは全然撮らないんです。ビデオを見るのが嫌で。構成も最後まで悩んで、シーンを入れ替えたりします。『GEEEEEK』なんかは、この間の韓国での公演ですら入れ替えました。ダンス作品なので抽象的でいいんですが、私の中では物語があって、それをやる側全員に納得してもらった上で舞台に立ってほしいと思っています。
何がどうなってるかというのはパッと見ただけでわからなくていいんだけど、このシーンはこういう意味があってこうなるから次のシーンに繋がるという、自分たちの中の一本の筋みたいなものが大事。それが共感できていないとだめですね。すごい細かい間やシーンの転換といった作品の流れはそういった共有の感覚で構成していく。でも、これは自分にとっての課題ですが、BABY-Qで作品演出する時のスタイルがちょっとパターンになっているので、今はそこを模索していきたいという時期ですね。違う角度から、作品をつくっていこうとしています。大きな規模じゃないとしても、私が出ない作品をつくるとか。
- 音楽のセレクトはどのように? 流れのベースになっているのですか?
-
昔は音があっての作品というものもつくっていましたが、最近は作品の世界観を音に物語らせるということが多いです。音の世界を大事にしているというか、音に対しては神経質になっている。舞台では視覚の次は聴覚だと思うんですよ。作品の中で音がつくる世界観を大事にしていて、音に影響されて出来上がるシーンも多いです。それに合わせて伴奏として踊るというよりも、音が空間を構築していく感じ。イチニサンシ、ゴロクシチハチは一切ないです。
ダンサーの踊りもメインではない。同等なんです。ダンス、美術、音、映像、照明、舞台空間、衣装、ビジュアル、情報、全部同じレベルで存在してほしい。だからカンパニーの中に、映像作家、音楽家、衣装さん、ビジュアルアーティストがいる。DIY。そのほうが確実なんですよね。私が創造することを確実にわかってもらえるというか。外に発注すると、思ってもいないデザインがあがってきても遠慮なく「いや、ちょっと…」って言えない。そうじゃなくて、「それ違うから、もう一回やり直してみようか」と。いつも一緒にやっているから自分のイメージにより近づけることが簡単にできる。それは作品だけではなく日常生活においてもそうで、ちょっとしたセッションだったり、コミュニケーションだったり、私がお母ちゃんと言われる由縁なんですけど、「ちょっと、ご飯食べてないんだったら、うちで食べて帰る?」とか(笑)。「しんどそうやったから、ちょっと様子見に行ってみるわ」とか。だから、みんな東京まで出て来てくれたと思うんですけど。だから、劇場があって上にみんな一緒に住んでいるアスベスト館みたいなのが理想ですね。最初は倉庫を借りてそういう場所をつくろうと思っていたんですけど、そんなお金なんかなくて…(笑)。スタジオをつくれただけでも幸せですね。 - 東野さんが他者、主に音楽家と色々な場所で異種格闘技的なセッションを行うということは、ダンスとは異なる表現との交わりを求めての本能的な行動なのではないかと思います。それはダンスも含め、既存のジャンルという囲い込みに飽き飽きしているから起こる欲求なのでしょうか?
-
私自身、刺激を受けるんですよね。想像のつかない自分になれるというか。知っている曲だとわかってしまっているから、そうではない、その瞬間にしかない1回限りの状況に身を置くことで、自分がどうなるのかということに興味があるんです。「大いなる私自身」の探求というか、研究だと思っています。「よくそんなに色々と出るね」と言われるんですが、私自身は全く苦じゃない。高円寺にある「円盤」というお店のたった二畳しかないスペースでも、私に何ができるのかと考える。いってしまえば縛りのある中での稽古というか。「私そんなところじゃできないわ」じゃなくて、そういう状況で生まれるテンションに出会いたい。それが凄い稽古になっていると思う。知っている踊りをやりたいんじゃなくて、もっと自分にあるはずの何かを、ないかもしれないんですが、その状況で生まれる何かを自分に経験させてあげたい。
それって、一人でスタジオに籠っていくら稽古してもなかなか生まれてこない。私は基本のテクニックや基礎レッスンを非常に大事にしていて、バレエレッスンや自主稽古をきちんとやって、つま先まで細部のコントロールができた上で、後は気持ちが全て。そこからどんな踊りが生み出せるのか。身体が利いている分、気持ちを表現できると思うんです。
即興に関しては、そこにどれだけの感動があるか。人前でその瞬間にしか起こらないことに惹かれる。セッションしている時の気持ちには日常ではなれないですから。日常では絶対になれない酷い気持ちとか、至福感とか、悲しくて辛くて大泣きしたりとか、それだけの心の動きというのが人前でやる瞬間にしか起こらないというのが面白いかな、と。それを見てほしいなというのはあります。
- 主に音楽の現場では煙巻ヨーコという名義でやられていますが、そこで状況論的に色々と体験される中で、東野祥子名義の活動やBABY-Qの活動にどのような影響を与えているのでしょうか?
-
煙巻の場合は無責任でいいというか、東野祥子でやる場合は抱えている責任というものがやはりあって。BABY-Qも然り。煙巻はもっと悪いというか、人のスカートめくって逃げるみたいな酷いことを無責任にできちゃう。かわいらしいですけどね(笑)。何が起こってもヘヘッって感じでいいかな、と。
- 気持ちの切り替えがはっきりしている分、煙巻ヨーコの行動は東野祥子の作品づくりには影響しない?
-
いや、すごい影響していますよ。そこで貰ってきた刺激みたいなものや引っかかった自分の気持ちというものが結局作品に出てくる。煙巻の現場が、私にとって良い稽古の場、発見の場になっています。スタジオで悶々と稽古をするのも大事なんですけど、本能的にやっちゃっている煙巻は、自分が成長していく過程としては必要だなと思う。私自身そんなに畏まらず、自由に、気楽に、伸び伸びと踊れる状況でもあるし。
- 2007年にUPLINKで、煙巻ヨーコが蛍光灯を演奏する美術家の伊東篤宏と、壁画づくりやライブペインティングを行うアーティストの鈴木ヒラクと行ったライブセッションがありましたね。これはわかりやすい例ですけれども、本来噛み合うはずがないであろう全く異なる表現を用いる三者が、セッションを成功させました。一回性の強い現場においてセッションが成り立つか、成り立たないかという基準に関して、考えることはありますか?
-
ある。即興って演者同士のコミュニケーションがちゃんと成り立っていないと絶対失敗すると思います。行き過ぎるとどうしても独りよがりになっちゃう。そういう場合はオナニーしている感じです。ちゃんと相手がいるもの、しかもお客さんがいるものだから、行き来があって、ちゃんとオーディエンスに届けるという作業をしないと。即興を二人だけでやっていても駄目で、二人がやっていることが人に向かって届くところまで面倒見ることが必要というか。そうじゃないと、即興のセッションでお金取ったらあかんと思う。
- 即興でやる場合であっても、共演者とは事前にきちんと話し合うものなのですか?
-
そう、世界観を共有しないと。全く知らない人とはできないですね。何を出してくるのかわからない人とは。その人の特徴とかもっているものを理解し、共鳴してからやりたい。そうでないと、なかなか面白くならないですから。基本的に誰とでもできますけど、でも合わせ過ぎても駄目。あるところで裏切って仕掛けるとか、外すとか。昔は合わせようとしがちだったけど、慣れてくると即興の中で自分自身がわかってくる。激しいから激しく合わせるとか、そういうことでは絶対ない。気持ちはグワーって上げられるんだけど、そこで「違うことしてやる!」みたいな闘いでもあります。
- 今後、誰とやりたい、何処でやりたいという希望はありますか?
-
もっと知らない人とやりたいですね。日本だけではなくて。イタリアに呼ばれて行った時は、「現地のミュージシャンとやりたいです」とリクエストしました。そうしたら向こう側が「この人とやったらいいんじゃない?」と組んでくれて、その人と作品をつくってイタリアを回りました。フランスで、パーク・イン・プログレスといって、各国から集まった色々なアーティストが公園でパフォーマンスを行うという企画があった時は、チェコのミュージシャンと一緒に作品をつくったんですが、次の年に呼んでくれて、チェコの国内とハンガリーを回るツアーを企画してくれた。一人の場合はノリがちょっと音楽寄りなんですけど、パッと行って、作品つくって、それで回るみたいな。フランスのアーティストとも同じで、来年の5月と10月にスペインやノルウェーでやりませんかという話があります。
知らない人の場合、事前に音を聴いて「ちょっとこの人は…」みたいなのもありますが、納得できた場合はお互い「初めまして」で始めて、2日クリエーションして作品にする。片言の英語でやってみる。それでも出来るんだよね、身体だから。踊りだからね。そういうことをもっとできたらいいなと思います。
- 海外の話が出たところで、海外でのこれまでの活動についてお話しいただけますか?
-
初めて海外に行ったのは、昔、先生のところにいた時で、中学校の時と高校1年生の時に文化交流としてパリとロンドンへ。先生のアシスタントとして行って、劇場で着物風のものを着せられて、モダンダンス!みたいな(笑)。その後は、ボーカルとダンスを担当していた「drill chop nine」というバンドで、2003年頃にシカゴとニューヨークへ行きパフォーマンスをやりました。
BABY-Qとして呼ばれて、正式に公演をやった最初は2005年のニューヨークとフランスです。BABY-Qは正統なダンスカンパニーの呼ばれ方からは外れていて、音楽寄りのフェスティバルに呼ばれることが多いんです。2007年に行った南仏ニームは、日本の色んなミュージシャンが呼ばれるフェスティバルだったし、今年行ったメキシコも音楽のフェスティバルでした。ダンス・フェスティバルという意味では、この間の韓国と2005年に行ったフランスのアンギャン・レ・バン、2006年のシンガポールでの「da:ns」の3つ。
2006年のイタリアのツアーの時は、遺跡の前とか外でもいっぱいやりました。イタリアでは「Geek」という名前を付けて、色々な場所で踊ったことで『GEEEEEK』という作品にまとまっていったところがあります。最近どんどんワーク・イン・プログレス手法というか、1つのイメージを掴んだらそれを2年周期で育てていくという風になってきている。言いたいことがたくさんあるというわけではなくて、『ALARM!』以降は自分の中に生まれたイメージが自分にとって何なのだろうか、これをどうやって伝えようかと探していく行程を大事にしています。これが私のつくり方なんだなと思う。
後は、海外公演の場合、劇場の機構によってできることが全然変わってきます。私は「劇場がこうだったら、こうしたい」と思うタイプなので、ここだったら後ろから映像打ちたいとか、同じ作品でもどんどんつくり変えて、その機構の中で一番いい方法を見つけてやりたい。日本の中でもそうなんですが、それでいちいち図面を書き直してもらったり。でも、その方がやりたいことが伝わるし、より良くなる。
- BABY-Qの海外での公演のリアクションはどうでしたか?
-
リアクションはどこの国でもすごいです。カーテンコール5回みたいな。日本じゃ3回くらいが限界ですけどね。向こうの人って反応が素直なんですよね。韓国でもそれを感じたな。日本の人は周りの人が拍手しないとできないとか、笑っていないと自分も笑えないとか、シャイじゃないですか。後で「良かったよ」じゃなくてその時言えって(笑)。
私たちの作品ってわかりやすいところがあると思うんですよ。コンテンポラリーなものよりは具体的なイメージというものがちゃんとあるから。普段からダンスにふれていない人でもわかってもらいやすいというか、そっちを目指しているところもあるし。スノッブにつくる方が簡単だと思うんですよね。パッと浮かんだアイデアに振り付けして踊ってというのは、上手いダンサーを使えばできそうな気がしますが、そうではなく、より身近にあるものを舞台上に上げる方が難しいと思います。
- 今後の海外公演の予定は?
-
1月のジャパン・ソサエティーを皮切りに、2月末までアメリカでの『E/G』ツアー。音楽のカジワラトシオと映像のROKAPENISと一緒に行きます。3月にはBABY-Qで2回目のニームへ。後、今話が動いているのが5月のスペインです。これはフランスのアーティストとつくったものの再演という形で。それと10月にノルウェーへ。ノルウェーでは『ALARM!』をやってくれと言われていて、また新しいバージョンにしたいと思っています。作品は好きだし、もう一度やり直してもいいかなと思っていたからちょうど良い機会かもしれません。
- 既にタイトなスケジュールですね。
-
そう、その間にも日本での公演があり、この前、私のケガで途中から公演を中止せざるを得なかった『VACUUM ZONE』のリベンジもやりたい!
- 『VACUUM ZONE』は本当に凄い作品だと思うのでリベンジに期待しています。
- 悔しかったんですけどね。絶対にやります。
東野祥子
異色コラボが生み出すgeekな世界 東野祥子のダンスパフォーマンス
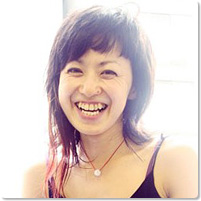
東野祥子Yoko Higashino
1972年奈良県生まれ。10歳でダンスを始め、現在はダンスカンパニー「BABY-Q」の振付家、ダンサーとして活躍。また「煙巻ヨーコ」名義で即興アーティストとのセッションを、クラブ・ライブハウス・ギャラリー・野外等で展開。2000年、Dance Company BABY-Qを結成。2004年、トヨタコレオグラフィーアワード2004にて上演した『ALARM!』で大賞の「次代を担う振付家賞」を受賞。2005年横浜ソロ×デュオ〈Competition〉+(プラス)にて群舞部門「未来へ羽ばたく横浜賞」を受賞。代表作としてこれまで、『ALARM!』『GEEEEEK』『error code』などを発表。アメリカ、フランス、イタリア、シンガポール、韓国など海外のフェスティバルに招聘され、国内外で活動を展開。2005年より東京・高円寺で、スタジオBABY-Q Lab.を運営している。
BABY-Q
http://www.baby-q.org/
聞き手:黒パイプスターダスト



『私はそそられる “I am aroused”』
「そそられる」という行為に秘める身体の感触を確かめ合うように女性ダンサーたちが踊り狂う。鏡をみ、化粧をし、男を下僕にする女たち。肌色の皮膜のような衣裳をまとい、身体を滑らす手の先に見える、本当にそそられているものとは何なのか。2008年初演。2009年8月に東京・吉祥寺シアターにて再演予定。
Photo: Yoshikazu Inoue
『GEEEEEK』
娼婦、ゲイ、小人、家畜、前と後ろが逆転し顔のないギーコなど、精神や身体にどこか奇形をもったGEEKな人間たちが、荒廃した闇の世界で危うく暴れ回る。夜行性の野生動物たちが闇の中でときに凶暴に、ときに性の奴隷となるがごとく、虚構ではない真の愛を求めてタブーの世界を繰り広げる。2006年初演。




東野祥子ソロダンス『VACUUM ZONE』
ペットボトルや工場から出る鉄くずや部品などの廃材を集めてオブジェを構築する美術家OLEO、元BABY-Qで音楽家の豊田奈千甫、VJのROKAPENISらと共同創作した東野祥子のソロダンス作品。舞台に掘られた暗黒の空洞、それがヴァキュームゾーンなのか。穴の上に吊るされた幾何学的廃棄物オブジェは轟音のたびに揺れ動き、ゴミたちとともにすべてが吸い込まれていく。
Photo: Banri
『MATAR O NO MATAR』
BABY-Q+Musiciansとして、上演ごとに異なる現代を象徴する気鋭の音楽家やDJらと即興的にコラボレーションしながら進化する作品。BABY-QのダンスとROKAPENISの映像インスタレーションが異空間を描き出す。
2008年8年の初演では、初日に中原昌也、伊東篤宏、鈴木ヒラク、L?K?O、KILLER-BONG、Kleptomaniac、虹釜太郎(DJ)らと、2日目にWorld’send girlfriend、kenichi matsumoto(サックス)、mujika easel(ヴォーカル)、置石(DJ)らとセッション。2008年9月再演では、大阪の造船所跡地にDESTROYED ROBOTの火炎放射戦車が登場するなど破壊行為へと至る。2009年には、新たな音楽家を迎えてさらなる進化を遂げる。
『ALARM!』
女の身体に流れる血と感情をえぐり出し、女性性に「警告」を発するかのような衝撃的な作品。『不思議の国のアリス』を思わせる少女と、圧搾空気で動く巨大ロボットや機械たちが闇のなかにグロテスクに共存する。ストロボ光や轟音ノイズを多用し、乱舞する東野の身体は圧巻。トヨタコレオグラフィーアワード2004「次代を担う振付家賞」受賞作。
この記事に関連するタグ

