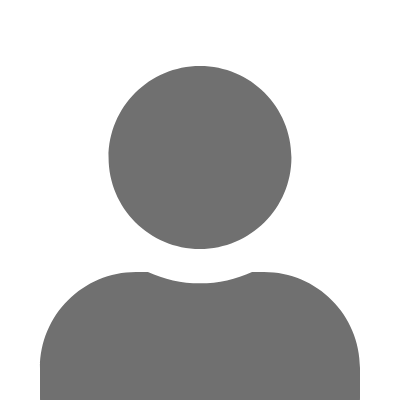喜劇に挑戦した新作文楽『其礼成心中』
- 昨年8月に三谷幸喜さんが初めて書いた文楽『其礼成心中』が初演され、今年の夏も再演されました。近松門左衛門の名作『曾根崎心中』を底本に、心中事件のその後を描いた喜劇です。近松門左衛門が曾根崎心中を書いたためにカップルが曾根崎天神の森で心中しようと殺到する。それを営業妨害だと憤る饅頭屋の夫婦が主人公で、近松まで登場します。文楽では珍しく、観客がどっと笑っていてとても印象的でした。三谷文楽の浄瑠璃はこれまで語って来た作品と比べてどこが違っていましたか?
- チャリ場のように話の一部分が面白いというのはありますけど、文楽は基本的には全部悲劇です。そもそも喜劇というものがレパートリーにはないのでそこは大きく違います。
- チャリ場というのは、例えば、毒キノコを食べて笑いが止まらない様子を、様々な笑い声で太夫が演じるといった滑稽な場面のことですよね。悲しい話の中で、こんな笑える場面が入ると、緊張が解けてほっとすると同時に、後に続く悲劇性が際立ちます。
- そういう芝居の一部として滑稽な場面を語ることはありましたが、全編が喜劇のものを語るのは初めてだったので面食らうところもありました。もちろん三谷さんは喜劇作家なので、当然、喜劇になるとは予想していましたが、どういう風に表現すればいいのかわからないことも多くて、稽古の時に三谷さんからいろいろ教えていただきました。
- 具体的にはどんなアドバイスがありましたか。
- 例えば、饅頭屋のおやじが心中志願の若い者に「達者でな!」というセリフがあるのですが、そこはもっとおちょくっている感じで言ってくださいと言われました。確かに本気で言ってるんじゃないのは台本を読めば分かります。でもどこまで軽く言えばいいのかがわからない。文楽では必要以上にふざけた言い方はしないので。自然に語って、真面目に語ってそれが面白い、というのが多い。師匠には「演者がふざけたから面白くない。真面目にやるのが面白いんだ」と言われます。それに我々は声の商売ですから、変な格好をするとか見た目でおかしいことはできない。お客さんを笑わすのは難しいと思いました。
- では、古典の語りとはかなり違ったわけですね。
- うーん、古典とそんなに違うということもないのですが….。一番違ったのはスピードかもしれません。三谷さんから、速く、テンポを上げて語って欲しいと言われたので。最初に舞台に登場する心中志願の娘は大店の娘なので、好きになった使用人と心中しようとして仮にどれだけ切迫していても、文楽では絶対に早口では話さない。それを、三谷さんは「速く、速く」と言う。三谷さんの台本は字数が多いので、今回の『其礼成心中』を古典のテンポでやったら多分4時間ぐらいかかったのではないでしょうか。初演のDVDを観たのですが、そうしたら間の開け方が足りなかったりして、速いのではなくせわしなくなっていました。今年の再演ではその辺りの工夫をしています。
- 古典作品は今ではもう使われない江戸時代の大坂の古い言葉で語りますが、三谷さんの台本は、現代口語で書かれています。その言葉を語るには工夫が必要でしたか。
-
そこは文楽の常識というものを、ちょっと破らなきゃならなかったところです。それと、いわゆる横文字、江戸時代にはなかった外来語がでてきます。例えば「パトロール」という言葉。三谷さんからは、ミスマッチでお客さんが面白がるから、強調して語ってくれと言われました。
そもそも文楽には演出家がいません。でも今回は、演出家がいて、しかも本を書いた本人の演出を受けるのは初めての経験でした。ちなみに文楽の場合は、普段の稽古がそのまま一種の演出を受ける場になっている感じです。師匠や三味線弾きが、「登場人物の距離感がないから、言葉を言う時は距離感を出しなさい」「こういう気持ちで言いなさい」とか、稽古で直してくださる、注意してくださるのがいわゆる演出ということになります。 - 演出家がいるというのは、やりやすかったのでしょうか。
- やっぱりやりやすいですね。ましてや作家本人なので、作家の意図を説明してもらうことができます。昨年は何せ初めての試みだったので余裕がなくて、何しろ喜劇だから笑うところは笑ってもらわなくちゃいけないけど、自分の語りで白けたらどうしようと心配しました。それでは三谷さんの台本を太夫が生かしてないということになりますから。一度も文楽を観たことのない方もお客さんでいらしているし。客席からいい反応があったので、正直安心しました。
- 文楽に限らず、日本の古典芸能では何日も舞台稽古をして作品を作るようなことはしません。こう演じる、こう語るという型があるので、日頃練習を積んでいれば見応えのある舞台をつくれるため、上演前に出演者が集まって、数回合わせるだけです。三谷文楽は全くの新作ですが、稽古はどのように行われましたか。
- 初演のときは、6月の大阪・国立文楽劇場の公演中から稽古していました。義太夫の場合は台本だけじゃイメージが分からないし、曲がないと稽古できない。三味線の鶴澤清介さんが作曲したのが6月ぐらいだったので、曲ができたところから仮録音してもらってそれに合わせて公演の合間に稽古をしていました。それで、浄瑠璃と三味線の合わせを1週間ぐらいやって、人形さんも入れた稽古を3、4回やって、東京での初日前に2日ぐらいやりました。
- 三谷さんは文楽の専門家ではありません。皆さんのほうから三谷さんにアドバイスをしたことはありますか。
-
曲は、清介さんの意向を反映していると思います。文楽らしさの出る泣き笑いみたいな場面も清介さんから提案があったと聞いています。
それから、人形遣いはいろいろ三谷さんとディスカッションしたようです。人形の動きについての要望があったのに対して、「それじゃあ文楽ではなくなるのでできない」とか、吉田一輔くんが「我々にとって人形は道具じゃないんです」と名文句を言ったとか(笑)。文楽以外のところで作った人形を使って欲しい、水で人形を濡らしたいなど、いろいろ要望があったらしいのですが、人形遣いとしては「文楽の本公演で使っている人形で、本公演でやれるような新作をやりたい。物珍しいのではなく、文楽の枠で面白いことをやりたい」という気持ちだったのだと思います。
でも、人形が淀川の中を泳ぐ水中シーンなんて、やっぱり文楽の人間では思いつかない発想だと思いました。三谷さんのすごいところです。稽古の時に三谷さんに「できますか?」と聞かれて、「じゃあやってみます」と。「そうそう、それです。それでいきましょう!」となったようです。 - 新作を演じたことが、古典を語る時に生きる点はありますか。
- 我々はどうしても自分たちの凝り固まったものの見方をしているので、文楽を違う目で見つめるということに関しては、新作の上演はすごくいいことだと思います。でも、技術的なことで何かが身に付くかと言われると、それはありません。古典で身に付けたものを新作に応用できることはありますが。
- 8月の大阪公演では、『瓜子姫(うりこひめ)とあまんじゃく』を語りました。1955年の初演ですから、半世紀は経っていますが、劇作家の木下順二さんが民話をもとに書いた口語体で語る新作です。三谷文楽の経験が生かせたのでは?
-
『瓜子姫』は竹本越路大夫師匠の立派な模範演技があるので、古典をやるのと同じように、師匠の言い回しをなぞります。自分の工夫で何かを変えるのは、文楽ではあまり良くないことです。過去の偉いお師匠さん方がいろいろ考えてきたことは、我々が小手先で思いついたこととは全然違いますから。形をなぞっていく中で、やる人が違えば個性は自ずとでてくるということです。自分なりの何かプラスアルファが自然に出て来て、それぞれの演者の何かが反映されていくのが古典の演劇だと思います。
13歳から歩き始めた太夫への道
- 呂勢大夫さんの芸歴は何年になりますか? 東京出身ですから、文楽の東京公演は年に4カ月しかないので観る機会も少なかったと思います。ご両親が文楽ファンだったのでしょうか?
- 始めたのは13歳ですからもう30年以上です。最初に文楽に連れて行ってくれたのは親で、こういうものがあるということを教えてくれました。祖父母は歌舞伎が好きでしたから、そういう下地はありました。かといって両親が文楽好きだったわけではありません。
- そもそものきっかけは何だったのでしょう。
- NHKテレビが放送していた連続人形劇の『新八犬伝』を観て、人形劇が好きになりました。当時は私だけではなくて、子どもたちはみんな好きだったのではないでしょうか。
- 人形作家の辻村ジュサブローさんの人形は、子ども向けのかわいい人形とは違って、登場人物の性格が表情に出ていて、とても魅力的でした。物語も江戸時代の作家・曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』をもとにした活劇で、大人も夢中になっていました。
- 親がどう思ったかわかりませんが、情操教育として、人形劇が好きなら文楽というのがあるよ、と連れて行ってくれた。そうしたらハマッちゃったんですね。内容は分からないんですが、最初はやっぱり人形がすごいと。元々音楽も好きだったので、『三番叟』の曲が良いなあと思いました。それで劇場の帰りにレコード屋に連れて行ってもらったら、『三番叟』のレコードを売っていた。それが人生の誤りだったんです(笑)。家で聴いているうちに、三味線をやってみたいと思いました。
- 人形劇が好きになったとしても、文楽をやりたいというのは珍しい少年だったのですね。
-
やってみたいと言っているのを祖母が聞いて、国立劇場に勤めていた知り合いに「うちの孫は文楽が好きだ」と話をしたようです。そうしたら、文楽の後継者を育成する養成課の方を紹介してくださった。その方が、「文楽の人に会わせてあげるよ」と楽屋に連れて行ってくれて、たまたまいらした豊竹呂大夫師匠に会いました。
その頃、父の転勤で富山県に行くことになり、養成課の方が「義太夫をやるなら最初は地歌をやるといい」と、富山にいる地歌の先生を紹介してもらった。富山にいた2年ほど、地歌と三味線を稽古しました。小学生の男の子が女の人ばかりの稽古場に通う。みんなにちやほやされてすっかりいい気持ちになりました(笑)。
東京に戻って呂大夫師匠のところに行ったら、「まだやりたいのだったら、三味線弾きの鶴澤重造という師匠が東京に住んでいる」と紹介していただいた。重造師匠はその頃80歳ぐらい。引退されるちょっと前で、新しい人は教えないと言っていたそうですが、有り難いことに引き受けてくださった。
それで、四谷の師匠の家に学校帰りに通って三味線と語りの両方を教えていただきました。今みたいにテープを聴いて覚えてこいというのではなくて、お師匠さんが1回やってくれて、2回目は一緒にやって、3回目は一人でやるという、昔風の稽古でした。まずは師匠の物真似です。子どもは何も考えないから、人に言われたらその通りにやれる。だから子どもの時からやるのは、良いことだと思います。 - 昔ながらの稽古をした、最後の世代ではないでしょうか。
- そうでしょうね。重造師匠に教えていただいたのは、十曲ぐらいだったと思います。それも、少しずつ。子どもには難しい『袖萩祭文』や『絵本太功記』も一段まるごとやってもらいました。今思えばですが、曲を覚えるということじゃなくて、義太夫がどういうものか、そういう曲を稽古することによって、構造を教えてもらっていたのでしょうね。
- その構造というのは、どういうものですか?
-
表現の仕方はいろいろあるけど、いわゆる常識というものがある。1つゆっくり言ったら次は早いとか。「のこるつぼみ」だと、「のこる」がゆっくりだと「つぼみ」は早くなり、逆に「のこる」が早かったら「つぼみ」はゆっくりになる。いろいろな形があるのでどちらが正しいということはありませんが、両方がゆっくりしていることはない。それから状況によって、声のトーンが変わる。立ってるんだったら高く言うし、座ってるんだったら頭下げているので低く言うとか、どんな曲にも応用できる基本を教えてくださった。
子どもだから理解できないことばかりでしたが、言われたことは何年たっても残っている。そういう稽古をしてもらったことは有り難いと思っています。今は、私が国立劇場の養成所で研修生に教えていますが、初心者に教えるのはすごく大変なんです。語りの基礎ができている後輩には「そこは違うよ」と言えばいいけど、研修生はどう語るか何も分からないので、自分が手本を示さなければいけないし、相手に通じないと思ったら通じるようにいろいろ考えなきゃいけない。ご高齢の師匠が、よく何も知らない中学生に教えてくださったと有り難く思います。 - 三味線と太夫を習って、どちらかを選ぶ時が来ます。
- 自分がどちらに向いているか分からないので、三味線も太夫も教えていただきました。でもどちらか選ばなきゃいけなくなった時に、太夫がいいと思ったんでしょうね、こんなに難しいとは知らなかったので。重造師匠はがっかりしていたと後でおかみさんに聞きました。師匠は三味線弾きにしたかったみたいです。
- 太夫になろうと、竹本南部大夫さんを師匠に選ばれます。
-
僕の声は義太夫の声としては細いんです。大音声で「わーっ」って豪快に語るものを自分の語り物にしていくタイプではない。それで周りの人も、声の質が同じような師匠のほうがいいと助言してくれました。
師匠の芸に対する姿勢等に接することができた以外に、南部師匠について何が良かったかというと、師匠のおかみさんに会ったこと。大阪の色町の出身なので、物腰が違うんです。笑うにしても、ちょっと品をつくって「おほほ」って。物言いとか、動きとかが普通の人とちょっと違う。文楽には遊郭の話がたくさんあります。『曾根崎心中』も『心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)』も遊女がヒロインです。僕らにしたら絵空事ですが、師匠のおかみさんは『廓文章(くるわぶんしょう)』のヒロインにもなっている夕霧の打ち掛けを見たとか、そういう話をしてくれる。すると全然身近さが違うんです。ああ、こういう人たちがいたのかと、イメージがつくれます。 - 南部大夫さんが間もなく亡くなって、次に選んだ師匠が呂大夫さんでした。残念ながら呂大夫さんも50代で亡くなって、4人目の師匠が豊竹嶋大夫さんですね。
-
いろんな師匠に稽古をしていただくと、ああ、こういう見方もあるのかって。自分が良いと思ってやっていたことを全否定されることもありますが。やっているうちに、表現は違うけど結局言っていることは同じだとか、全然違うこともあるとか、勉強になります。
義太夫の魅力
- ちなみに呂勢大夫さんは年間で何ステージぐらい勤めていますか。
- 本公演だけだと百三十数日間ですが、公演のない時は稽古があるので、義太夫をやらない日は十何日あるかないかですね。
- 義太夫漬けですね。
- 義太夫漬けじゃなかったら文楽はできないと思うんです。子どもの頃に重造師匠に言われました。師匠は明治の方ですが、「昔はカフェもない、映画もない、もちろんテレビもないから、夢中になれるのは芸ぐらいだ」と。そうすると深さが違うというわけです。極端なように聞こえますが、生活すべてが文楽じゃないとダメだと思うんです。義太夫の本を開いている時だけ、師匠に稽古をしてもらう時だけ、舞台をやっている時だけじゃなくて、いつも芸のことが頭の片隅にある。それくらい深く考えていないと、師匠方のような芸はできない。
- 義太夫は、一人の太夫がストーリーを進める地の部分も語りますし、声色はほとんど使わずに、女になったり男になったり、年寄りになったり子どもになったりしてせりふを言う。効果音まで表現します。また、幕が変わると、呂勢大夫さんが語っていた若い娘を、次は全然声柄の違う太夫が引き継いで渋い声で語ったりします。それを当然のように観客は受け止めます。文楽を見慣れない人には不自然なことかもしれませんが。
-
太夫が入れ替わった時は声の印象が違うなと思うかもしれませんが、聞いていると違和感がなくなるのが文楽です。若い娘だから綺麗な声でなければいけないということもなくて、だみ声であっても、技術がある人が語るとかわいく聞こえる。声が綺麗、汚いじゃなくてかわいらしく聞かせるのが芸です。観客は段々芝居の世界に入っていって、声の違いは忘れちゃいます。
せりふについては、まずはどういう人物であるかを頭に描けと師匠方はおっしゃいます。たぶん現代人に一番分からないのは身分の違いでしょうね。同じ娘でも町娘と大店のお嬢さんでは違います。その違いをどうイメージできるかです。
義太夫は、つくり声はいけないというのが大前提です。女を語る時は女らしい声をつくるなんてことはしません。自分の持ち前の声で語る。地声という意味ではありませんが、自分の声で義太夫の発声をマスターするんです。それから、他の日本の伝統音楽に比べると義太夫は音量が大きいですね。音域も広いというか、色んな声を出さなければいけないので、修業してバリエーションを増やさないといけない。
昔の人は「声修業」と言いましたが、声が細い人は声を太くするとか、がらがら声しか出ない人は綺麗な声も出るようにするとか、そういう技術を学びます。どうするかというと、加減をしないで声を目一杯出せと言います。自分の持っている力をすべて出し切って語る。そうすると声が嗄れる。わざと潰すのとは違います。一生懸命やったことによって声が嗄れる。嗄れた声を治しながら稽古をしていくと、段々声に幅が出てくる。そういう作業をしないと義太夫の声にならないといいます。かばって潰さないようにやるのではなく、目一杯声を出す。そして何かをマスターしていくものだと師匠もおっしゃいます。 - 呂勢大夫さんも同じようなことをして声を作ってきたのですね。
- それが求められているのですから、やらないと怒られます。三味線で叱られる。『天変斯止嵐后晴(てんぺすとあらしのちはれ)』をやった時に、三味線は鶴澤清治師匠だったのですが、語っていたら途中で三味線に突然力が入って、すごい迫力でした。終わって舞台裏に回ったら「休憩するなら楽屋でして」って言われました。自分では一生懸命やっているつもりで、もちろん手抜きなんかしていないのですが、師匠は足りないと言う。私はこれくらいのテンションで演奏しているんだ、お前は足りないぞって教えてくださった。目一杯やって、極限まで行って、だんだん力が抜けてくる。力の抜き方が分かって来る。それは、行くところまで行かないと分からない。行く前に止まっちゃダメだということですね。
- 極限に達したかどうかは、自覚できるものですか。
-
自分ではマックスのつもりだけど、足りないと言われることのほうが多い。義太夫というのは、迫力です。先人が皆そうなんです。声が大きいという言い方はおかしいですが、スケールが大きいというのが義太夫のひとつの条件なんです。四畳半で聞いて上手い浄瑠璃ではダメ。大劇場の後ろの席にも同じぐらいに聞こえるような舞台にしなければいけない。それが義太夫という音楽の特徴なんです。この大きさがなかったら義太夫ではないんです。
よく「寸法」と言うんですが、師匠と私とでは芸のスケールが違っていて、間が違う。同じ5秒だとしても、その5秒がどう聞こえるかが違うんです。師匠はグッと詰まっているのに、僕らの5秒は長く聞こえる。でも、上手にやれば長く聞こえない。物理的な大きさ、長さではないんですね。 - ほかに、義太夫ならではの特徴はありますか。
- 誇張ですね。表現がオーバーなんです。びっくりするにしても、実際はそんなことないのに、人形はのけぞるように動きますし、太夫も「ヒエ〜!」って声を上げます。びっくりしていることをお客さんに伝えるためにはオーバーにやらなきゃいけない。人形も、三味線も、太夫も、作品の内容をお客様に伝えるのが一番の目的なので、そういう手法を取っています。
- 太夫にとって一番身近な存在は三味線だと思いますが、どちらに主導権があるのでしょうか。
- 立場によって違いますね。大先輩の清治師匠が弾いていれば、僕の語りを師匠が引っ張るのは間違いない。後輩の三味線で語れば、僕が引っ張ることになる。理想は拮抗していることでしょうね。清治師匠にはもちろん引っ張っていただいているんですが、「自分の持っているものを全部出して思いっ切りぶつかってこい」とおっしゃる。とても拮抗しているとは言えないですが、そういう気持ちで語りなさいということですね。
- 人形の動きに合わせて語るということはありますか。
-
人形を見て語ることはありません。例えば亡くなった名人の吉田玉男師匠でも私の語りに合わせて遣ってくれる。若い人はチャチャチャッと人形を遣っちゃいますが、玉男師匠は寸法が、スケールが大きいので存在感が違います。名人と一緒だと、舞台の方から自然とオーラが来ますから、合わせるつもりはなくても、自然に合っていくんじゃないでしょうか。
うちの嶋大夫師匠はよく「時には人形を見て、浄瑠璃を聞きなさい」と言います。勉強のために舞台裏で師匠の浄瑠璃を聴いているのですが、たまには人形の見える所に行って、浄瑠璃を聴きながら人形の動きを見なさいと。人形はこんな動きをしているんだというのを見ておけばイメージとして湧いてくるし、自然にいい語りができるようになるということですよね。 - 呂勢大夫さんは、どういうところに注意しながら稽古をしていますか。
- 稽古も大事ですけど、やっぱり舞台が一番勉強になる。舞台でいい師匠に弾いてもらって、途中でオエーっとなっちゃってうまく語れないと死にたくなるわけです、恥ずかしくて。終わった後で考えるわけです、どうしてそうなっちゃったんだろうって。息の継ぎ方が悪かったんだろうか、気張ったからだろうか、前の言葉の言い方が悪かったから失敗したんだろうか、と考えるわけです。舞台で練習しているわけではないですが、真剣勝負の場で体験して身に付けていくのが一番の修業です。
- 急遽代演することも多いですね。
- 普段から師匠の舞台を聴いておかないとできませんが、それは勉強ですよね。聴いていれば、ある程度の形は語れるんです。代演の場合は、普段やっている役より重い役が多いのですが、声をかけてもらったら逃げ回っていちゃだめです。やると、師匠たちがどれだけ大変か身を持って思い知る。1回ぐらいなら極端に言えばメチャクチャでもお茶を濁して終われますが、1カ月近く、毎日、水準を保ってやらなければならない。明日のために今日は加減するんじゃなくて、その日その日で一生懸命やる。それをできる師匠は本当にすごいなと思います。
- 太夫は60歳、70歳にならないと大成しない芸だと言われます。経験を重ねると、自分でも力が付いてきたと思いますか。
-
いやあ、それは思わないですね。やればやるほどハードルが上がっていくから、力が付いたなんて思っている暇が無い。若い頃は、元気で大きな声で語っていればそれで良かったけど、今はそれじゃ済まない。人物が語れてないとか、情がないとか、次から次へと課題が出て来る。まあ、師匠は1年生には1年生向けのことしか言わないですが、10年やっていればこれだけのことはできないと、となる。
舞台で命懸けで語って、目の前に来る課題をこなすだけで精一杯です。今だに訛を直される。文楽は江戸時代の大阪の言葉ですから、関東人には訛は大きなハンディで、まだ克服できない。いつかできるかな、なんてことを考えたら、生きていけないと思います。 - 研修生を指導するなど、文楽を次の世代に伝えていく立場になり、自分の芸を磨いていればいい状況ではなくなってきました。太夫になりたいという人は増えてますか。
- どうでしょう。三味線弾きには楽器、人形遣いは人形がある。太夫は身一つですから、正味の実力が露呈します。下手な場合は一番目立つ。太夫の研修生はいますが、どこまで好きなのか分からないです。それどころか、今は正座もできませんから。稽古で3分ぐらい正座しただけで「うーん…」って言い出す。僕らは座ってなきゃいけない職業なのに…。
- 語る以前の問題ですね(笑)。
- がっくりきます。聞けば、家に畳の部屋がないから正座をしたことがないとか。生活環境が古典向きでなくなってきているということなんでしょうね。
- 日常生活は大きく変わったかもしれませんが、文楽がテーマにしている夫婦の情愛や自己犠牲、親子の愛情などは、人間にとって普遍的なものです。
- そういうのは変わらないですよね。この前、駅で外国人の子どもがお母さんに物をねだって駄々をこねていたんですが、昔も今も、日本人も外国人も子どもの駄々のこねかたは一緒です。人間が持っている共通のものって変わらないんだなと思いました。
- 今年は9月末から約1カ月、現代美術家の杉本博司さんが構成・演出・美術・映像を担当された「杉本文楽」で欧州に行かれます。マドリード、ローマ、パリでの公演ですが、文楽の海外公演についてはどう思われますか。
-
よく言うのですが、言葉が分からなきゃ理解できないという発想はやめるべきだと思います。オペラでも、ドイツ語とかイタリア語とかが分からなくても、良い音楽、良い舞台だったら、悲しい場面なんだなとか分かります。言葉で理解しよう、粗筋を理解しようとするとつまらなくなる。フィーリングで観てもらえれば、文楽という芸能は充分楽しめると思うんです。極端に言えば、義太夫を語っている大夫の顔が面白いでもいい。分からないけど凄かった、でいいんです。
もちろん、文化が違って理解できないということもあります。悲しい話なのに人形の動きを見て笑っちゃうこともあるかもしれない。でも、可笑しいと感じるのは、それだけ興味をもったということです。反応があるということは、何か感じているわけで、それでいいんです。
舞台はお客さんとつくるものだと思っています。劇場で僕らが演じて、観客が観る。寝ている人がいるかもしれないけど、その人にだっていろんなことが耳に入っているでしょうし、同じ空間に居るわけです。海外公演はその空間が外国になるだけで、我々が演じることは国内でやるのと一緒です。それがどう受け取られるかは、場所によって違って当然だと思います。我々としては少しでも分かってもらえれば嬉しいし、興味をもってもらうことが一番です。