- なぜ、日本に帰国したのか?
- ダンサーとしてカンパニーに属してやっていくことにちょっと行き詰まりを感じていた。自分でことを起こさなければ何も始まらないという不自由さと、自分で選択できるという自由さを味わってみたくてフリーになった。振付はカンパニーに属していた時もやっていたが、受けられない仕事や、受けても時間が限られることもある。そういうシステムの中でネガティブになっていく自分がいたので、これはちょっとよくないと思った。
日本人なので、一度、日本でやってみようと。すぐにいろいろな仕事をさせてもらったが、ヨーロッパと日本ではお客さんの見方の意識が違っていて戸惑った。バレエにしてもアートとして見に行っているのではなく、有名な人が出ているという興味で見ている人が多い。それはそれで、自分なりの自信と経験を踏まえて良いものは良い、というふうに見せたいとは思ったが、自分の踊りの評価のされ方に対してギャップを感じていた。そういう状況の時に、新潟から誘っていただいた。 - 新潟の公立カンパニーとしての抱負は?
- Noismというダンスのカンパニーが新潟にいて、新潟で作品をつくって、新潟から発信していることを、一人でも多くの市民に喜んでもらえるように努力していきたい。東京はマーケットなので、そこで評価されれば可能性は広がるが、そのことが新潟での立場を楽にしてくれるわけではない。市民に作品を届けるために必要なことはいろいろとやっていきたい。
- 地元市民に受け入れられたからといって、その作品がそのまま海外で通用するとは限らないのでは?
- 東京やヨーロッパのようなダンスの先進地で自分の信じる表現(ダンス)を見せていくことに対する自信は当然ある。挫折はあるかもしれないが、そこは創作する以上は必ず通らなければならない道だし、乗り越える自信もある。逆に、新潟を忘れてはいけない、ということを自分に言いきかせている。
- とりあえず3年間の契約になっているが、芸術監督としてマネージメントにはどのぐらい関わるのか?
- Noismの公演は年2回を予定している。Noism 以外のダンスプログラムについても責任をもつが、予算に限りがあるのでなかなか難しいと思う。
自分にとってスタジオで作品をつくっている時間はかけがえのない、一番幸せな時間だ。しかし、それを得るためにはスタジオ外でしなければならないことがたくさんある。芸術監督になると決めた時に、ただ作品をつくるだけではなく、そうした仕事もやる認識でいることは新潟にも伝えた。前例のない公立カンパニーを立ち上げた限り、コミュニケーションをとらなければならないことも多いし、覚悟はしている。そうした仕組みをつくるのに3年ぐらいはかかるのではないか。 - 日本人との仕事について。
- 日本に来て一番変わったのは、日本語が使えるようになったこと。母国語が使えることで、自分が意識していることを言葉にできるようになった。実際に振り付けていく上でも、自分が何を伝えたいのか考えるのに明確に頭が働くし、作品についても言語化することでより掘り下げていくことができるようになった。それに対して、ヨーロッパにいた時は、英語もちゃんと勉強したわけではなくてイメージで覚えていたから、作品もあくまでイメージの世界だった。
振付けは自分と向き合うことだから、一旦、日本語で考えるようになった自分がいる限り、これからは誰とやるとしても、日本語で作品をつくることは変わらないと思う。だからといって日本人のアイデンティティについてアイデアとして強く意識しているわけではない。あくまでDNAレベルのことだと思っている。 - Noismではヨーロッパ的なカンパニーのシステムを目指しているのか?
- 一口にヨーロッパのダンスカンパニーといってもいろいろなシステムがある。自分が通ったカンパニーのいいところを学んでNoismに活かしていきたい。しかし、とりあえず3年後の目標としては、カンパニーがプロの集団として、胸を張って新潟で機能していると言えるようになりたいし、他に公立ダンスカンパニーをつくりたいところがでてきた時のモデルになるようなシステムをつくりたい。いつになるかわからないが、学校もつくりたい。僕も17歳でベジャールのところに行って得たものが大きかったし、教育の場から変えていくようなことができればと思っている。自分の時は、ダンスでプロになるんだったら、海外に出ていかないとどうしようもなかったが、海外に行かなくても日本で充分にやっていける、と言えるような状況づくりに貢献できればと思う。
- レパートリーについて。
- 自分の作品だけやって、自分の作品がベストだみたいなカンパニーにはしたくない。まずは、日本で見せたい海外の先達たちの作品(マスターピース)がたくさんあるので、それをダンサーにも経験させたいし、日本のお客さんにも見てもらいたい。それから外部の振付家に委嘱することも考えている。早いうちに、一度、僕以外の日本人の振付家にお願いしたい。海外では、自分と同年代の、それこそ才能がある仲間がたくさんいるので、いつかは彼らを呼んできて作品をつくりたいと思っている。また、自分が今最もヴィヴィッドだと感じている振付家を招いて、自分もダンサーとして参加したい。外部から招いた振付家に、Noismと一緒にやったからこの作品が生まれた、と言ってもらえるようなレパートリーが欲しい。
- ダンサーと振付の両立について。
- 両方ともやっていきたいが、今は作品をつくることに専念している。まだ踊りたいが、自分の踊りについて考える時は、自分のことだけ考えればいいので、エゴイスティックになる。今はそういうことに時間を割く時ではなく、自分の選んだダンサーたちと、自分のつくりたいものとの真剣勝負をやっている。Noismがある程度エスタブリッシュすれば、自分が踊りたいという欲望の方が強くなると思う。
- どのようなダンサーを育てたいか?
- これからのダンサーにとって、自分自身で動きをつくることは最低限求められる要素であって、できなければいけないこと。ダンスはどんどん進化し、新しい課題が次々にでてくるのだから、今見えていることを目標にしていてはいけない。プロのシステムでやるということは、そういう課題に対して言われる前に自分で対処するということだが、日本のダンサーにはこの意識が足りない。先生に言われたことをやればいい、言われてないことをやると逆に怒られるような教育システムの中で育っているから難しいのはわかるが、早く気づいて欲しい。
プロのダンサーというのは、自分でしかありえない、替えのきかない存在になるということ。創造の現場で、彼のもっているこれを使って何かをつくりたいという欲求を振付家に抱かせる存在になって欲しい。創作はギブ・アンド・テイクだから、振付家もダンサーから刺激を受けたいと思っている。そういう価値のあるダンサーだからクリエーションにキャスティングされるわけで、それこそ自分から出てきたものだけでつくるのなら、自分だけでやればいい。逆に僕も彼らに与えていきたいし、そういう相互の関係がもてるのがベストな状態だと思う。
それと、レパートリーに関連して言えば、マルチなダンサーになって欲しい。ダンスというのはいろいろな身体の使い方があって、今後、外部の振付家を招く場合、僕とは違う身体の使い方に興味のある人を頼む可能性が高い。その時に対応できる、そういう振付家からも吸収できて、刺激を与えられるダンサーでいて欲しい。 - 音楽について。
- 音楽にインスパイアされて振付けを考えることはよくある。マーラーの交響曲5番のアダージェットは、曲に出会ったときにすごく惹かれたが、その後、ベジャールが振付けた作品を見たのでためらっていた。しかし、曲のインパクトが残っていて、自分なりに何か創造できないかやってみようと、短期間でつくったのが「アンダー・ザ・マロンツリー」。池田亮司さんも好きな作曲家なのでたくさん使わせてもらっていて、オリジナル曲を委嘱したこともある。
「black ice」では権代敦彦さんの曲を使っている。今回はオリジナルではないが、彼に相談して送ってもらった曲が素晴らしくて、ぜひにとお願いして使わせてもらった。
音楽は直感で決めている。振付けの曲を探すときにはたくさん聞くが、普段は(聞き入って)疲れてしまうのでほとんど聞かない。 - 「SHIKAKU」では建築家と、「black ice」では現代美術家とコラボレーションしているが、今後もコラボレーションを続けるのか?
- ダンスというものがどうなっていくのかを考えると、様々な分野のアーティストとのコラボレーションは必要不可欠だと思う。ダンスは総合芸術になってきていて、演劇家や美術家とは何年も前から一緒にやっているし、音楽的にもどんどん新しくなっている。コラボレーションで新しいアーティストと一緒に創作する過程で得るものはとても大きい。ただ、作品が成功するかどうかは別なので慎重にすべきだとは思う。
僕にとってコラボレーションは作品をつくるための「模索」で、新しい可能性を見つけては壊すことで自分の表現ができあがっていく。「SHIKAKU」の時は建築家の田根剛とコラボレーションしたが、建築家として空間について感じていること、身体について感じていることをいろいろ話し合ったことがとても面白かった。ダンスと直接関係ないことでも、彼と過ごした時間はとても刺激的だった。
金森穣
29歳の芸術監督
日本初 金森穣が語る公立ダンスカンパニーの未来

撮影:篠山紀信
金森穣Jo Kanamori
舞踊家/Noism芸術監督
1974年生まれ。幼少より父の金森勢に学び、牧阿佐美バレエ団に所属していた時に才能を認められ、92年からモーリス・ベジャールが設立したルードラ・ベジャール・ローザンヌに日本人としてはじめて留学。以来、ネザーランド・ダンス・シアター?などヨーロッパを拠点に活動。2002年に帰国し、翌2003年、初の自主プロデュース作品「ノマディック・プロジェクト」で、朝日舞台芸術賞の舞台芸術賞、キリンダンスサポートをダブル受賞。2004年から新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ舞踊部門芸術監督。
https://www.jokanamori.com/
9月1日。「black ice」の稽古中に新潟市民芸術文化会館を訪れ、金森穣にインタビューを行なった。
聞き手:塩谷陽子
Noism04
2004年に新潟市民芸術文化会館・りゅーとぴあが、舞踊部門の芸術監督に金森穣を迎えて設立した日本初の本格的な公立コンテンポラリーダンスカンパニー。全国からダンサーを公募し、オーディションで10名を選考。新潟にレジデンスして活動を行なっている。6月に第1作「SHIKAKU」、10月に第2作「black ice」を発表。
新潟市民芸術文化会館・りゅーとぴあ
開館:1998年10月
新潟市が設置した、コンサートホール(1900席)、劇場(900席)、能楽堂(380席)をもつ複合文化施設。新潟市芸術文化振興財団が隣接するホール付きの音楽専用練習場の新潟市音楽文化会館を含めてトータルに運営している。演劇部門の芸術監督にプロデューサーの笹部博司、演劇部門のアソシエイト・ディレクターに演出家の栗田芳宏、舞踊部門の芸術監督に金森穣が就任している。総事業予算は約4億円。音楽部門では音楽文化会館を拠点にジュニアオーケストラを育成し、小中学生を対象にしたスクールを運営。演劇部門でも小中学生を対象にしたスクールを運営し、オリジナルミュージカル作品をプロデュース。また、全国ツアーを行なうオリジナル作品のプロデュースも行い、人気俳優をキャスティングした公演や能楽堂を使うシェイクスピアシリーズなどを発表している。

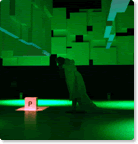
『SHIKAKU』
初演:2004年6月
若手建築家田根剛、音楽家平本正宏などとコラボレートした作品。タイトルの「SHIKAKU」は、同音異義語で「四角」「視角」「死角」「詩客」「詞客」「刺客」「資格」「詩格」「視覚」「始覚」などの多様な意味がある日本語。白い壁で仕切られた4つの部屋のようなセットを往来しながら踊るダンサーたちを、観客は自由に歩き回りながら見るという実験的な作品。暗転している間にセットが天井に吊り上げられると、何もないフラットな空間が出現するなど空間的な造形にも優れている。「SHIKAKU」という言葉のさまざまなあり様を、10名のダンサーたちが休むことなく踊り続けることによって発信する。
©新潟市民芸術文化会館

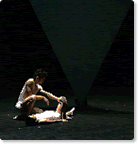
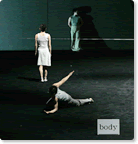
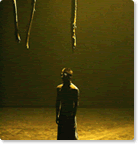
『black ice』
初演:2004年10月
現代美術家高嶺格(TAKAMINE,Tadasu)とコラボレートした作品。タイトルの「black ice」は、完全に透明な氷という意味。アスファルトの道路の上を覆う完全に透明な氷によって、下のアスファルトの黒が透けてみえることからこの名前がある。道路が凍っていることが判らず、車がスリップしたりすることから、目に見えないけれども影響を与えるものの象徴として使われている言葉。作品は、短編3作で構成されたオムニバス。高嶺のビデオアートをバックに、死を目前にした男をテキストにした「black wind」、「接地面」をテーマに特殊な映像とダンサーがコラボレートする「black ice」、ダンサーが自らの深層心理を森のようなオブジェの中で探求する「black garden」と3作ともタイプが異る。通常は滑るため絶対に行なわないが、ダンスフロアーに地絣(じがすり・舞台で使う黒い布)を敷き、完全なブラックボックスを実現するなど、この作品でも空間造形に優れた工夫が行われている。
この記事に関連するタグ

