

劇団太陽族『それからの遠い国』
(2012年6月8日〜10日/伊丹アイホール) 撮影:石川隆三
Data
:
[初演年]2012年
[上演時間]1時間50分
[幕・場数]1幕
[キャスト]12人[男6、女6]
それからの遠い国
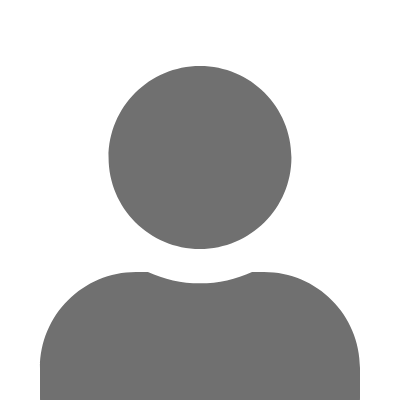
1963年生まれ。劇作家・演出家、劇団太陽族主宰。関西小劇場演劇界の旗手のひとり。1982年に、大阪芸術大学舞台芸術学科の学生で「劇団大阪太陽族」を結成し、演劇活動を始める。1990年に199Q 太陽族と改名、2001年から現在名で活動。1995年に日本を震撼させた宗教団体オウム真理教事件を題材にした『ここからは遠い国』を発表し、OMS戯曲賞受賞。社会で起こる事件や現象をモチーフに、現代人のもつ閉塞感とわい雑な人間関係を描いた作品で定評がある。特に、幻想と現実、時間と空間が行き来する舞台ならではの非日常的な演出スタイルにファンが多い。高校生などを対象にした劇作や演出のワークショップ指導者としても活躍し、北九州芸術劇場、長崎ブリックホールなど全国の公立ホールで市民参加劇を発表している。2008年から伊丹アイホール・シアター・ディレクターに就任。


劇団太陽族『それからの遠い国』
(2012年6月8日〜10日/伊丹アイホール) 撮影:石川隆三
Data
:
[初演年]2012年
[上演時間]1時間50分
[幕・場数]1幕
[キャスト]12人[男6、女6]
被災地の林道を走る深夜の軽トラックを女が呼び止める。運転手は40代の中年男・義正。女は、義正が10年以上前に脱退した宗教団体の仲間のひとりだが、実は幻影である。
かつての義正は、信仰により、意志の力で未来を切り開く意欲に満ちていた。しかし、今では被災地の廃品を夜中に運びだしては売り飛ばすうしろ暗い仕事で生計をたてていることが、女とのやりとりの中から浮かび上がる。
流されるままに生きて良いのかと女が問うと、その声から逃れるように義正は車を出す。
女の幻影が消えるや、今度は亡父の幻影があらわれる。義正の様子を心配する亡父に、工務店を継いだが長引く不況で廃業したこと、未だ独身でいることを告げる。
ふたりの妹、礼子と真理も独身で生業に就くこともなく、実家で義正と同居している。嫁いだのは長女・信子だけで、父親の生前となにひとつ変わるところがない。義正と家族は根深い鬱屈を抱えている。
軽トラックが戻ったのは、大阪にある倒産して久しい義正の工務店。以降このガレージが舞台となる。
今日は父親の十三回忌。嫁いだ長女・信子、その夫と息子。そして母方の従妹が法事のために母屋に集まっている。
長女夫妻は、父のむかしの仕事場を懐かしみガレージをのぞきにくる。息子は高校の入学祝いに買ったガイガーカウンターで、トラックの荷物を計測して遊ぶ。
姉夫婦を探しに義正が来ると、軽トラックから見知らぬ青年があらわれる。演劇活動をする妹・真理の劇団の青年である。劇団はガレージを稽古場として利用しているのだ。
言葉の端々が理屈臭い青年で、理論ばかり先走って知ったかぶりをする態度に義正は苛立つ。しかし、おそらくかつての義正もそうした頭でっかちの青年であった。
劇団の次の演目はシェイクスピアの『テンペスト』。青年は怪物キャリバンを演じる。魔法使いプロスペローにコトバを教えられ、文明の知性に目覚めるキャリバンという役どころも、かつてあやしげな教団に教えをうけた義正を彷彿させる。
続いてガレージに、マッサージ師風の女が白杖をついて「集金」に来る。女は、義正のいた教団のかつての仲間。いまは身元を隠して生活している。盲人というのもみせかけらしい。
「集金」は教団のおこした事件の賠償金で、義正は毎度、弁当代程度の金額を渡してきたようだ。
金をせびられた義正が渋っていると、再び父親の幽霊が登場し、困ってる人は助けてやれと促す。
義正は法事に呼ばれて出て行く。
父の幽霊は、白杖の女、そして法事をさぼった高校生の孫と世間話をはじめる。女は信仰のシンボルとして兎を大事に飼っており、女と幽霊は、兎にまつわる様々な伝承を少年にきかせる。
ガレージに、またひとり劇団員の演出家が訪れる。
少年は声優の仕事に興味があり、演出家が手にしている戯曲が何かと聞く。演出家は大好きな戯曲『ワーニャ伯父さん』だと答え、読んで感想をきかせてよと少年に本を貸す。
法事を終えた義正がガレージに戻ってくる。
法事のあと、長女信子に工務店の土地を売る話をもちかけられ、憤って中座したようだ。劇団員と入れ違いに、義正を追って信子たちがガレージに入ってくる。
信子は、夫の転勤に伴い、一家3人の引越し資金が必要で、工務店の土地を売って兄弟4人で4等分したい。義正は、工務店経営で父親が作った借金をまだ返済途中。家を失ってはいまの仕事もできない。二人の妹もいまだ義正と実家に暮らす身の上で、姉の急な申し出に不安を感じる。
しかし信子は、兄弟のうち自分ひとりで父母の最期を介護したことをあげ、土地を売ることを取り下げない。母方の従妹も話にはいってきて信子を後押しする。
信子と従妹の話しぶりから、従妹が工務店の土地を買う算段で、もうあらかた話がついているようだ。弟や妹の事情にまったく配慮しない姉の独断と周到さにうんざりし、義正は衝動的に家を出ていこうとする。
「俺は死ぬ。一度死んでやりなおす」という言葉に、信子は、義正が教団に戻るつもりかと早とちりする。それは外聞が悪い、礼子も真理も結婚できないのは義正があの教団にいたからだ、と信子はなじる。
義正がエンジンをかけようとする車の前に、再び亡父の幻影があらわれ、車を押し止める。義正のつらい過去、地下鉄での教団の事件のイリュージョンがあらわれる。溶暗。
数ヵ月後の工務店のガレージ。
真理の劇団の青年たちが話している。『テンペスト』の公演も終了したようだ。土地の売却の話もついて、稽古場にしていたガレージがいよいよ壊される。
白杖をついた教団の女が、義正にお別れを言いにくる。信仰のシンボルとして大事にしていた兎が死んだので、隠れ家を出るという。
義正は白杖の女に、自分が喪失したのは長い年月だとつぶやく。女は「魔法の杖をあげましょう」と、白杖を義正にわたして去る。
高校生の少年を演じた役者が、演出家にもらった戯曲『ワーニャ伯父さん』の有名な台詞を独白する。
〈生きていきましょう、ワーニャ伯父さん〉からはじまる、失意のワーニャを慰めるソーニャの励ましは、オウム事件に象徴される95年から現在までの長引く停滞のなか、その前の時代ならありえたチャンスや希望を失った者たちへの手向けである。
義正を演じた役者が、「魔法の杖」こと白杖を手に、『テンペスト』終盤、魔法使いプロスペローの台詞をいう。プロスペローは魔法に耽溺して国を追われたが、自分を追放した弟への復讐心に区切りをつける。
〈ここに私を留めようと、あそこへ送りだそうと、皆様のお気持ち次第。皆様の拍手の力で、私のいましめをお解きください〉
プロスペローの進路が観客の判断にゆだねられたように、この十余年の歳月を超えたその次は、観客自身の手にゆだねられている。
この記事に関連するタグ