Data
:
[初演年]1927年
[上演時間]約60分
[幕・場面数]2幕
[キャスト数]6人(男3・女3)
岸田國士
動員挿話
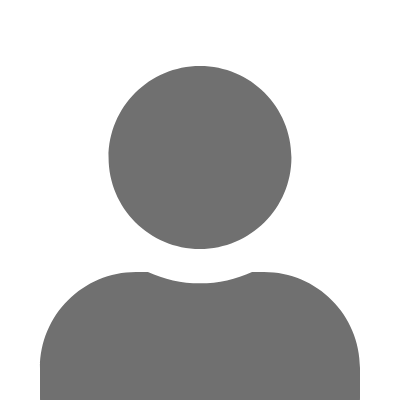
岸田國士Kunio Kishida
1890〜1954。劇作家、演出家、批評家、小説家。東京四谷に陸軍士官の長男として生まれる。幼年学校から陸軍士官学校に進み、少尉に任官、久留米に将校として配属されるが、文学への思いやみがたく、父の反対を押し切って退官、東京帝国大学文科大学に入学する。1920年には、パリへ留学し、イプセン、チェーホフ、ストリンドベリーなどヨーロッパの近代劇に出合い、演出家ジャック・コポーが主宰する小劇場ビュウ・コロンビエ座に師事して、当時フランスで盛んであった演劇純粋化運動に接する。帰国後、「演劇新潮」に戯曲『古い玩具』と『チロルの秋』を発表して注目を浴びる。左翼演劇に反対して、戯曲の文学性を説く一方、1937年には久保田万太郎、獅子文六らと文学座を創立した。台詞は美しい「言葉」でなければならぬと主張し、そのためには劇作家が、音楽を聴くように「言葉」を聴かせるような作品を書かなければならないと考えた。
第1幕は、明治37年の夏の夕刻、日露戦争に出征の命が下った宇治少佐宅の居間が舞台。従卒の太田と少佐の妻鈴子が、軍用鞄の整理など、明日にひかえた少佐の出征準備に余念がない。そこへあらわれた少佐は、馬丁の友吉を呼び寄せ、戦地への供を言いつけるが、友吉は返答を渋る。
それというのも、自分は決して戦争が恐いわけではないけれど、女房の数代が、行ってくれるなと懇願しているというのだ。数代は言い出したらきかない芯の強さがあり、どうやら友吉と結婚する時にも生きるの死ぬのという騒ぎがあったらしい。しかし、それはしょせん女の言うことだぞと釘を差す少佐は、あぶない前線にはまず出ないから、戦死するようなことにはならないと、友吉と数代ともどもに言い聞かせ、説得するが、数代は聞き入れない。立腹し、主従の縁を切ると言い残して少佐が席を立ったあと、愛するものと一日でも離れるなどということはできませんと、数代は鈴子夫人に抗弁するのだった。
第2幕は、次の日の昼頃、友吉夫婦の部屋が舞台。世帯道具がくくってあり、すっかり暇をもらう用意がととのっている風情。少佐の出立を無事に終えた鈴子が、あわてて出て行かなくても、行き先が決まるまでゆっくりしておいでと、数代に語りかける。体面上はともかく、夫人は心の底では数代の考え方に同情しているようである。
そこへ友吉が師団司令部から戻り、仲間のみんながお供をするのを見て、自分もやっぱり戦場に行くのを決心したと告げる。友吉はどうもかなり優柔不断な人物のようである。友吉の心を聞いて安心し、去る夫人。決して死ぬようヘマはしないし、世間から臆病者と指をさされるのも我慢ならないからぜひ行く、行きたいのだと言う友吉。数代は、「戦争に行くのが偉いのなら、戦争に行かないことだって偉い筈よ。さうでしょう、人を殺さないですむんですもの」と言い、あたしはあんたと一日でも離れたら生きてゆけない女だ、「うそぢゃなくってよ、今、ここで死んでみせるわ」とかき口説くのである。
どうしていいか分からなくなってきた友吉だが、隊から迎えにあらわれた太田にうながされるように着替えはじめる。ひどく失望しつつ、夫人に夫の決心を伝えてくると、去る数代。入れ替わりにあらわれる夫人が、数代は一度来たがすぐ帰ったと告げるところへ、女中よしが血相を変え飛び込んでくる。「おかみさんが、あの、井戸で御座います、奥様、井戸……」。友吉が「うそだよ、うそだよ、おれは行かないよ。行かないってばさ」と狂乱の体で悶え叫ぶなか、幕。
この記事に関連するタグ

