- ディレクターに就任されて最初の演劇祭が終わりました。トーマス・オスターマイヤーを「アソシエイト・アーティスト」に迎えて、フランスと並んで、ドイツ、オランダ、フランドルを中心に組まれたプログラムは、関係者や批評家からもたいへん評価の高いものでした。このアソシエイト・アーティストの試みについて詳しく教えてください。
-
ヴァンサン・ボードリエ(B):
毎年、異なるアソシエイト・アーティストを起用します。非常に強烈な独自の芸術世界を築いていて、私たちが作品を愛してやまない人たちを、アソシエイト・アーティストとして選びました。2004年はベルリンのトーマス・オスターマイヤーでしたが、それに続いて2005年はベルギー(アントワープ)のヤン・ファーブル、2006年はフランスのジョゼフ・ナジ、2007年は同じフランスのフレデリック・フィスバックが、すでに決まっています。毎年、アーティストを変えることで、演劇祭自体が大きく異なる表情を見せることになります。ファーブルとはもちろんですが、ナジやフィスバックとも、演劇祭の方向性についてすでに議論をはじめています。
フェスティバルのプログラムでは、アソシエイト・アーティストや彼に関連の深いアーティストの作品を複数取り上げますし、また作品だけでなく、リーディング、展示、作家や哲学者や社会学者を招いてのトーク、ディスカッションなどを通じて、アーティストの世界を多面的に経験できるようにしています。
具体的な作業のプロセスとしては、まずはアソシエイト・アーティストと基本線についての議論を重ねます。その後、具体的な内容、ほかに招聘するアーティストや作品の名前について議論します。最後に、周辺企画などもっと細かい部分を議論し、詰めていきます。プログラムの最終決定について全面的に責任を負うのは私ですが、こうして、彼らもまた私たちと一緒に演劇祭のプログラム作り、準備過程のすべてにも関わるのです。 - 演劇祭の客層は? たとえば、プロフェッショナルの観客はどのくらいの割合を占めるのですか?
-
B:
2004年の入場者数は10万人あまりでしたが、プロデューサー、ジャーナリスト、演出家などの演劇関係者は15%ほどです。大部分は普通の観客であり、フランス全土や周辺の国から、何日かの間、非常に密度の濃い演劇的な時間を過ごすために集まって来ます。とても開かれた好奇心と感受性を持っている彼らの存在が、演劇祭の豊かさであると思います。
オルタンス・アルシャンボー(A): アヴィニヨン・フェスティバルの特色の一つは、ジャン・ヴィラールによる創設以来、新作中心であり、きわめて同時代的なフェスティバルでありながら同時に、業界の人間だけでなく、きわめて幅広い観客に開かれているところにあるといえると思います。 - 2004年も来年以降のプログラムも、強い「ヨーロッパ」意識が感じられるように思いますが・・・
-
B:
起用したアソシエイト・アーティストに応じて、毎年のフェスティバルの内容も変化するので、特定の国や地域を中心にしたプログラムを意図的に組んでいるわけではありません。ですが、ヨーロッパが私たちにとっては自然な現実の枠組みであるのは確かです。2004年の演劇祭のために、ドイツの演劇人と深く接してみて、フランス演劇とドイツ演劇とのちがいに大きく驚かされました。演劇の組織化・構造化のあり方、作品の表現、俳優の役割、俳優の演技、セノグラフやドラマトゥルグの役割・・・何をとっても大きく異なるのです。これらのフランスとは異なる文化とフランスの文化を対面させ、ぶつけること、それぞれの文化の特異性、独自性、差異を経験できる場を作り出すことが、アヴィニヨン・フェスティバルの使命だと思っています。
A: 欧州統合がさらに深化し、東方拡大が実現したわけですが(2004年5月にEUの加盟国数は15から25となった)、その流れの中で、来たるべきヨーロッパの文化政策のモデルを見つけること、それも今ヴァンサンが言ったように、差異が存在することを前提として見つけることは非常に重要だと思います。
B: 私たちは、フランス、ドイツ、ベルギーほか、ヨーロッパ各地の政治家に、国家が文化領域における公共サービスを維持することの重要性、アーティストと創造活動を支援することの重要性を理解してもらえるよう、政治的な働きかけも行なっています。文化は、資本主義の例外として市場経済の外部におかれなければなりません。それが、ヨーロッパの文化的アイデンティティを守るための唯一の手段だと思います。 - 公共サービスといえば、2003年の演劇祭は、アンテルミタン(舞台芸術・視聴覚産業のフリー労働者で、プロの俳優、ダンサー、技術者の大多数が該当する)たちの抗議運動によって中止に追い込まれました。お二人はそのときも演劇祭の事務局で働いていらっしゃったわけですが、どのような思いを抱いていらっしゃいますか?
-
A:
アンテルミタンの問題は、いかにアーティストが社会の中で存在し続けることができるか、普通に生活し続けることができるかという問題に直結しています。フランスの失業保険制度は、政府が直接管理するのではなく、雇用者、組合・労働者の代表によって運営されています。(巨額の赤字を出しているといわれる)アンテルミタンの休業補償も、舞台芸術と視聴覚産業だけでなく、労働者全体の拠出金によって支えられています。政府は、この失業保険制度の改革は、たとえば助成金を削減するといった、文化政策の重要な変更には該当しないと考えていたのです。ところが、その改革は、舞台芸術や映画に携わる人間の経済状況を根本から不安定にするものであり、演劇界に危機感を引きおこしました。失業保険の性質上、それが文化省に直接関わる問題ではないにしても、失業保険機構あるいは文化省が、すべての関係者が納得できる解決策を提示することを願っています。
2003年には、生活基盤が脅かされたと感じたアンテルミタンたちが、ストライキや示威活動などを通じた強い抗議運動を起こしました。私たちは、彼らの主張に共感し連帯する一方で、ストライキや演劇祭の中止という手段は、一時的な感情に流された戦術であり、適切なものではないと考えていました。演劇祭の中止は、60年近くの歴史の中ではじめてのことでした。失業保険の改革はいまだ決着していない問題ですが、アーティストにとっての演劇祭の重要性を考えても、アーティストが再び自ら演劇祭を中止に追い込むことはないと思っています。というのも、演劇は、ほかの芸術と同様あるいはそれ以上に、人間の存在なしに成立しない、人間の存在そのものといってもいい芸術ですし、そのことをアーティストも理解していると考えるからです。
B: 失業保険の改革案は、舞台芸術界の現状に見合ったものではありませんでしたが、演劇祭の中止もまた最良の手段ではありませんでした。それ以来、私たちは関係各界の代表たちを集めて、何らかの合意を形成できるよう、粘り強く議論を続けるための場を設けてきました。もうじき新しい改革案が示されるはずですが、それが満足できる内容となることを期待しています。 - 2003年までディレクターを務めたベルナール・フェーヴル・ダルシエ氏の部下であったお二人が、その後任としてディレクターに任命されることになったわけですが、そこまでの経過はどのようなものだったのですか。
-
B:
フェーヴル・ダルシエ氏は二つの期間にわたってディレクターを務め、演劇祭をさらにプロフェッショナルで国際的なものへと発展させることに貢献しました。94年に非常に優れた日本特集を企画したことはご存じでしょう。けれど、文化大臣(前文化大臣ジャン=ジャック・アヤゴン)は、フェーヴル・ダルシエ氏の任期を更新しない方針を打ち出しました。それを受けて、私たちはこれまでの演劇祭の総括を行うとともに、今後に向けた提案を行ったわけです。
アヴィニヨン・フェスティバルの運営母体は非営利協会なのですが、その運営委員会が後任のディレクターの選考委員会を兼ねていました。運営委員会には国(文化省)、地方、県、市など演劇祭の主たる支援者の代表が含まれており(文化省とアヴィニヨン市の意見が特に重要視されます)、彼らを前にして、新しい演劇祭についての提案を行い、選ばれました。 - フェーヴル・ダルシエ氏から、何を受け継いでいるとお考えですか。あるいは彼の路線とどのような違いを打ち出そうとされたのでしょうか?
-
B:
幅広い観客に向けられた、新しい創造のためのフェスティバルという点で、私たちの仕事もこれまでの伝統の延長線上にあると思います。その一方で、国別の特集をやめて、アソシエイト・アーティスト中心のプログラムを組んだことは大きな違いです。
2004年のフェスティバルに招いたアーティストたちの多くは、これまでにも演劇祭に参加してきた人々ですし、私たちが何か全く新しいことを生み出しているわけではありません。ジャン・ヴィラールが1947年に創設して以来の57年にわたる演劇祭の伝統が、これからも続くように努めることは私たちの責任だと思います。
A: 上演された作品のその後のツアーをサポートする体制も充実させました。演劇祭が単独で制作する作品はありません。上演する作品は、関与の仕方に違いはあれ、すべて共同制作です。事務局の中に、ツアーのコーディネート担当部門を置きました。 - 歴史のある世界有数の演劇祭のディレクターに、若くして就任するのにはプレッシャーを感じませんでしたか?
-
B:
ジャン・ヴィラールがアヴィニヨン・フェスティバルを創設したとき、彼はまだ35才でした。フェーヴル・ダルシエ氏もディレクターに就任したときには35才でした。ですから、私たちも、まさに適齢です(笑)(インタビューの時点でボードリエ氏は36才、アルシャンボー氏は34才)。
若いということには一つの強みがあります。舞台芸術は生きた芸術であり、若さの芸術だと思います。アヴィニヨン・フェスティバルを、「今」の芸術家、「今」の芸術表現、「今」の観客に向けて、一層開かれたものにしたいと望んでいます。 - 数少ない批判の一つはチケット代の高さに向けられたものでしたね(主要会場の正規入場料は23〜33ユーロ/1ユーロ=約135円)。日本に比べればはるかに安いのですが、たとえば2004年の私のように、1週間滞在して20本以上の作品を見ると、その幸福感の代償として、それなりの出費は覚悟しなければなりません。宿の少なさと予約のとりにくさも、幅広い観客を集めるには大きな障害になっていると思いますが。
-
A:
これらのアクセスの問題は、当然認識しています。演劇祭にやってくる人々に、可能な限り安価に滞在してもらえるよう努力しています。宿泊施設については、学校などを若者向けの安価な宿泊施設として開放してもらっていますし、アヴィニヨン市にも改善を働きかけています。チケット代については、助成金のおかげで、比較的安く抑えることができています。とはいえ、1週間、見られるだけの作品を見れば、確かにかなり高くはなりますね(笑)。
B: それでも、実際にかかったコストを考えれば安いものですよ。エクス・アン・プロヴァンスの音楽祭に行けば、チケット代はアヴィニヨンの数倍はします。さらに、今年からの試みとして、格安の学生・若者料金も設けました。そのおかげで、若者向けのチケットの売り上げはたいへん枚数が伸びました。収入面からいえば痛手でしたが、私たちのプロジェクトにとっても、演劇祭の将来にとっても、非常によい知らせでした。実際劇場の客席を見ても、若い観客が増加していると感じました。昔からの観客から(中には1947年以来通ってくれる客もいます)、はじめて演劇祭に来た人まで、3世代あるいは4世代にもわたる観客が同じ劇場の中に同居しているのも、アヴィニヨン以外にはなかなか見ることができない強みだと思います。
A: 若者・学生向けには12ユーロの料金を設定しましたし、いくつかの作品は無料あるいは5ユーロという格安な設定にするなど、精一杯の努力をしています。それ以上を求められても、もう経済的には限界です・・・(笑)。 - 財政について、公的助成の内訳を教えてください。国や自治体との関係はどうですか? 特に、地元自治体との関係は、演劇祭は誰のためのものか、という問いと密接に関係していて、昔から主催者を悩ませてきた問題だと思いますが・・・
-
B:
国、地方、県、市から助成を受けていますが、助成金の60%は国からです。アヴィニヨン市が21%、残りが県(10%)と地方(9%)の助成です。地元の観客との関係は、きわめて重要な問題です。私たちはパリからアヴィニヨンに事務所を移しました。法王庁の中庭、カルム修道院、ブルボンの石切場など、アヴィニヨン・フェスティバルには、この土地と深く結びついたところがいくつもあります。ここに事務所があれば、アーティストたちに実際の場所を見てもらった上で、直接議論できますし、また、地元の観客にも生の声で語りかけてもらえる。観客の35%は周辺の地方からやってくる人々なので、これは非常に重要なことです。
A: かつては市の助成も国と同じくらいあったのですが、開催費用が増大する中で、市の助成は増えず、国の助成金額だけが増加していったため、今では大きな差がついてしまいました。演劇祭の財政については、中止などという予定外の出来事がない限り、収支は均衡しています。国や自治体との関係はすこぶる良好です。本当ですよ(笑)。私たちに相当な芸術的自由度が残されているので、芸術的内容について外部から意見されることはありません。 - かつてアヴィニヨン市は、世界的な演劇祭よりも、無名の市立オペラ座により多くの助成金を出しているといって批判されていましたが、今もそうなのですか?
- A: 今もそうです。
- どのようにお二人で働いていらっしゃるのですか。二人の間での役割分担は?
-
B:
二人隣り合って、仲良く働いています(笑)。私は主として芸術面、プログラムづくりに責任を持っています。
A: 私は運営に関すること、財政や人事のことなどを受け持っています。夢を見るのがヴァンサンの仕事だとすれば、私の仕事はそれに現実を突きつけることでしょうか。ウィというのはいつもヴァンサンで、ノンというのはいつも私(笑)。 - 日本の文化の現場で今いちばん求められているのも、まさに夢と現実との高度な共存だと思います。ありがとうございました。
ヴァンサン・ボードリエ/オルタンス・アルシャンボー
新生アヴィニヨン・フェスティバル
新たにアソシエイト・アーティスト制度を導入するなど話題
2005.02.16

ヴァンサン・ボードリエVincent Baudriller
アヴィニヨン・フェスティバル総監督
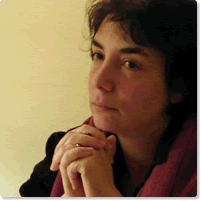
オルタンス・アルシャンボーHortense Archambault
アヴィニヨン・フェスティバル副監督
インタヴュー&文:藤井慎太郎(早稲田大学文学部教員)
アヴィニヨン・フェスティバル
Festival d’Avignon
https://www.festival-avignon.com/
この記事に関連するタグ

