

極東退屈道場『サブウェイ』
撮影:石川隆三
Data
:
[初演年]2010年
[上演時間]1時間45分
[幕・場数]1幕8場
[キャスト]7人(男3・女4)
サブウェイ
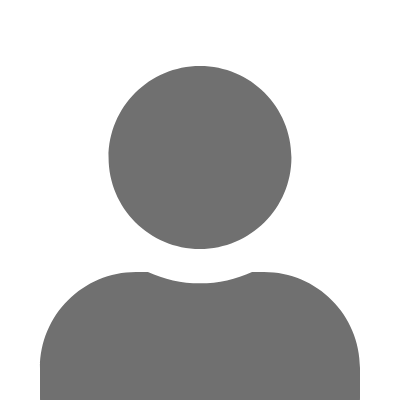
1977年北海道函館市生まれ。劇作家・演出家。1998年、京都大学在学中に(劇)ミサダプロデュース結成に参加し、演劇活動を開始。以降、筆名・ミサダシンイチとして、劇作・演出を担当。2004年、伊丹想流私塾にて北村想に劇作を師事。2007年、劇団活動終了とともに、本名の林慎一郎としての活動に切り替え、公演毎に俳優を集める個人プロデュース「極東退屈道場」を発足。都市に暮らす人々の姿を、俯瞰的な目線からノイジーに点描することで、浮遊する「現代都市」の姿を切り取ろうと試みている。代表作に、函館とおぼしき夜景を背景に、ロープウェイの中に行き過ぎるいくつかの冬に浮かびかつ沈む人々の会話を描く『夜ニ浮カベテ』(2004年初演/(劇)ミサダプロデュース)、地下鉄に乗り込む都市生活者を点描した 『サブウェイ』 、コインパーキングから狂騒的に「現代」を切り取った『タイムズ』で、第18回OMS戯曲賞大賞、第20回OMS戯曲賞特別賞を受賞。『PORTAL』で第61回(2016年)岸田國士戯曲賞最終候補。
極東退屈道場
http://taikutsu.info/


極東退屈道場『サブウェイ』
撮影:石川隆三
Data
:
[初演年]2010年
[上演時間]1時間45分
[幕・場数]1幕8場
[キャスト]7人(男3・女4)
映画監督ヒバリー・チャンは新作ドキュメンタリー「武装のサラリーマンのショック」を華々しく公開した。その内容は、日本の地下鉄ではサラリーマンたちがある「音」を聞かされながら、有事の際にいっせいに「兵士」となるべく訓練させられている、という怪しくもショッキングなもの。
まず監督は地下鉄で通勤する保険会社社員、学生、小学校教師、ナース、フリーター、パドンナ(広報誌「ぱど」を配る女性)、図書館職員ら7人にインタビューをし、それぞれどのように地下鉄を利用しているか、その殺伐たる状況をおのおのの言葉で事細かに語らせることで、労働世代の現状を浮き彫りにしていく。彼らの中にはすでに地下鉄で「音」らしきものに気づいているものもいる。
7人のインタビュー・シーンが長い独白となって創世の7日間を構成していく狭間に、ひとりひとりの実時間の生活風景がはさまれてゆく。すると、バラバラの存在だったはずの彼らの間に、さまざまなつながりが見えてくる。DJを目指す学生・橋は小学校教師・山村とつきあっており、橋はナース・三船の自転車を盗んだことがある。保険会社社員・矢代は事故にあったパドンナ・世良を訪ねると、世良の看護をしているのはナース・三船の同僚だ。フリーター・佐藤はTSUTAYAで世良と同じDVDを探しているといった具合である。
年齢も性別も仕事もまちまち、まったく立場の異なる人々だが、彼らにはある共通項があったのだ。それは大都会に住み、故郷を遠く離れていること。
どこまでが映画のシーンでどこからが現実なのかも不確かになってくる中、故郷を失った彼らを象徴する戦後の一つの家庭が映し出される。
とある北の町。歌で食べていきたいミノルと、それをとめようとする昔気質の両親。ミノルはのちに北島三郎と改名し、紅白でトリをつとめる大物歌手になる。彼の十八番は日本人なら言わずと知れた「まつり」。三郎が「まつり」を歌うとほとんど紅白は白が勝つ。
「まつり」、それは勝利の歌。そして日本人はまつりの心理状態の時、無敵になるという。映画監督ヒバリー・チャンは地下鉄で流されている音がこの「まつり」であることを発見し、「サブウェイ」とは「三郎への道」の意、もし宇宙からの侵略があっても入念に訓練された日本人サラリーマンが「まつり」をきっかけに世界を救うと断言する…。
が、もちろんこれは「虚構」である。監督は虚構こそが現実で、現実は虚構のために存在すると主張する。しかし、そんな監督も病院に入院しているのかもしれず、何が現実なのかはもはや誰にも分からない。
地下鉄は右も左も暗闇である。見るべき景色はない。ふるさとなど、もともとなかったのかもしれない。しかし地下鉄は目的地へは必ず到着する。私達の現実はどこにたどり着くのだろう。
この記事に関連するタグ