Data
:
[初演年]2007年
[上演時間]2時間
[幕・場面数]二幕十二場
[キャスト数]2人(男2)
三谷幸喜
ラスト・ラーフ
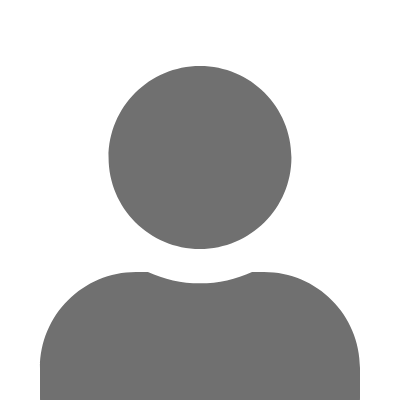
三谷幸喜Koki Mitani
劇作家、演出家。1961年、東京都出身。日本大学芸術学部演劇学科卒業。大学在学中の83年に、学友らと劇団「東京サンシャインボーイズ」を結成する。コメディに強いこだわりを持ち、明確なキャラクター設定を施された登場人物による、ウェルメイド・プレイを活動当初から多数執筆。舞台以外にテレビドラマのシナリオを多数執筆する他、裁判員制度実施以前に、陪審員制度を導入した日本を仮定した『12人の優しい日本人』(90年初演)、太平洋戦争下での軽演劇の作家と検閲官の攻防を描いた『笑の大学』(96年初演。2007年にはリチャード・ハリス脚色の英訳版 『The Last Laugh』 での英・日公演も実施)、幕末の英雄・坂本龍馬の死後に遺された未亡人を巡る人情劇『竜馬の妻とその夫と愛人』(2000年初演)など映画化された戯曲も多い。自身でも劇団時代の戯曲でラジオドラマの収録現場での騒動を描いたコメディ『ラヂオの時間』(93年初演)を映画化し、97年に監督デビュー。以降は映画監督としても作品を発表している。劇団は97年の『東京サンシャインボーイズの「罠」』公演をもって、30年間の活動休止中。『笑の大学』で第4回読売演劇大賞最優秀作品賞、99年『マトリョーシカ』で第3回鶴屋南北戯曲賞、00年に初のミュージカル 『オケピ!』 で第45回岸田國士戯曲賞、08年に第7回朝日舞台芸術賞 秋元松代賞など受賞歴も多い。

戦時下。「コメディ劇場」の作家が軍に上演許可をとりにいく。検閲官に台本を読んでもらい、規律に反するところが無いかを確認した上で「承認」のスタンプを押してもらわなくてはいけないのだ。担当の検閲官はなじみで、彼がチョコレートを贈ると検閲が甘くなった。今回も作家はチョコレートを一箱携えている。
しかし、その日は違う男が現れた。前任者は取り調べを受けているという。とにかく四角四面で冗談一つ理解できない新しい検閲官と、上演を控えてなんとか台本を許可してほしい作家との10日間にわたる攻防が始まる。
新任の検閲官は台本にト書きがあることすら知らない演劇の門外漢。その上、国家存亡の危機にコメディという不真面目な演劇に取り組むことにも大きな不快感を抱いている。もともと反戦芝居ではないし、大仰なスローガンを含んでいるわけでもないが、作家はあの手この手でこの男を懐柔し、笑いの必要性を理解させなくてはならなくなった。
演目はシェークスピアを下敷きにした「ロミオとジュリエットの喜劇」。無害なドタバタコントだ。しかし、にわか勉強をした検閲官は、この古典的ラブロマンスは戦時下にふさわしくないので、「ヘンリー五世」を登場させろ、と言う。作家は時間をもらい「ヘンリーとジュリエットの喜劇」と書き換えた。他にも「我らが指導者万歳」というセリフを3回入れろ、警察署長を登場させてセリフに政策を盛り込めなどと迫る。作家は、「我らが指導者万歳」という名の馬を登場させ、署長役に美男俳優を起用するなどの工夫で何とか乗りきる。検閲官がカラスを飼っていることを聞くと、大道具に小屋を作らせて差し入れるなど、細かい気遣いにも余念が無い。
書き直しが進むにつれ、検閲官はどんどん作劇の、演劇の面白さに目覚めていく。作家に対しての厳しさは失わず、書き直しを命じ続けるが、台本にアイデアを出し、果てはカツラを被って稽古の相手までする始末。そういう中で作家は「笑いとは残酷さをベースに持ちつつも人類に必要なもの」、「僕らは皆死ぬという事実を忘れさせてくれる工夫」などと喜劇の必要性を伝え続ける。
しかし、最後の最後で作家は調子に乗った。息子を戦争で失ったばかりの検閲官の心の傷に触れてしまい、激怒させてしまう。今までの苦労虚しく、「笑いの要素を全部無くせ」との命令が下される。しかし、全部書き換えた新作は、ストレートな体制批判喜劇になっていた。当然、スタンプは「却下」。作家はそれを予期していた。彼にも召集令状が届いていたのだ。最後の最後、書きたいことを書ききって彼は何かすっきりとしている。
検閲官はその前夜、劇場に行っていた。今まで作家から喜劇とは、笑いとはということを聞き、息子が死んだあと、本当に笑いが人を救うのか知りたかったのだ。そこで見たのは、戦時下にすべてを忘れて笑いさざめく人の姿だった……。
もちろん立場上、上演は許可できない。しかし、向き合う2人には静かだが確かな絆が生まれていた。そう、この状況こそ、喜劇なのかもしれない……。検閲官は言葉少なに、作家の無事を願った。
この記事に関連するタグ

