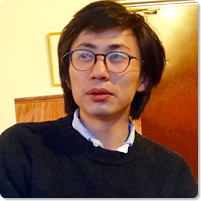空間現代の音づくり
- 空間現代のバンド結成は2006年です。どういう経緯でバンド活動を始めたのですか。
- 結成は私が大学3年生の頃です。その頃ちょうど暇ができたという事もあり、バンドを組んで曲をつくってみようかと何気なく思い立ったのが始まりです。メンバーを探そうと考えていて思い浮かんだのが、古谷野慶輔と山田英晶の名前です。2人は中学・高校の後輩ですが、音楽の趣味が合ったということもあり、誘ってみました。3人とも大した音楽経験はなかったのですが、バンドを組むのにそうした事はあまり関係ないと思っていました。まぁ、今から振り返ると若気の至りのようなところもあって、とにかく勢いで始めました。
- ということは、別にプロになりたくて始めたわけではない?
- 音楽で生計を、という事に関しては全く考えていませんでした。周りにはプロミュージシャンを目指している人たちもいましたが、私たちはそこまで考えていなかったと思います。普通に就職して、仕事もしつつ、本気で取り組む遊びの様なものとして音楽活動を続けていければと思っていました。
- バンド結成当時、空間現代として目指した音楽はありましたか。何か音楽的に参考にしていたバンドがあったのでしょうか。
- 結成当時は、主に日本のバンドものを聴いていました。フィッシュマンズ、ニューエスト・モデル、ゆらゆら帝国、くるり、ZAZEN BOYSなど。その後はいろいろな音楽に触れる機会もあって、電子音楽、実験音楽、ヒップホップなど次第に裾野が広がっていきました。その頃、メンバーの間ではレーベル「HEADZ」を主宰していた批評家の佐々木敦さん (*1) が紹介する音楽が面白いと意見が一致していました。それで佐々木さんに曲を聴いてもらおうとデモテープを渡したら、HEADZから出そうよと言っていただきました。
- 野口さん、古谷野さんは早稲田大学の学生で、当時は佐々木さんが講義をされていました。
-
受講していました。講義もさることながら、佐々木さんが流す音楽や著作『ex-music』『(H)EAR ─ポスト・サイレンスの諸相』からいろいろと学びました。それまでは「“聴く”とはどういうことか」「既存の音楽からどのようにして脱出するか」といったコンセプチュアルなことを、全く考えたことがなかった。文体や単語も難しいものばかりで、当時は読み進めるのも大変でした。でも読んだ時にピンときた事もあって、それは自分の経験と重なるところがあったからだと思います。例えば『ex-music』に楽器というものをひとつの制度として書かいてあるくだりがあるのですが、これはすんなりと理解できた事を覚えています。
ギターを弾いている以上は、ギターという楽器からは離れられない。楽器というものが、ある程度その音楽の枠組みを決めている。この事は作曲している時に強く感じていた事なので実感として理解できました。そうした音楽における既存の枠組みをズラす様な音楽をつくりたいと思い始めていた頃だったので、佐々木さんの著作で紹介されていた既にそうした取組みを行ってきたあらゆる音楽家たちの話は非常に刺激になりました。 - 佐々木さんから紹介された音楽で、現在までの空間現代の独特の音楽性に影響を与えたものはありますか。
-
たくさんありますけれど、今話していた流れで言えばOval(ドイツのテクノ音楽ユニット)には驚きました。彼が行った「グリッチ」と呼ばれる手法、CDの裏面に落書きをして再生するとスキップが起こる、そのスキップ音をサンプリングして音楽をつくっていくというものですが、これにはやられました。もう既に使い古されているもの、しかも楽器じゃなくてメディアを使って新しいことを生み出せた訳ですから、凄いですよね。もちろんそんな手法のことや概念的凄さみたいなことを知らずに聴いても、彼の音楽からはその斬新性と未知の質感が感じ取れる。
新しい音楽、という言葉の定義は難しいですが、少なくともつくり手としては自分ですら驚いてしまうような未知の音楽を生み出したいと思うようになったきっかけのひとつです。 - 空間現代の音楽は、極端に言えば「電子音楽のサンプリングのようなことをわざわざ3ピースでやっている」ところがあるように思います。3ピースではなく他の楽器を加えたり、電子音楽に進むという方向は考えなかったのですか。
-
先ほどの話で言えば、楽器というものは確かに揺るがない制度かもしれないけれど、それを否定して違う楽器に持ち替えたところで、また異なる制度に縛られるだけになる。ならば既存の枠組みを少しズラす事で新しい音楽をつくった方がよいのではないか、とOvalの様な音楽に触れてより一層強く思いました。だから楽器を変えたり、加えたりすることは考えませんでした。
しかし、一方でその頃は電子音楽をよく聴いていたので、今聴いている音楽の要素をバンドに取り入れようとすると、無理が出てくる事にモヤモヤした思いもありました。それで、ある時遊び半分でレコード針がプツッと飛んだ時の“音飛び”の感じを無理やりでいいから再現してみようと3人で試しました。
作曲に行き詰っていたので、ほとんどおふざけでやってみたんです。でも思いのほか発見があった。もともとコラージュ的な発想、パッと曲調が切り替わるような展開のさせ方は好きだったのですが、そのためには新しいフレーズをどんどん繋いでいかなければならない。ところが音飛びの場合は同じフレーズの反復でありながら、そのコラージュ感というかパッと切り替わる感じが出せる。
それと同時に、演奏の意識が変化している事に気づきました。何というか、「変拍子を弾く」という意識から、「現象を起こす」という集中感に変わった。短いフレーズを繰り返している中で、パッと音飛びをしようとすると、今まで味わった事のない、独特な息の合わせ方が必要になってくる。私はこうした演奏意識の変化こそが、既存の枠組みから少し外れるための突破口になるのではないかと考えました。この路線でいけば、楽器や編成を変えなくても、いや変えないからこそ面白い音楽をつくれるのではないかと。
なので、こうした手法の発見のために一時期様々な実験を行っていました。ギターとベースとドラムがそれぞれ音数を段々と減らしていくためのルールを考えよう、とか。試しに1個短いフレーズをつくり、それを3人に割り振る。これを“分配”と呼んでいますが、例えば15個音数があったとしたら、ひとり5個“分配”して、3人でひとつのフレーズをリズムを狂わさないようにパスを繋げていく。
次に、その5つからそれぞれランダムにどれか音を抜いていい、というルールをつくってさらに音数を減らしていく。これを「穴あけ」とか「歯抜け」と呼んでいますが、とにかく弾くべきところを弾かないという行為を混ぜることによって、独特の間合いが生まれてくる。こうすると、同じフレーズを反復していても、演奏者も聴き手も反復している感じにならず、「おやっ?」となる。それがやっていて凄く面白かった。しかも最初は下手くそだったから、まあ今も下手ですが、リズムがよれたりしてさらに変な音楽になっていく。 - 「現象を起こそう」というのは、メンバー3人のプレイの間でもそうだけど、曲に対しても同じように考えていた、と。
-
そうですね。とは言え、曲をつくるときに実際考えていることは単純で。作曲の際、「リフ」…「リズミック・フィギュア」とか「リフレイン」とかの略と言われていますが、ある短い音型ですね、それをつくる事から始めます。ギター、ベース、ドラムがそれぞれのリフを関係させて音楽をつくる、という発想が根底にあるのだと思います。
ファーストアルバム『空間現代』(2009)は、そのリフを三者がぶつけあうというか、絡み合わせる様なイメージでつくられた曲が多いと思います。それがセカンドアルバム『空間現代2』(2012年)の頃になると「1つのリフを演奏者3人で形づくる」ということへと興味が移っていきました。そのため、“音飛び”と“分配”と、“歯抜け”という手法だけでなく、3人の演奏が全て同期する演奏方法も取り入れる事になりました。反復して、飛んで、途中で音を抜いたり、足したり、同期したり。そうすると、フィギュア自体は保持されながらダイナミズムが出てくる。こうした事は現在の空間現代のライブや曲の考え方の土台にもなっていると思います。
ちなみに、セカンドアルバムに関しては音をバラバラに録音してからデスクトップ上で曲の再現を行うという、ややこしい方法でつくりました。それはエディットしないと生まれ得ない音楽ではなくて、エディットによって普段ライブで演奏している曲を再現し、産み直すという試みでした。よく言われるのですが「デジタルミュージックの人力再現」という事に私たちは興味を持っている訳ではありません。むしろ別物になってしまうことを目的としてやっている。だから、セカンドアルバムでもそういうことを狙ったわけです。エディットでしかできないものではなくて、普段やっていることをエディットでつくろうとした時に生まれるねじれ、ライブと音源はまったくの別物であるということを念頭につくりました。 - 既存の音楽のつくり方ではない方法を模索するにあたって、影響を受けたバンドがありましたか。
-
つくり方の模索、という点において難しいのはやはり歌の存在でした。結成当初は歌を主軸に置いてつくっていたのですが、これまでの経緯から歌は後回しになっていきました。なので歌が入っていながら既聴感のない音楽、そういうものをよく参考にしていました。
たとえば、PANICSMILEや54-71、nhhmbase(変拍子や転調を多様する日本の革新的ポップス・バンド)など。nhhmbaseのメンバーがインタビューで「普通のポップスはボーカルしか歌っていないけど、僕は全楽器が歌っているようにしたい」とおっしゃっていたのですが、これには共感しました。私も、歌を入れた途端に歌が圧倒的に権力を持ってしまって、ギターやベース、ドラムが伴奏でしかなくなってしまうことを回避したいと思っていました。全部フラットに聞こえるようにしたいというか。
他にも、キャプテン・ビーフハート(1960年代の米国サイケデリック・ミュージック・シーンを牽引したアーティスト)やThe Shaggsの影響は大きいと思います。両者とも歌をガンガン乗せていくのですが、演奏が全く伴奏のようには聞こえない。それどころかたまに歌が伴奏に聞こえたりもしてくる。バンドをやるからには、ギターもベースもドラムもボーカルも全部、なんというか拮抗している感じがしないとダメだ。そういう音楽をやりたいと思いました。 - 拮抗させ続けるのは難しいでしょうね。聴いている側も何か一つのまとまった音楽とし聴こうとしますし。
-
そうなんです。どんなに周りの音を聴かないように演奏しようとしてもやっぱり聞こえている音に影響は受けてしまうし、録音して聴いてみると伴奏みたいに馴染んじゃっていることも多い。音楽は、ひとつになろうとする力が相当に強い。けれど私たちはその逆をついてみたかった。アンサンブルとは別の形の在り方はないものだろうかと。簡単に言えば、それぞれの音がせめぎ合っている感じをつくりたかった。
そういう発想から、対バン相手と全く別の曲をそれぞれ同時演奏したこともあります。ただ、それだと単に別々なだけで、拮抗する感じはしなかった。実験としては相当おもしろい演奏になったと思いましたけれど、少し目指しているものとは違う手応えだった。別々のものが同時に鳴るという事が、先ほどから繰り返し述べている拮抗関係やせめぎ合いみたいなものには必ずしもならないという事は、私にとって大きな発見でした。
その流れから、ラッパーのECDさんとコラボレートする機会をHEADZから頂きました。空間現代の曲の演奏にECDさんのラップを乗せてもらうライブを披露したんです。私たちの曲はラップを乗せるための曲でもないし、ラップありきでつくられた曲でもない。でも、ラッパーがラップを乗せてくると丁度良いバランスでせめぎ合っている感じがあった。それで「せめぎ合う」感じを生み出すためには、「リズムの共有」が少なくとも必要なのではないかと思うようになりました。 - “現象”をつくる場合、作曲はどういう順番で音づくりを考えることになるのでしょうか。まず現象ありきで、現象が起きるようなルールとか展開を先に考えるのか、それとも、とりあえず何かフレーズを考えてから現象が起きるように変えていくのか。
-
セカンドアルバムはどちらかというとルールや現象ありきでつくっていました。先に現象をおこせそうな曲の構造や設計図を考えて、それを試すために何かしら素材になるフレーズをつくる。ファーストアルバムの時はフレーズづくりが「作曲」だったのですが、セカンドの時は素材としてのフレーズはある意味で適当で、現象を起こすための設計図をベースにつくっていました。適当につくった素材でも意外と設計図にハマるんです。もちろん後から素材やフレーズへのこだわりは出てきますが。ちなみに最近では、方法論にそこまで興味がなくなってきて、フレーズの方に立ち返ろうとしてます。過渡期なのかなと思いますけれど。
ちなみに先ほどから繰り返し出てくる「現象」という言葉ですが、その原点はなにかと言えばとてもオーソドックスなものだと思っています。それは、バンドという形態へのこだわりとも繋がる事なのですが、たとえばパンクやロックバンドのライブにおける始まりの瞬間。そこに観客がいて、ステージがあって、バンドメンバーが出てきて、ジャーンと鳴らして「ウオー!」となる。あれはオーディエンスとバンドの間に起きている何らかの出来事ですよね。ここに原点があると思っています。あの瞬間に触れた感触を、別の在り方として変質させて、ずらしていくこと。そういうことをやってきたつもりだし、これからもやっていきたいと思っています。
演劇との接点と三浦基との協働作業
- 空間現代の音づくりに音楽以外の分野からの影響もあったのでしょうか。
-
演劇の影響、特に「同時多発会話」(あるひとつの場所で複数の会話が同時進行する手法)を観た時の驚きは大きかった様な気がします。同時に別の人が別のことを言っていて、それらが絡まないまま、それらの声がノイズとして充満して次のシーンに移る。あれは良いなあと思いました。演劇は台詞と物語と役があるので、聞こえ方というレベルでも、台詞を喋っている発話者がそれぞれ別のフレームを持っていると認識しやすい。Aが喋ったらBが聴いている、という光景を私が観ている。舞台上において発せられた言葉の先には常に自分以外の特定の他者が想定されているからこそできることだと思います。
音楽は基本的に聞こえている全員に音を届かせているので、関係性が役者A対Bじゃなくて、「音楽対オーディエンス」になってしまう。「別々の相手に喋っている」という“別々の”という感じはつくれない。それで「1つのリズムを3人でつくる」という方向に振り切ろうと思いました。ただあの時に観た演劇の感触はどこかで今でも残っているし、糧になっていると思います。
それから、地点の『あたしちゃん、行く先を言って』(2010年)を吉祥寺シアターではじめて観て、凄いと思いました。ビジュアルが物凄く格好よくて、映像なども含めて、複数の要素がワッと全部並走している感じがあった。これは “音楽”だと思いました。 - 地点は、戯曲の言葉を一音一音バラバラに分解して発語します。これは野口さんたちのやってきた、リズムを脱臼したり、フレーズを分解して分配したりするのと凄く近い作業にも見えます。
- あの発語は最高だなと思いました。特に俳優の安部聡子さんの台詞は、ひとつのメロディーにも聞こえてくる。だから最初は演劇というより音楽として聴いていました。
- “わたし”が解体されて“わ! た・し”と言われた時、“わ!”がどこに、あるいは誰に向けた“わ”か、わからない。“わ”対オーディエンス、になっているとも言えます。
-
なるほど。だから音楽的だと思ったのかもしれません。ただ当時はもっと単純に「私」という言葉の意味を無化させるというか、音楽的なものへと変換させるために「わ」と「たし」に分けているのかなと思いました。ところがその後、一緒に協働作業をするようになって認識を改めました。彼らは言葉の意味と真摯に向き合っているし、言葉の矛先に他者という存在がいることを、むしろ強く意識している。ただ、それが単なる役者同士という意味合いの他者ではなくて、もっと抽象的な他者というか、そうしたものへの意識というか。
というのも、最初は「“わ”たしの…」って言った時の“わ”の言い方を演出の三浦基さんが作曲者、あるいはオーケストラの指揮者の様に指示しているのかなと思っていました。しかし、稽古に立ち会うと、三浦さんは感覚的な問いや違和感を出発点にして、俳優に「何かしろ」と訴える事から始めている。たとえばですが、客席に座った三浦さんが「もっとこっちを突き刺す感じで言え」、「“わたし”という言葉で客を殺せ」って檄を飛ばしているんです。そうすると俳優がそれを意識して“わ”だけ張り上げて発語する。
一観客でありながら批評家でもある三浦基という演出家が、「わたし」という言葉で俺を突き刺してほしい、絶望させろと言っている。そうしないと「わたし」という言葉はいつまでたっても喋れない、観客は「わたし」という言葉に希望なんか見出したくないと言っている。この様な稽古風景を見ていて、地点にとっての「観客」という言葉には様々な意味合いが重層的に含まれているのだという事が分かりました。それこそが言葉の矛先にある他者なのだとも。
彼らが想定する観客という存在は、様々なものを背負って劇場に来て、座って、演劇を観ている。歴史、制度、時事的要素、体感、眠気、気分。それらが折り重なっている存在。その代表として演出家が俳優に指示を出す。これはすさまじいことをやっているなと思いました。自分たちのライブにおいて、そこまで観客のことを考えたことはあったのか。いや、そもそも考える方法として音楽の演奏は成り得るのか。演劇の力強さを知ると共に、音楽の限界や特性についても考えるようになりました。
ただ、もちろん我々と似ているなと思う点、制作工程において共感できる点も多々ありました。たとえば、普通は感覚を再現するために言葉の内容を精査するけれど、彼らはその感覚を得るために発語の仕方や構成の方を変える。「現象の設計かフレーズか」「設計図か素材か」というのとちょっと似ていると思いました。 - 似ている部分があると感じたにしても、協働作業となるととても難しかったと思います。はじめて協働作業を行ったのがブレヒトの未完の戯曲断片を再構成した『ファッツァー』 (*2) です。
- 一緒につくるにあたって、三浦さんの方から、「音楽は伴奏になりがちだけど、それではダメだから並走しよう」みたいな話がありました。『ファッツァー』の最初と最後のシーンでは、私たちは私たちの演奏をして、演奏と役者の台詞がぶつかったら役者が倒れるのですが、このシーンは本当に並走できていると思います。大きな音によって役者が死ぬという演出によって、演奏における「間」の緊張感が増します。無音であっても演奏は続いているという聞こえ方がより際立たつ。演劇側からすればその無音の時にセリフを入れていくことができる。セリフと演奏の並走関係はこの様なことだったと思います。
- 『ファッツァー』も他の地点の作品同様、戯曲を再構成しています。三浦さんは三浦さんで文字と格闘して構成するプロセスがあるとして、音楽はどのようにこの作品と取り組んでいったのですか。演出家と戯曲の内容や演出の方向、音楽に関してどのような摺り合わせが行われたのですか。協働作業のプロセスを教えてください。
- 三浦さんから事前に指示はなく、というのもその時点では三浦さんにもどうなるか全くわかってないので、何でも良いからたたき台を1曲つくってきて欲しいと言われました。それで、一応原作を全部読んで、それを入口にしてつくりました。三浦さんの方には、「音楽はこれでいい、あとは芝居で何とか頑張る」という発想があります。だからいろいろ提案し続けると、「止めて!」って言われる(笑)。もしかしたら三浦さんにとって私たちの存在は、舞台美術のあり方とどこかで似ているのかもしれません。環境というか、条件というか。
- では、原作からどうやって曲をつくったのですか。
-
曲づくりに関しては、いつもはボーカルを最後に加えて完成という順序なのですが、『ファッツァー』に関しては逆に言葉しか手がかりがないので、いっそのこと言葉からつくったらどうかと、3人で話し合いました。『ファッツァー』を読んで気になった単語を摘まんだりして、まず私が詞を書いた。書いていくうちに、いつもやっている「歯抜け」という手法を歌でやったら面白いかもしれないと思いました。例えば、「聞こえた音が間違っている」という歌詞は、「聞こえた音」の「こ」を抜けば「消えた音」になる。音の抜き方、減らし方によって、違うフレーズやリズムに聞こえて、何通りにも意味が広がっていくような詞にしよう、というイメージで書き始めました。
でも、いざバンドに持っていくと難しいわけです。結局、ギター、ベース、ドラム、歌、全部を同じ詞のリズムに同期させました。例えば、「き、こ、え、たお、と、が」という詞のリズムだったら、ベースもドラムもギターも同時に「ジャ、ジャ、ジャ、ジャジャ、ジャ、ジャ」にする。言葉と音の全同期ですね、そんな感じで、リズムを詞として口ずさみながら練習し、稽古場では台詞の邪魔になるので、歌抜きでやることになった。言葉ありきでつくり、最後に言葉をなくす。これは今までやったことのない新しいつくり方でした。 - その後、三浦さんとは『ミステリヤ・ブッフ』(2015)と『ロミオとジュリエット』(2017)の協働作業をしています。コラボレーションのあり方に新たな展開はありましたか。
-
『ファッツァー』の時、三浦さんは「音楽が勝ってしまうと役者はダンスをせざるを得なくなる」と言っていました。音量が大きくなればセリフを消してしまうし、役者は身振りのみで対抗するしかない。音楽の時間が演劇を覆うと、役者はダンサーになってしまうと。そういうこともあり、音楽と演劇が並走するような工夫を演出で施していたように思います。空間現代としては始めての演劇作品への参加だったので、右も左もわからないまま、稽古に食らいついていた感じです。
『ミステリヤ・ブッフ』は逆に音楽だけの時間があっても良いかもと言われました。それで、私が歌うシーンもありましたし、バンド演奏がメインとなるシーンもありました。2作品目となるとお互い呼吸がわかってくるので、制作しやすい状況ではあるものの、『ファッツァー』の二番煎じにならない様にすることはとても難しく、音楽の関わり方という点でいうとかなり苦労した気がします。
3作品目である『ロミオとジュリエット』では、こちらから積極的に音楽の在り方を提示するよう心がけました。『ファッツァー』の時と同様「演技と演奏を同時にできないか?」ということを意識して。ただ『ファッツァー』の時とは違うアプローチの仕方で演劇に関与する方法を考えたという点では、それなりに新しい展開をつくれたのではないかと思います。
具体的に言えば、『ミステリヤ・ブッフ』の時に発見した「ベースとバスドラムは、割と大きく鳴っていても台詞が聞こえやすい」という、言われてみたら当たり前のことですが、その教訓を活かしてベースがずっと鳴り続ける曲を書きました。構造としての並走から、実質的に鳴り続ける音を並走させられたと思います。 - 音の高低や音色など、音楽に関して三浦さんから注文は来ないのですか。
- 最初の注文は「アンニュイな感じ」とか「イタリアの伊達男で」とかざっくりしたのがきます。で、最後は「何でもいいから早く何かつくって」になったりします(笑)。すでに出来た曲に関しての変更は本当にたまにですが、「そこだけ何か音階変えるか何かして」とか「クッて感じで外連味出してみて」とか、指示がきます。まずは言われたことをすぐさまやってみる。たまに時間をかけないと修正できない様な事を言われたりもしますが、基本はその場で少し修正すればできそうなことをやる。根本的なダメ出しは少ないです。
- 『ファッツァー』を契機にして空間現代は凄く変化したという印象を持っています。ライブパフォーマンスの演奏の説得力が増したとも感じますし、バンド活動もそれまでとは違うものを目指し始めたように思います。
-
本当にその通りです。特に、観客との関係については『ファッツァー』を通して多くのことを学ばせてもらいました。地点は、観客という存在をとても重要視していて、一緒に演劇をつくる、くらいの感じで考えている。その影響から私たちも観客とのやりとりみたいな視点が生まれてきました。
活動の在り方に関しても、地点からはかなり影響を受けていると思います。何というか勇気づけられましたよね。あれだけ堂々と格好良く鋭い芸術活動をされてる人たちをみて、奮い立ちました。 - 地点との協働作業では、普段はいない俳優というプレイヤーがいます。リズムも違うしあり方も全く違う。俳優という存在についてどのように捉えていますか。
-
ECDさんとコラボレーションした時の感覚と似ていると思っています。ECDさんと初めてやったときはぶっつけ本番の方が面白いと思っていたので、一度も音合わせのリハーサルをやらなかった。でもサウンドチェックの時に、「1回チョロっとだけはやっといた方が良いよ」とECDさんに言われたので、さわりだけやったら演奏が全くうまくいかない。言葉のテンポに引き寄せられて失敗してしまう。本番はとにかく集中して自分たちの曲をやらないと、ラップを聴いて引っ張られる様な演奏しちゃダメなんだと思い知りました。そのおかげでその時のライブはとてもスリリングで、鋭い演奏ができたと思っています。
(*3)
- 今でもこれが原体験として残っているので、誰かとやる時は「互いに引っ張り引っ張られる」という関係になってこそ面白いと思ってます。『ファッツァー』でも、役者の芝居に圧倒されて普段絶対しないミスをしてしまう時があります。その時に綱渡りがうまくいくように集中して演奏できると、いい感じになるのではないかと思っています。
スタジオ兼ライブハウス「外」について
- 昨年、空間現代の皆さんは東京から京都に移住し、拠点となるスタジオ兼ライブハウス「外」をオープンしました。狙いを教えてください。
-
バンド結成当初は音楽活動を仕事として考えない方針でいましたが、時間をかければもっと良い作品をつくれる自信がついてきたという事もあり、二足の草鞋ではなく、空間現代でなんとか生計を立てたいと考えるようになりました。
そんな中、自分たちのスペースを持つという発想が出てきました。自分たちのスペースを持てたらそこで音づくりもできるしイベントも打てる。自分たちのライブでチケットを販売したらすべて自分たちのギャラになる。そう思ったら、価値のある作品をつくらなきゃダメだし、いいプレイをしなきゃダメ。経済面の意味と、演奏や作品を磨き上げたいという思いの両方があって、スペースを持ちたいと思いました。
実際、地点がアンダースローという自分たちのスペースを持って、そこで稽古して、本番をやってというのを実践しているのを目の当たりにしたのが大きかった。こういうことを本当にやっちゃった人達がいるんだ、凄いなと思いました。音楽家の場合は、レコーディングスタジオをつくるのが普通の発想ですが、どうしても本番を打ちたかったんです。「観客」と「演奏者」と「音楽」の三者が、どういうふうに場をつくっていくかという事にも興味があったので。加えて、よく言われるように京都はコンパクトで、家賃が安い外れのエリアでも面白いことをやっていれば人が来る。東京だったら電車で1時間かかる場所しか借りられないけど、京都なら何かできるんじゃないかと思いました。 - 「外」では、他のミュージシャンのライブも企画しています。ライブハウスとしての運営コンセプトはどのようなものですか。
- ホールレンタルは一切せず、空間現代及び外のスタッフが企画を主催していくことで、空間現代がつくる音楽の、その根底にある音楽観みたいなものを提示できたらいいなと思っています。「外」を通じて、新しい音楽や未知のものへの可能性や好奇心を感じてもらえればと。
- 「空間現代の音楽観」とフィットするミュージシャンというのはどういう人達ですか。
- 多分、ジャンルとか形態、楽器とかそういうことではないのは確かで、じゃあ何にピンとくるかというと、答えるのが本当に難しい…
- “外(そと)”の人?(笑)
- お、それかもしれないですね。簡単には枠組みにおさまらない音楽を演奏する人というか。ちなみに「外」という名前は、自分たちの曲名から取っていますが、それだけではなく「外」というのは面白い単語だなと思っています。ある辞書では「そと」「ほか」「はずれる」とあって、最後に「それより彼方」と書いてあった。格好いいじゃんこれ、ポエムだねって決めました。
- 自分たちのスペースを持ったことで、空間現代の音づくりに変化はありますか。
-
音自体へのこだわりもそうですが、やはり練習の場と本番の場が同じというのは本当に制作しやすい環境で、時間もある程度都合がつくので練習の質は上がったと思います。それにスペースを持つまでは月1回位しかライブをやってなかったのが、月6、7回やるようになり、かなり鍛えられた演奏ができる様になってきていると思います。
また、大きな作品もつくろうと思えばつくれる状況なので、どんどんやっていこうと思っています。「ライブパフォーマンスとしての大作」への取り組みとして、1作目の『擦過』という長編楽曲をつくりました。現在2作目の制作にとりかかっています。大作としてだけでなく、自分たちの場所を使って、どの様な音楽作品をつくるべきかいろいろ考えながら、様々な形で見せていければと企んでいます。 - 近年『ファッツァー』のツアーや、空間現代のツアーもあって、海外で演奏する機会が増えてきたと思います。どのようなことを感じていますか。
-
『ファッツァー』でロシア、中国、ドイツに行き、去年は初めて空間現代の海外ツアーをイタリアとドイツでやりました。イタリアでの体験は凄かったです。
ボローニャの外れのフォルリという、別荘と畑しか無いみたいな田舎の町でした。そこのスペースが凄くて、ボランティアのスタッフが運営し、月2回ぐらい外国からツアーで来たミュージシャンを呼んでいる。観客はそこでやるという時点でライブに興味をもってくれて、私たちみたいな無名のバンドのワンマンライブに120〜130人くらい集まり、満員でした。アットホームだけどメチャメチャ集中して聴いてくれて、空間現代は初めてのはずなのに、聞き所では的確な拍手をしてくれる。日本は日本ならではの味わい方をしてくれていると思いますが、この時感じたショックは大きかったです。 - 最後に、「外」と空間現代での今後の展望を聞かせてください。
-
「外」と空間現代はそれぞれ別のプロジェクトだと考えていて、どこかで線を引いています。ただ、「外」としての成功と空間現代としての成功が相互に関係を結んでいるということでなければいけないとも思っています。
そういう意味では、「外」がどうなっていくのかは本当に手探り状態です。理想は、多くの人が現場に足を運んでくれて、「自分の好きな音楽家のライブだから行く」でなくて、「『外』でやっているから行ってみたら良い音楽だった」という、イタリアで味わった体験ができるような場になりたいと思います。「空間現代は気に入らないが『外』は面白い」という人がいてくれても構わない。「外」はその音楽性にせよ、運営方針にせよ、経営的には厳しくもありますが、今の時代においてこういう形態での場所の運営には可能性があると考えています。「外」はなんでもできる場所ではない。その、経済的にみれば不自由な運営方針こそが新しい潮流をつくれるよう、努めていこうと思っています。
空間現代の展望としては、海外で演奏することに凄く興味を持つようになりました。イタリアの後にドイツのデュッセルドルフとベルリンでやったのですが、複数の国でやれて本当に多くの刺激を受けました。観客の雰囲気が全く異質であることが、そのまま演奏の質も変えてくれる。そういうチャンスをもらえることで、自分たちの音楽との向き合い方は成長するし、音楽観を深めていけると感じました。こうした体験を「外」に持ち帰って、どうフィードバックしていくか。これから試みていきたいと思います。