- 遡った質問で恐縮ですが、まずは演劇との出会いをお話しくださいますか。
- 高校時代は絵描きになろうと思っていたんだけど、それじゃあ食っていけないよと親戚中から止められた。それですぐ反省し、新聞記者になろうとして早稲田に入ったんです。入ったら、入学式の日に「お前芝居やれよ、背が高いから役者ができるよ」と先輩に勧誘されて、ついフラフラッと「自由舞台」に入ってしまった。当時の自由舞台は新入部員だけで百人くらい、総勢で二百人以上という大所帯でした。「社会科学研究会」といった学問的あるいは政治的な集まりをいくつも抱え込んでいて、すごくエネルギッシュだった。その活気のよさにあっという間に巻き込まれていったという感じです。
- のちに「早稲田小劇場」を旗揚げし、ともにしばらくの間活動することになる演出家・鈴木忠志さんと、その自由舞台で別役さんは出会われています。鈴木さんとの初めての共同作業であり、別役さんにとっても処女作である『AとBと一人の女』は、どのような経緯で書かれたのでしょうか。
- 僕はしばらく芝居から離れて、新島基地反対闘争に出かけていたことがあるんです。1961年です。そこから帰ってきたら、鈴木忠志たちが、自由舞台とは別に自分たちだけで芝居やろうという感じになっていて、早稲田祭で上演する台本がないというので、思わず書いちゃった。それが『AとBと一人の女』です。
- 男Aに劣等感を抱く男Bが、モノローグの応酬のような対話のなかで男Aに苛まれつづけるうちに、関係が逆転し、男Aは男Bに殺されます。処女作とはいえ、ここにはすでに別役作品の特徴である「静けさ」や「もっていきどころのない葛藤」、孤高なセリフ文体までが完成されています。劇作はどこで学ばれたのですか。
-
その当時、我々が芸術的刺激を受けるものといったら、専ら映画でした。『AとBと一人の女』は、『目には目を』(アンドレ・カイヤット監督/仏=伊/1957年)という映画にインスパイアされて書きました。ヨーロッパ人の医師がアラブ人の男に復讐される話で、復讐の根拠も誤解に満ちていれば、復讐するほうも、されるほうもとことん救いのない結末に陥る。その決して止揚されない、とめどもない葛藤のプロセスみたいなものを形にできないかと思いました。
もうひとつは、ベケットの登場が大きい。ちょうどその頃、リアリズム演劇というのがそろそろ限界にきていて、特に僕らがやっていた社会主義リアリズム劇、つまり最終的には社会主義革命を達成しなければならないという、そういう政治的理念にがんじがらめになった芝居に嫌気がさして、その窒息状況から何とか逃れたいと思っていたんです。そこへベケットがあらわれた。僕自身はその前にカフカにずいぶんとらわれていたから、カフカからベケットへという感じで影響を受けていったのですが、社会や政治の問題ではなく、ベケットのように個人の内面のドラマに目を向けても芝居は成立するんだという、解放感のようなものを感じました。
さらにベケットは、裸舞台に木が一本という、その舞台空間の取り方もかなり刺激的だった。舞台の三方をパネルで囲んだ、いわば制度化された空間で、環境(制度)に強制されたキャラクターが登場するというのが当時の演劇の常識でしたから、セットをつくり込んだりしない「生の空間」に、得体の知れない乞食みたいな俳優の「生の身体」がポンと出てきて、そこからドラマを始めましょうというこのやり方はひどく魅力的で、この「ベケット空間」から──僕、「ベケット空間」と名づけているんですけど──当時は、唐十郎も佐藤信も、みんななんらかの影響を受けているはずだと思います。 - 「ベケット空間」から受けた衝撃とは別に、『ゴドーを待ちながら』の不条理劇としてのドラマツルギーに衝撃を受けられたということはなかったのですか。
- ドラマツルギーとしての衝撃はそれほどなかった。ヨーロッパでは、近代化の中で不条理性みたいなものを排除する方向に動いたから、不条理劇というのがドラマツルギーとしてたいへんな衝撃だったんだろうと思います。だけど、日本では近代がそれほど成熟した形で成立していないし、個人も独立した個としてそれほど確立していなかった。その上、そもそも不条理という考え方そのものが東洋ではさほど目新しいものではないでしょ。人間というものは不可解なものである、諸行無常、生々流転、といった考え方は昔からあって、不条理なセンスはほとんど生理的な了解事項として成立していたということがあります。
- 別役さんは、長い劇作家生活の中で、何回か大きな作風の変化を経ていらしています。まずごく初期の頃、「早稲田小劇場」において鈴木忠志さんの演出により発表された作品群は、たとえば老夫婦の平穏な日常に戦争直後の極限状況の姉弟が侵入してくる『マッチ売りの少女』や、被爆によるケロイドの背中を見せ物にしたいと思っている病人が主人公の『象』など、優れた日本人論・日本状況論として読めるだけでなく、個人の「タマシイ」のあり方を描いた作品として、日本の現代演劇のエポックとなっています。そこには、絶望的な孤独に耐えようとする人間の姿がありました。
- 孤独っていうのは、それはそうなんだけど、60年代の我々のような少なくとも反体制的な人間にとってよりどころになっていたのは状況に対する「恨み・辛み」だったんです「恨み・辛み」という形で「孤独であること」を理解できるときは、「孤独であること」が武器であり得た。ところが時代とともにこの「恨み・辛み」は消えていった。状況や生活がよくなったわけではないのに、社会が情報化されるなどして視野が広くなったりすると、孤独が「孤独であること」を確かめるよりどころとしての「恨み・辛み」が消えてしまう。80年代にほぼ消えてしまい、それに応じて「個」も「個」であることをやめて「孤」になっていった感がある。まとまりのある実体としての個人は消えて、人間が意識だけの「点」になってしまった気がします。そうすると作品も自ずと変わらざるを得ない。「点」である「孤」の行動意識を形にしようとすると、誰かとの「関係」のなかにしかよりどころがない。それで、個人の行動を描くのではなく、「関係」の演劇になっていったんです。
- 「早稲田小劇場」を離れてからしばらくの間、童話の『不思議の国のアリス』などをモチーフに配した、寓意性の高い、ストーリー性の豊かな作品をお書きになっていました。
-
それは、ベケットの方法論を押し進めると、どんどん作業が自閉症的になっていって、演劇が演劇でなくなると感じたものだから、意識してベケットから離れようとしたからです。自分の意識とか、内部の問題とか、内へ内へと閉じこもらざるを得ない作業がまずいと思った。僕は、演劇というのは、内へ向かうのではなくて、外へ向かって華やかに展開するものだという潜在的かつ伝統的な意識をもっているんです。だから楽しくやれたし、自分を解放できた。それが演劇の魅力だった。それで、ストーリー性を取り込んで、構造的に展開していこうとしたんだと思います。
もうひとつは、それ以前の僕のセリフの成り立ちは自己表白のモノローグ文体でできていたということがある。それが嫌になったんです。セリフに自分の私的な心情みたいなものが過度に反映されて、次の日に読み返してみると震えがくるくらい嫌悪感に駆られるようになりました。それでモノローグ文体で書けなくなり、ダイアローグ文体に変えていったら自分の演劇そのものも変わった。主人公一人がどうしたかということでなく、「関係の演劇」「関係のドラマ」になっていった、つまり、「関係」が(作品の)主人公になったんです。言うまでもなく、関係性は時代とともに変わっていくので、「現代の人間」ではなく、「現代の関係」という視点を、現代性を追求するための手がかりにしようとし始めたわけです。
- 電信柱のすぐ下にゴザを敷いて、家財道具一式を並べた家族が座り込むという奇妙な風景を描いた文学座のアトリエ公演『にしむくさむらい』あたりから、現在につながる別役演劇が花開いたという感じがあります。
-
文学座の演技陣の生活感覚あふれる演技、生活実態のある芝居が非常にマッチしました。わりと観念的な芝居だと自分でも思っていたから、さっき言った「ベケット空間」に生活感を持ち込んでも成立しないのではないかとおそれていたのですが、案に反して、生活感が濃厚になったほうが、背後にあるべき世界への予感が鋭く働くようになった。『ゴドー』にもともと予定されていた道化芝居っぽいものが、文学座の演技陣の生活実態、もっというと世話っぽい芝居みたいなものを通して、完全に日本に移し替えることができる、ということが分かりました。
- 『にしむくさむらい』もそうですが、70年代始めごろから別役作品には頻繁に「裸舞台に電信柱が一本」という舞台設定が登場します。
-
電信柱は『ゴドー』で使われている一本の木の援用です。もともとヨーロッパの舞台は横幅よりも縦のほうが長い筒型の空間になっていて、演劇が立ち上がってくる感じがする。立ち上がることによって宇宙とか、虚空とかに対する関心を醸そうとしている。『ゴドー』のような作品はそうした空間の中でしか確かめられない気がするのですが、日本の演劇は、歌舞伎に典型的に表れているように「水平」なんです。水平的にドラマが起こり、動きももっぱら左右です。そこで、その水平軸に対する「垂直軸」がどうしても必要になり、「電信柱」を建てた。建てただけでは垂直軸への感受性の鈍い日本人には、まだ垂直感覚みたいなものが生まれない。それで、街灯が点っているとか、途中から紐が張られて万国旗がぶら下がっているとか、そういうことをして初めて垂直軸を若干意識できるようになるようです。同時に、電信柱に張られたチラシがはげ落ちているとか、電信柱にリアリティを付けると、そこにある種の「生活感」が生まれ、その生活感をよりどころにして、世界全体への気配を予感させようという計画です。
僕は、こういう空間のことを「局部空間」と呼んでいるけど、要するにリアリズム演劇が用いる何の誰それの部屋といったような「典型的な場所」でもなく、崖の上といったような「象徴的な場所」でもない、また表現主義に見る「記号化された場所」でもない、「偶発的な場所」──細密画の昆虫の一本の脚みたいな場所と僕はたとえるんだけど、これは集合させても拡大させても昆虫にはならない。にもかかわらず、その一本の脚がきわめて精密に具体的に描き込まれていけばいくほど、昆虫の全体像みたいなものを何となく予感させる。同じように、空間の向こう側に広がる世界全体、あるいは宇宙のようなものへのつながりを予感させる空間が「局部空間」で、それが演劇の場所として非常に重要だと思っているんです。ベケットのつくりだした空間もそういうふうにできていたという感じがあります。
- 『にしむくさむらい』の電信柱の下で展開された家族のドラマに関して、「小市民のたたずまいを描いた」などと評されました。
- 当初は、「小市民を揶揄したり否定したりしている」と書かれたものですが、実際には、僕は日本の戦後の高度成長を支えたのは「小市民」だったと思っています。小市民というものが日本の実体だった。健全な精神の小市民をたとえるとすると、非常にきまじめで、愚直で、融通が利かないところもあるが勤勉であるという「下級武士の精神」です。にもかかわらず小市民という言葉が自嘲的に囁かれ始めたのは、小市民であることが崩壊しだしたから。その小市民の崩壊と家族の崩壊はほぼ期を一にしている。だから今、小市民や家族が埋めていた日本の根幹がぽっかり空いて実体がなくなり、日本は空洞だという感じがしていますね。
- 先ほど言われていたように「個」が「孤」になり、日本の根幹たる実体も空洞化しているとすると、それこそ待ちこがれたゴドーがやってきても体験として受け止めることのできない滑稽な状況になる。別役さんは今年、「不条理ドタバタ喜劇」という副題を付けた最新作 『やってきたゴドー』 で、そうした現代の状況をテーマにされました。もしかしたら別役さんは、そもそもベケットの『ゴドーを待ちながら』も、笑って読むべき作品だと思われているのではないですか。
-
そう思っていますね。いまだに演劇界全体に、「悲劇」が演劇の正道であるという考え方がはびこっているけど、僕は「喜劇」こそ現代を写し取るために最も有効な手法であると考えている。むしろ正道は喜劇のほうにあるのであって、悲劇というのは極端ないい方をすれば、「神と人間との対話」みたいな古い器の中で人間を計るスタイルだと思います。今では我々の日常感覚は喜劇のほうがはっきりと主流になってきているわけで、喜劇的行動パターンというものがきわめて有効な時代に入ってきていると感じます。もし『ゴドーを待ちながら』を重要な作品だと考えるなら喜劇として読み込まれるべきであるし、どうすれば『ゴドー』が喜劇として成立するかを突き詰めて書いたのが『やってきたゴドー』でした。
喜劇は、世の中全般からくだらないものだとおとしめられる傾向があるでしょ。唯一許されるのは、社会風刺が入っている場合。だけど僕のいう喜劇は、そうではなくて、社会風刺も何もない「ナンセンス喜劇」。ナンセンス喜劇こそ喜劇のなかのもっとも純粋なものであり、もっといえば、「不条理劇の究極の形はナンセンス喜劇だ」と感じる。イヨネスコの『授業』とか『椅子』なんかもナンセンス喜劇の極北だと思います。
- 別役さんの作品では、笑いがただその場かぎりで消費されてしまわずに、作品全体からある感動のようなものがちゃんとこちらに伝わってきます。それは戯曲を書くときに、別役さんの頭の中に、劇空間と対比する何か超越的なものが想定されていて、そことの緊張関係によって演劇が普遍化されるからだという気がするのですが……。
-
ありますね、超越的なものへの感触。西欧でいう「神」とは違うもので、仏教用語の「空」に通じるもの、虚空とか、虚無という言葉であらわせる何者かなんですけど。カフカがこう言っています、「神の前で常に人間は間違っている。神が間違っている場合でも、間違っているのは人間のほうである」と。間違っているのが人間のほうだけならこれは悲劇ですが、それに対して、神が間違っている場合でも、にもかかわらず間違っているのは人間の方だと言ったとき、それは喜劇になる──これが不条理喜劇の究極の姿だろうと思います。崇めるためにではなく、人間が間違っていることを確かめるために、超越的な存在に関心を持たなければいけないということはあると思います
- ところで、2003年に兵庫県にあるピッコロシアター(兵庫県立尼崎青少年創造劇場)の代表に就任されましたが、いかがですか。
-
僕は、おそらくもう60年代にやっていたような、状況全体に対して「これが現代である」と、大向こうを唸らせる大きなドラマは成立しないんじゃないかと思っています。ただひとつ救いがあるとすると「地域」で、地域特有のドラマというのは成立するという感じがします。その意味で、僕は地域にある地元の劇団が、「方言」で芝居をやり始めているのはかなり重要なことだと思っています。
方言に対して、NHK共通語といいますか、標準語といいますか、そういう言葉には「演劇的な力」というものがもうほとんどなくなっている。「言葉としての力」がなくなり、単なる意味として、記号としての作用しかなくなっていると感じます。しかし、方言には、まだ「肉感的な要素」があります。意味としてだけでなく、匂いとか響きとか、そういうものを伴った実体のある言葉として、ドラマを巻き起こすだけの力をまだもっている。かつて方言は普遍性がないものとして排除されていたけど、普遍性がないことがかえって地域のコミュニケーションの内密性みたいなものを養い、補償する手だてとなっている。地域に依拠して、地域の言葉で、ある演劇性みたいなものをつくり出す地域での活動には可能性があると感じています。
- 言語という意味で見ると、たとえば平田オリザさんが「現代口語演劇」と名づけた過剰に日常的なセリフで舞台をつくり、片方では三浦大輔さんが言葉になる前のナマな若者の姿をそのまま舞台上に晒すような芝居をやり、また岡田利規さんみたいに若者のスラングをそのまま使ったような若い演劇人たちの取り組みもあります。
-
それは、なかなか正しいあがきであるという気はします。僕は若い人たちの芝居をあまり見ませんが、それぞれがそれぞれの形で活性化された仕事をしているという感じがあるので、演劇の未来をあまり悲観してはいません。地域から新しいものが出てくるだろうし、東京でも標準語じゃないところから新しい芝居が出てくるだろうという予感があります。
- 非常に素朴な質問で恐縮ですが、映画でもテレビでも音楽でもなく、演劇というメディアだけが観客に手渡すことができる体験みたいなものがあると思うのですが。
-
ありますねぇ。やっぱり等身大の人間から等身大の人間に対して、具体的にドラマとして投げかけることができるのは、演劇という装置を通じてだけだろうと。劇場という閉鎖的な場所をくぎって、そこに集まった少数の観客にだけしか通用しないという、演劇の古さというか、不便さというか、それが結果的に幸いしたという感じがします。グローバリズムになって、日本語で喋ったらすぐ英語に転換されて、ボーダレスでどこにでも通用するものは拡散して、極端にいえば文化そのものが消費されると思います。文化が蓄積され、再生産させるための素材になるような、創造の手がかりとなるためには、むしろ演劇のような閉鎖された環境が重要だという気がする。
僕は「肉声」と言っているんだけど、世の中から「肉声」がなくなってきていると思います。「肉声」には、記号化されるとこぼれ落ちてしまう部分がそのまま残っている。西洋医学の薬と漢方薬の違いみたいなもので、必要な部分だけを抽出したものではなく、必要以外の部分も生で抽出されないまま使われる。その必要以外の部分がどう作用するのかははっきりとは分からないけど、副作用がなかったり人間に優しいといわれたり、何か重要かもしれないよというものを伝統的に持っている。演劇も、何か得体の知れないものを伝統的に持っていて、まだ抽出、抽象化されていない、その部分が重要なのだと思いますね。
別役実
日本の不条理劇の礎を築く 劇作家・別役実の果てしなき冒険
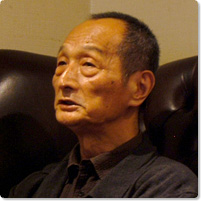
別役実Minoru Betsuyaku
1937年、旧満州(現、中国東北部)生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。日本の不条理劇を確立した劇作家として、多くの演劇人に影響を与えた。小説家、童話作家、エッセイスト。ベケットらの不条理劇に影響を受け、鈴木忠志らと劇団早稲田小劇場を創設。戯曲『象』(1962年)で注目され、『マッチ売りの少女』(1966年)と『赤い鳥の居る風景』(1967年)で第13回岸田國士戯曲賞を受賞。1971年、『街と飛行船』『不思議の国のアリス』で紀伊国屋演劇賞受賞。同年『そよそよ族の叛乱』で芸術選奨新人賞、 1987年に戯曲集『諸国を遍歴する二人の騎士の物語』で読売文学賞、1988年、『ジョバンニの父への旅』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。2007年、劇作130本を達成する。戯曲や童話の他に、生物学の常識を覆す奇書のふりをしたジョークエッセイ『虫づくし』をはじめ、日本古来、および現代の妖怪の生態を解説した『もののけづくし』や、『けものづくし』『鳥づくし』『道具づくし』『魚づくし』など「〜づくし」シリーズは、ナンセンス作家としての著者を一躍有名にした。また衝撃的な事件の闇に包まれたメカニズムを鋭敏な目で分析した犯罪エッセイ「犯罪症候群」などの独創的な論考も発表しており、その関心は森羅万象に及ぶ。
聞き手:岡野宏文
『AとBと一人の女』
初演 1961年
AとBのふたりの男が、モノローグじみた長いセリフを交互にしゃべりながら、お互いの間に生じる、根拠のない蔑みと引け目の葛藤を描く作品。AはBにハゲがあり足も不自由だと指摘する。Bは自分は頭も悪く居候までしていると卑屈に淫するが、正面切って罵倒してくれないとAに迫り、殺してほしいと哀願する。が、やがて会話はAこそ足が悪いのかもしれないといった方向に進むことで、ふたりの憎悪関係は逆転し、BがAを殺してしまう。
『マッチ売りの少女』
初演1966年
典型的な小市民的老夫婦の家庭に、ある夜、女が尋ねてくる。女はかつて街角でマッチを売っては、火の灯っているあいだスカートの裾をあげて見せていた。そうするように教えたのはあなたですね、お父さん、と男に迫る。もちろん男には覚えがない。女は、弟や子供たちまで招き入れ、さらに深く夫婦の日常を侵犯しようとする。戦争にまつわる悲惨で後ろ暗い過去を「なかったこと」にして生きる「戦後の良識」に、激しい否を突きつけた作品。
『象』
初演1962年
原爆で背中に負ったケロイドを、町中で見せびらかし、町の人々から拍手喝采を得たいと奇妙な情熱を抱く病人。彼を引き止め、人々はもう我々被爆者を愛しも憎みも嫌がりもしないんだ、ただとめどなく優しいだけなんだ、だからひっそり我慢することしかしてはいけないと説得する甥。ふたりの心の行き違いから、原爆病者の陥った閉塞状況を、ひいては人間全般の抱える存在の不安を、静けさの張りつめた筆致で描いた作品。
『アイ・アム・アリス』
初演1970年
共和制と王政の混在する国で、ある日アリスは叛乱の名目によって、王国からと政府から二重の形で追放される。追放されたアリスは、もう一度自分をアリスとして発見することで、「アリスであるもの」となり、世界に向けて「アイ・アム・アリス」の電報を発信する。管理社会の中での(芸術家の)アイデンティティは、一度名前を捨て去り、新たに自分であることを発見しない限り確立できないことを、寓話じみたスタイルで描いた作品。



『数字で書かれた物語〜「死なう團」顛末記』
初演1974年
「餓死殉教の行」と大書された額のもとにあつまった7人の男女。死ぬことを目的として籠城したかれらは、そのための時間を7人で過ごさなければならない。小さな話はやがて大きくなり、ただの遊びは命がけになって……。「一、二、三、四、五、六、七、八、九、十……」無限に数字を数え、はっきりしないまま目的へと向かう。
文学座アトリエの会「別役実のいる宇宙─新旧書下ろし連続上演」
『数字で書かれた物語〜「死なう團」顛末記』
(2007年6月15日〜7月5日/文学座アトリエ)
演出:高瀬久男
撮影:飯田研紀
『にしむくさむらい』
初演1977年
二組の夫婦とひとりの乞食の物語。ある日ふと会社に行かなくなった夫たちは、発明家になるなどとうそぶきながら、すべてにつけそのままズルズルと、何も決定しないまま時をやり過ごそうとしている。妻たちは、夫のはっきりした決意を聞きたいと迫るものの、うやむやになし崩しされ、他にどうしようもないからといって、夫の発明した「乞食を獲る」殺人装置を作動させる。



『やってきたゴドー』
初演2007年
サミュエル・ベケットの「ゴドーを待ちながら」の設定を借りた後日譚。ウラジーミルとエストラゴンの待っていたゴドーが、ある日とうとうやってくる。しかしふたりには、ゴドーのやってきたのを「認識すること」はできるのだが、内実のある出来事として「体験すること」ができない。
木山事務所公演『やってきたゴドー』
(2007年3月24日〜31日/俳優座劇場)
作:別役実
演出:末木利文
撮影:鶴田照夫



『犬が西むきゃ尾は東〜「にしむくさむらい」後日譚』
初演2007年
とめどもなく続く電信柱。そこに五人の老いた男女が、つかず離れず流れてゆく。何故かはわからないまま、どうしてもそちらへ行かなければならないのである。それぞれ、病気か故障を持っており、道中はままならない。しかもその五人は、或る過去を共有しているようなのであるが、思い出は錯綜し、それに従って関係も混乱する……。『にしむくさむらい』の続編ともいえる作品。
文学座アトリエの会「別役実のいる宇宙─新旧書下ろし連続上演」
『犬が西むきゃ尾は東〜「にしむくさむらい」後日譚』
(2007年6月15日〜7月5日/文学座アトリエ)
演出:藤原新平
撮影:飯田研紀
この記事に関連するタグ

