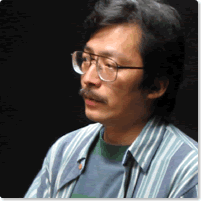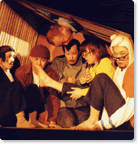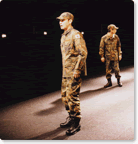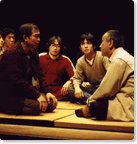- 「平穏を揺さぶる自由」──坂手洋二インタビュー
-
インタビュー当日、ちょうど前日まで「屋根裏」が上演されていた梅ヶ丘BOX(まさに「箱」と呼ぶべき鉄道高架下の小空間)で私たちは会った。「屋根裏」の舞台装置は、翌週から始まるアメリカ公演ツアーのためにすでに解体され、輸送準備が整っている。坂手さん自身もツアー最初の開催地フロリダへ向け、支度中であった。そんな彼が語ってくれたのは・・・・・・。
僕の戯曲に対するアプローチの仕方は、他の劇作家たちのそれとは微妙に違うような気がします。僕はストーリーから全体を組み立てていくのではなく、人物像からつくり始めるんです。人の一生は物語そのものよりも複雑だと思うからです。登場人物に物語を強いることは、登場人物たちから自由を奪うことになります。もちろん僕の作品にも彼らを拘束しているモラルはあるでしょうが、それは舞台を観て観客が感じるもの、観客が決めるものだと思います。
では登場人物は、ストーリーからその存在意義を与えられないとすると、どこからそれを得るのか。それは、演劇の仕組みの基本にある「認識する」ということ、つまり「言葉」によってです。「この人は人間です」と言ったり、それについて具体的に話すことによってのみ、舞台上でその存在を認識することができるのです。伝えるべき抽象概念というのもあるかもしれませんが、それを描くために表現することは、僕はあまり好きじゃない。そういう主張をすることで、劇作家の作為が見えてしまう。芝居が作為によって失われてしまう。作為によってすべてが予定調和になってしまいます。そうならないよう、細くできることはできるだけ細くしてしまって、ひとつにまとめない、ひとつで代表させないというのが僕の方法論です。
僕が最も、しかも長い間、興味をもってきたのが「転移」のプロセスです。つまり、置き換えるという作業が演劇のスタートだと考えています。たとえば俳優はある役を演じつつ、同時に別の役にもなれる。それはある人が別の身体、もしくは別のあるものに乗り移っていくという作業ですが、役者にこの転移について認知させ、転移するものについて認識させ、それを表現できる知識を与えること、それが「言葉」の役割だと思っています。つまり「言葉」は、役の個性を追求する自由を役者に与えてくれるための機能なのです。
これについては多少違和感をもつ人もいるかもしれませんが、この転移という考え方は、日本の伝統芸能の中心にあったものです。そういう意味で、夢と現実が交差する世阿弥の「複式夢幻能」という様式はすばらしいと思いますし、彼の考えは現代にも通じるものだと思います。実は、僕の大学の卒業論文は世阿弥がテーマだったのですが、ただ、実際に能を観たのはせいぜい10本程度。能そのものに魅力を感じているわけではないということを付け加えておかないとダメですね(笑)。それでも世阿弥の思想には心を動かされます。
古典には亡霊がよく出てきますが、たとえば、目の前にあるこのコーヒーカップが僕の亡霊だとすると、僕はここにいるはずなのに、(コーヒーカップを指差して)ここにも僕がいることになります。僕は本当はこのカップなのかもしれないし、カップが僕なのかもしれない。どっちが本物の僕なのか? どちらが生身の描写でどちらが亡霊なのか? 亡霊と出会うことで、僕たちは舞台上に2つのイリュージョンがあることに気づいて思考する──これが演劇の基本であり、そのことを確かめる表現を僕は目指しています。これはいわゆるリアリズム演劇の仕組みとは異質のもので、言葉、身体感覚、ジェスチャーを通した別の表現の仕組みを追求しています。
僕は、岡山に生まれ育ちました。岡山は東京という日本の文化的中心から離れている地方都市で、当時、映画館も4館程度しかなく、演劇もほとんどやってなかった。大学に入学するために18歳で上京するまで、自分が劇作家になるとは夢にも思っていなかった。初めて観た芝居は、70年代に俳優座がやったイプセンの「ヘッダ・ガブラー」で、「なんでこの芝居には年寄りばかりが出てくるんだろう」って(笑)。でも、78年ごろに観たつかこうへいの「熱海殺人事件」には度肝を抜かれました。いろいろあって、山崎哲さんの劇団「転位・21」を経て、自分のカンパニー「燐光群」を旗揚げすることになるわけです。
燐光群というカンパニー名の由来ですが、最初はなんとなく響きから入ったんですね。後になって、ラフカディオ・ハーンの文章の中に、遠くの海の波間に光が漂っているのを見て、「ある「燐光」の一点を見た」という一節があるのを知った。「ここにいる私も、宇宙から見れば、同じ燐光の一点」と言ったハーンは、この光に自分を転移させてみていたんだと思いますが、こういう部分が演劇的だなあと。もっとも、これは劇団名を付けた後で考えたこじつけですが(笑)。
僕はどちらかというと、映画少年だった。高校時代に友人たちと映画クラブをつくり、岡山では絶対に見ることのできない外国映画の上映会を企画したり、自分たちで自主映画も3本撮りました。1本は、ただひたすら走る映画。僕が映画クラブと陸上部の両方に所属していたので、いつの間にかそれがダブってしまったんですね(笑)。もう1本が、外界から隔離された3人の若者が無人島で暮らすという設定の作品で、ヘリコプターが来て”さばみそ”の缶詰を毎日空から落していく。彼らはそれだけを食べて、結局、無人島を離れられない。実はこの作品は80年代にアマチュアの8ミリ映画を対象にしたコンペティション「ぴあフィルムフェスティバル」で選ばれて上映されました。
思い返すと、僕は、昔から閉鎖状態に陥ってしまう話が好きなのかもしれない(笑)。三船敏郎とリー・マーヴィンが主演した『太平洋の地獄』とかも好きだし。これも無人島にたった二人だけでドラマが展開する映画です。密室や押入、こういうものにはそそられます(笑)。僕は、アメリカの戯曲「CVR」の日本版を演出したことがあって、これもコックピットという閉鎖的な空間が題材です。「屋根裏」もそうですが、こういうシチュエーションが好きなんですね。
カンパニーを立ち上げてからは・・・・・・ちょっと奇妙に聞こえるかもしれませんが、まずカンパニーが先にあって、芝居はその次にあるような気がしています。僕らは一つの共同体であり、小さなコミュニティーなんです。その共同体の実験が演劇であり、日本語とか、宗教意識とかもその共同体の実験として演劇で表現している。ちょっと亡霊の話に戻しますが、誤解しないでほしいのは、僕は魂を信じているわけではなく、特定の宗教意識を持っているわけでもありません。しかし、亡霊のようなイリュージョンが、ある世界に入り込むための僕なりの方法論になってきていて、きっと世阿弥もそうだったのではないかと思いますが、重要なのは、物事が変化していけば、人物も置き換わっていくということ。僕ら日本人は常に自分の枠を変えないで物事を捉えようとするので、何かが起こっても何も変わらない。とても習慣に弱くて、この習性はひどいものだと思います。
僕の芝居では、いろいろな日本の社会問題を扱っていて、いくつかは国外に及ぶテーマもあります。たとえば、死刑問題、捕鯨、沖縄の米軍基地問題、イラク戦争など。でも、日本のメディアは多くの重要な問題について黙認していて頭にくることが度々あります。メディアだけでなく、国民もそうです。沖縄の基地問題ひとつとっても、以前は強い反発があったのに、今では若い世代の中にはアメリカ人がいる方が格好良いと言ってはばからない子たちもいる。メディアがいろいろな問題を議論しないで黙認し、国民も黙認することが事態を悪化させているのです。僕は演劇をつくるというやり方でものを考えているので、これからもこうした問題をテーマにした作品を書き続けていくつもりです。今も、再来年あたりに上演する予定の芝居を書いています。棟田博の小説『拝啓天皇陛下様』を原作にした作品です。「おい、軍人はいいぜ。ただで食わせてもらえるし、金だってもらえるんだから」っていう軍人の話です。
日本には反戦自衛官という人たちがいて、ベトナム戦争や湾岸戦争に関連した服務に関して自衛隊に対して訴訟を起しています。こうした問題についてもメディアは積極的に取り上げようとはしません。僕は、この問題にも着目していて、昨年、元反戦自衛官の渡辺修孝(のぶたか)さんについての「私たちの戦争」という芝居をやりました。彼はイラクで拘束された日本人のうちの一人なのですが、僕の以前からの知り合いで、この芝居の半分は彼の実体験に基づくものです。地方公演で市が共催を下りるという事態となったのですが、言論の自由の問題にもかかわらず、記事として取り上げてくれたのは地元の新聞1紙だけでした。
日本ではこういうメディアの状態が続いていて、どんどん悪くなっています。たとえば、死刑制度についてもマスコミはめったに書きませんし、昨年、刑法改正について重要な審議が行われていたのですが(現在、日本では無期懲役の受刑者はおよそ20年で保釈されているのを、30年に引き上げるというもの)ほとんど報道されませんでした。僕は、殺人容疑のでっちあげ証言により34年間も獄中生活を送っている政治犯の星野文昭さんをモデルにした芝居「ブラインドタッチ」を書きましたが、刑務所内で恣意的に刑期を決められる無期懲役について論じているメディアを見たことがありません。
こんなに何もかも僕が演劇でやらなくてはならないのか、と時々感じるのですが(苦笑)。もっといろいろな人がでてきて、これらの問題を取り上げてくれればと思いますね。日本に自由があるかどうかを尋ねられるなら、僕は本当に分からないとしか言いようがない。今の日本人は、息を吸ったら(本当は楽になるのに)息苦しくなるんじゃないかとおそれて、息を殺しているようなところがあります。呼吸し、自己表現することができない。
「屋根裏」に登場する日本人の少女は、アンネ・フランクの自由がうらやましいと言う。彼女さらにこう続けます。「ヒトラーの暗殺計画を聞いたアンネ・フランクは、そのことを楽しみにしている」と。そして「私は、テレビの連ドラを見るのを楽しみにしている」と。自由というものは一体何なのか、本当にわからなくなります。果たして自由が人々に正しい選択や、選択する知恵を与えているのか。日本人はとくに、習慣や時勢に流されやすい。人と一緒のことをやってでこぼこが出ない、平穏を乱さないという自由を選ぶんです。
Review
天上のすぐ下──坂手洋二『屋根裏』 →今月の戯曲
ロジャー・パルバース
屋根裏に引きこもる少女が客席のなかに立ちアンネ・フランクについて語りだす。現代日本に暮らすであろうこの少女は、自分の好きに人生を選択することができる、アンネ・フランクのそれとは似もつかぬような。だが少女はアンネ・フランクの自由をうらやむ。少女は、自由とは何かを自分自身に、そして私たちに問いかけてくる。
こうした場面で「屋根裏」は高揚し、私たちが乗るべき自己反省という乗り物と化す。その意味では、同様の選択をした青年のみならず屋根裏に閉じこもるこの少女のほうが、屋根裏から彼らを救おうとする「自由な人々」よりも、社会の落とし穴をより意識的に捉えているといえる。
この空間には精巧な装置が備えられている。文字通り大きな壁の穴だ。そして演出家・坂手はすぐれた手腕でこの穴を利用し、穴は時に驚くほど柔軟なものとなる。屋根裏(attic)であるが、それは屋根のすぐ下にあるものでなく、劇中のあらゆる場面で地下になったり、空のてっぺんであったり (さらに「弟」が飛び出すとそこには大地が広がっていたり)、戦争中の防空壕として現れたりもする。登場人物が「胎児も一種の“引きこもりだ”」と言えば、屋根裏は突如として子宮にも変わる。
「引きこもり」はこの作品の軸となる言葉だ。社会から退き、部屋に隠る日本の若者たちのことだ。彼らはたいがい両親と住んでいる。しかし冒頭から明らかだが、坂手は現代日本の習俗に向き合う単なる社会の解説者をはるかに超えている。あるとき少女の女教師が家庭訪問する。むやみに孤立せず学校に戻るよう少女を説得しようとするが、ここで笑いを誘う場面に変わる。“大人”社会のいじめに悩むこの教師は、ついに感極まり、少女に許しを請いながら、外界をシャットアウトしてしまいたいという自分の引きこもり願望を吐露する。
日本人は苦手だと思われがちのブラックユーモアが、あらゆる場面で提示される──ある青年の過保護な母親が登場する場面でこの母親は、息子が深刻な神経症や広場恐怖症に悩まされていても、とにかく自分のそばにいてくれればそれでもいいと思っている。テレビの刑事番組のキャラクターにあこがれる二人の刑事。段ボールの「屋根裏」に暮らすホームレスに近い家族。2023年のニュース番組。吹雪に遭った山小屋。棺と化した屋根裏にいる“死体”の大げさでコミカルな演技。屋根裏が時代劇パロディーの舞台にもなり(サムライは部屋が狭くて刀が抜けないが!)……。坂手の屋根裏はいわば、日本社会の縮図でありながら、明らかに私たちが生きる時代の生活そのものを示している。
音響・照明を含む坂手の空間操作は、実に鮮やかで独創的だ。身体的であろうが、精神的であろうが、屋根裏という領域が光と音によって空間と場面の意図を明示し、われわれの心理をはっきりと浮かび上がらせる。
役者の肉体と発声も見事だ。全体の調和をとってもスタイルといいリズムといい、すばらしい一体感をもった彼らの動きは、非常に明快でありながら無駄に気どることのないジェスチャーをもって、彼らのいる屋根裏をいっそう明確なものにする。彼らの身体法は、私が何年も前に見たポーランド・ヴロツワフのイェジィ・グロトフスキー劇団を思わせるものだ。
この作品で坂手は日本から遠くを見つめている。茶の間で見られる低俗な日本のテレビ番組があるかと思えばカスパー・ハウザーなどの歴史的人物を描いてみたり、世界から不本意にも隔離されたアンネ・フランクまでも登場させたりする。女教師が訪問する場面で少女がベッド脇の小さなスタンドをプラネタリウムのプロジェクターに変えると、劇場全体が満天の星であふれる──その瞬間、坂手の屋根裏が私たちの想像力をどこへでも連れて行ってくれることに気づく。
坂手は狂気とシリアスの要素を組み合わせ、リリカルな日常を生む。特に美しいモノローグが二つあった。ひとつは「夢は続く……終わることなく……」と、私たちに語りかける。私たちは、屋根裏で自殺した青年が手に持っていたのは、武器でも棒でもなく、絵筆だったことを知る。そして、坂手の屋根裏がいたるところにあるのなら、屋根裏の壁に描かれた若い芸術家の自画像はまさに、何万年も前に古代の人々が洞窟に残した壁画のごとく、私たち一人ひとりの肖像なのだということを知る。
坂手の「屋根裏」は、あらゆる意味でいたる所に存在するのだ。